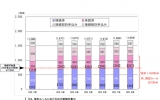暗雲漂うCOP29

COP29 HPより
6月にボンで開催された第60回気候変動枠組み条約補助機関会合(SB60)に参加してきた。SB60の目的は2023年のCOP28(ドバイ)で採択された決定の作業を進め、2024年11月のCOP29(バクー)で採択する決定の準備作業を行うことにある。
資金問題と先進国・途上国の対立
COP29は「資金COP」とされている。2015年にパリ協定に署名した際、既存の年間1000億ドルという目標に代わり、「気候変動資金に関する新たな集団的定量化目標」(NCQG)を設定することを決定した。NCQGはCOP29で採択されることになっており、途上国が2025年に提出が必要な次期NDCの野心レベルを高めるために大きな役割を果たす。
先進国は1.5℃目標、2050年カーボンニュートラル等、温度目標、削減目標に強いこだわりを持っているが、途上国が温暖化交渉に参加する最大のモチベーションは先進国からの資金援助である。
COP28で採択されたグローバルストックテイクに関する決定文には2025年ピークアウト、2030年▲43%、2035年▲60%(いずれも2019年比)、2030年までに再エネ設備容量3倍、エネルギー効率改善2倍、化石燃料からの移行等、1.5℃目標を射程に入れるための緩和面での野心的なメッセージが盛り込まれた。
しかし同時に決定文には途上国の現在のNDCを実現するために2030年までに約6兆ドルの資金が必要、2050年全球カーボンニュートラルを達成するためには2030年までに年間4.3兆ドル、その後2050年まで年間5兆ドルの投資資金が必要との途方もない数字が含まれている。
今後の温室効果ガス排出の帰趨をにぎる途上国は先進国に対して「野心的な削減を求めるのであれば、先立つもの(金)をよこせ」と請求書をつきつけているのだ。
SB60での議論と未来への懸念
今回の補助機関会合の議論を聞いている限り、COP29の見通しは暗いと言わざるを得ない。NCQGについては共同ファシリテーター(豪州、南ア)の下で4回、議論されたが、先進国、途上国がそれぞれの立場を主張するのみで全く進展が見られなかった。各国の主張を羅列したインプットペーパーが作成されたものの、交渉テキストにはとてもなっていない。
今回の会合で最も議論が紛糾したのは、気候資金のドナーの範囲と受益国の範囲である。先進国は気候資金への貢献主体を先進国のみならず、経済力を有する新興国にも広げるべきであり、気候資金の受益国は島嶼国や後発発展途上国等のぜい弱国に絞るべきであると主張した。
これに対し途上国は資金援助は枠組み条約、パリ協定上の先進国の義務であり、ドナーの拡大という議論は先進国の責任逃れである、気候資金の受益国を限定すべきではなく、全ての途上国にアクセスを認めるべきであると主張した。
これはパリ協定交渉時にさんざん議論されたことであり、
- 「先進締約国は、条約に基づく既存の義務の継続として、緩和と適応に関連して、開発途上締約国を支援する資金を提供する(shall)」(9条1項)
- 「他の締約国は、自主的な資金の提供又はその支援の継続を奨励される(encouraged)」(9条2項)
- 「世界的な努力の一環として、先進締約国は、公的資金の重要な役割に留意しつつ、広範な資金源、手段、経路からの、国の戦略の支援を含めた様々な活動を通じ、開発途上締約国の必要性 及び優先事項を考慮した、気候資金の動員を引き続き率先すべき。気候資金の動員は、従前の努力を超えた前進を示すべき」(9条3項)
- 「規模を拡大した資金の供与については、適応のために公的なかつ贈与に基づく資金が必要であることを考慮しつつ、各国主導の戦略並びに開発途上締約国(特に、気候変動の悪影響を著しく受けやすく、及び著しく能力に制約があるもの。例えば、後発開発途上国及び開発途上にある島嶼(しよ)国)の優先事項及びニーズを考慮に入れて、適応と緩和との間の均衡を達成することを目的とすべき」(9条4項)
という形で決着している。妥協の結果、出来上がった条文の執行について再びそもそも論をやっているようでは先が思いやられる。
先進国と途上国の認識ギャップ
途上国は市場金利での融資や市場利回りでの民間資金フローはNCQGに含まれるべきではなく、先進国からの無償資金もしくは譲許的な資金でなければならないと主張し、NCQGの具体的なレベルとして年間1兆ドル超の数字を提示しているが、先進国は民間部門からの資金、多国間開発銀行の改革、各国の国内支出(化石燃料補助金を含む)等の協議が必要と主張し、具体的な数値目標の議論に応じていない。
厳しい財政状況を抱え、ウクライナ戦争等による安全保障環境の不透明化で軍事支出の拡大を強いられている先進国にとって気候資金の大幅拡大に応じられないのは無理もない。民間資金フローの重要性を強調するのはそれが理由だが、民間資金に着目すれば、必然的に「途上国が民間投資フローを期待するのであれば、自国の投資環境を改善せよ」ということになり、資金目標の確実性がなくなる。途上国から見れば先進国が資金目標の議論を遅延させ、途上国に「責任転嫁」していると映る。
温暖化交渉の本質は、温室効果ガス削減目標を最重要視する先進国と資金援助を最重要視する途上国のあくなき戦いである。全員一致の合意を目指す以上、両者の要求をパッケージで解決することが鉄則だ。
COP28でのグローバルストックテイクの議論はまさしくそのような妥協の産物であった。しかし途上国が最重要視するNCQGの合意を目指すCOP29においては、先進国がNCQGの見返りに取りたい成果が余りない。
先進国は新興国の野心レベル引き上げを働きかけるメカニズムを構築したいと考えているが、中国、インド等の有志途上国の強い主張により、緩和作業計画はセミナー開催、グローバルストックテイク年次対話はベストプラクティスの共有といった情報交換の場に「矮小化」されている。
COP27で発足した「公正な移行作業計画」、COP28で設立が決まった「UAE対話」を使ってエネルギー転換の加速を促そうと目論んでいるが、途上国は「公正な移行作業計画」を更なる支援拡大の起爆剤に使おうとしており、「UAE対話」はグローバルストックテイク決定文の「資金」の章で位置付けられており、エネルギー転換はマンデート外であると主張している。何よりも先進国と途上国の間ではNCQGの水準をめぐって文字通り「桁違い」の認識ギャップがある。
結論と今後の見通し
こう考えるとCOP29ではNCQGに合意できない可能性が十分ある。上述のようにNCQGは2025年に提出される途上国のNDCの野心レベル引き上げを可能にするとのとの位置づけであったため、途上国側がNCQG合意失敗を理由に、国別目標見直しの野心レベルを下げ、その責めを先進国に帰することは確実であろう。
6月の欧州議会選挙では温暖化対策に懐疑的な右派、極右政党が大きく議席を伸ばした。域内で問題山積の中で途上国支援を大幅に拡大することはますます難しくなるだろう。仮に11月の米大統領選でトランプ政権が復活すれば、米国は気候資金を一切出さなくなる。途上国が期待するような資金フローがなされる可能性は限りなく低い。
筆者は本コラムにおいて繰り返し「1.5℃目標は死んだも同然」と述べてきた。
COP29ではそれがますます明らかになるだろう。1.5℃目標を所与の前提とした日本のエネルギー温暖化政策についてもこうした現実を踏まえたものであるべきだ。

関連記事
-
気候変動対策のひとつとして、世界各地で大規模な太陽光発電や風力発電プロジェクトが計画されている。しかし、経済的要因や政策の変更、環境への影響などから、こうしたプロジェクトが撤退や中止に至っているケースも多い。 有名な事例
-
オーストラリアの東にあるグレートバリアリーフのサンゴ礁は絶好調だ。そのサンゴ被覆度(=調査地域の海底面積におけるサンゴで覆われた部分の割合)は過去最高記録を3年連続で更新した(図)。ジャーナリストのジョー・ノヴァが紹介し
-
民主党・野田政権の原子力政策は、すったもんだの末結局「2030年代に原発稼働ゼロを目指す」という線で定まったようだが、どうも次期衆議院選挙にらみの彌縫(びほう)策の色彩が濃く、重要な点がいくつか曖昧なまま先送りされている。
-
きのうのアゴラシンポジウムでは、カーボンニュートラルで製造業はどうなるのかを考えたが、やはり最大の焦点は自動車だった。政府の「グリーン成長戦略」では、2030年代なかばまでに新車販売の100%を電動車にすることになってい
-
2018年4月8日正午ごろ、九州電力管内での太陽光発電の出力が電力需要の8割にまで達した。九州は全国でも大規模太陽光発電所、いわゆるメガソーラーの開発が最も盛んな地域の一つであり、必然的に送配電網に自然変動電源が与える影
-
自民党萩生田光一政調会長の発言が猛批判を受けています。 トリガー条項、税調で議論しないことを確認 自公国3党協議(2023年11月30日付毎日新聞) 「今こういう制度をやっているのは日本ぐらいだ。脱炭素などを考えれば、あ
-
アゴラ研究所の運営するエネルギー調査期間のGEPRはサイトを更新しました。
-
先日3月22日の東京電力管内での「電力需給逼迫警報」で注目を浴びた「揚水発電」だが、ちょっと誤解している向きもあるので物語風に解説してみました。 【第一話】原子力発電と揚水発電 昔むかし、日本では原子力発電が盛んでした。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間