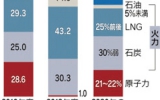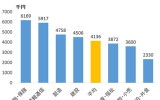産業立国ドイツの危機と欧州の行方
加速するドイツ産業の国外移転
今年6月のドイツ産業連盟(BDI)が傘下の工業部門の中堅・中手企業を相手に行ったアンケート調査で、回答した企業392社のうち16%が生産・雇用の一部をドイツ国外に移転することで具体的に動き始めており、さらに30%が国外移転計画を検討していることがわかった注1)。
またドイツ産業の屋台骨を支える自動車産業連合会(VDA)が5月に公表したやはり中堅・中小部品企業に対するアンケート結果(128社が回答)でも、5%が国内投資を中止し、27%が国外投資に変更するとしている(うち43%がEU域内他国、30%が北米への投資を計画)という。
こうしたドイツ国外への移転の理由として6割を超える企業が「エネルギー・原料価格の高騰」を挙げているという。VDAの副会長は、自動車産業の中小企業支援のために、エネルギーコストの削減策の必要性を政界に求めているという注2)。

Ilari Nackel/iStock
もともと地場で事業活動をし、国内市場に依存するケースが多い中堅・中小企業ですら、こうした状況にある中で、国際市場でグローバルなビジネスを展開しているドイツの化学、自動車といった基幹産業は、既に雪崩を打って海外に製造拠点をシフトし始めている。
世界最大の化学メーカーBASFは総額100億ユーロ(1.5兆円超)を投じて、中国南部の軍港の街、湛江に巨大な化学コンビナートを建設しており、またフォルクスワーゲンも71億ドルを北米に投じてEV生産に乗り出すと発表し、BMWは17億ドルを投じて米国でEV生産工場を立ち上げることを発表している。
ドイツの直面しているエネルギー危機
こうした動きの背景にあるのが、ドイツの直面しているエネルギー危機である注3)。ドイツのエネルギーというと日本の新聞では、同国が2010年から脱炭素政策の目玉として進めてきたEnergiewende(エネルギー転換政策)の「成果」が成功例として喧伝され、太陽光、風力といった再エネの普及拡大の模範生とされてきた。
しかし現実には、2021年時点のドイツの一次エネルギー消費全体に占める再エネの比率は16%にとどまり、依然エネルギーの76%が石油、石炭、天然ガスといった化石燃料によって賄われている(2021年実績注4))。原子力は21年時点で8%、天然ガスが27%を賄っていた。それが2022年5月に始まったロシアによるウクライナ侵攻以降、大きく様変わりしてしまう。
ドイツは気候変動対策の鍵として、2000年以降石炭依存を大きく下げてきたが、その代替となったのが再エネ拡大と天然ガスへの転換であり、特にロシアから海底パイプラインを通じて輸入される安価で潤沢な天然ガスの安定供給が重要な役割を果たしてきた。ロシア産の安価なパイプライン天然ガスは、同国のエネルギー供給の中で最も低コストだった石炭を代替していく際の、エネルギーコスト上昇抑制に貢献してきたのである。
これがウクライナ戦争によるロシア産天然ガスのボイコットにより使用できなくなり、さらにノルドストリームパイプラインの破壊によって、長期的な安定供給の目途が立たなくなってしまった。その代替のために急遽米国や中東から輸入しはじめた天然ガスは、コストが数倍に跳ね上がるLNGになることから、安価な天然ガスを前提としたドイツの産業競争力モデルの前提が実質的に破綻してしまっているのである。
上記のBASFがドイツ国内のルードウィヒスハーフェンに持つ、世界最大級の化学コンビナートは、このロシアからくる安価な天然ガスを原燃料として、アンモニア肥料や様々な化学品を競争力あるコストで大量生産し、欧州域内外の市場に販売してきたのであるが、同社は今年2月に、安価なロシア産天然ガスのこない未来に適応するためのコスト削減策として、2600人(2%)の人員削減を打ち出し(うちルードウィヒスハーフェンでは700人削減)、一部操業ラインの閉鎖も発表している注5)。
あの独裁者を彷彿とさせるドイツのリーダーたち
このように昨年来、エネルギーの危機が顕在化している最中であるにもかかわらず、ショルツ政権は、メルケル政権下で縮小してきたとはいえ依然8%のエネルギーを国内に供給していた3基の原発を、公約通り今年4月に全停止させて廃炉にする政治判断を行い、エネルギー安全保障上の危機的事態を自ら悪化させている(これに対して国内産業からは不満と不安の声が上がっている)。
欧州最大の工業生産国であり、EU経済をけん引してきた産業立国としてのドイツが、その産業の生産活動を維持するために必要な、莫大なエネルギーを安価・安定的に供給してきたパイプライン天然ガスの供給をウクライナ戦争で失い、その代替機能をもつ石炭と原子力を脱炭素政策と環境政策を理由に自ら排除して、不安定で低密度な再エネに置き換えていくという政策にまい進している姿は、外から客観的に見ても非常に危ういものに見える注6)。
そしてそのエネルギー危機の前線にいて、価格高騰と供給危機を実感しているドイツ産業は、こぞって国外逃避を始めている、という姿が上記のアンケート結果に表れているのではないだろうか。実際、こうした事態を背景にして、IMFはG7国の中で唯一、ドイツの2023年GDP成長率がマイナスになることを予想していて、かつての「欧州の病人」の再来がささやかれ始めている。
そうした中にあって、ショルツ独首相は、夏休み前のテレビインタビューで、こうしたドイツ産業経済への懸念を司会者から向けられても、楽観的な態度を崩さず、「明るい未来が待っている」として、「国民は自信をもって落ち着いていればよい。」と繰り返していたということである注7)。

以前筆者は、第二次大戦末期を描いた「ヒトラー~最後の12日間」という映画(2004年)を見たことがある。
その中で、帝国首都ベルリンが連合軍に包囲され、もはや陥落間際という危機的状況の中で、ブルーノ・ガンツ演じる総統ヒトラーが、地下の司令部にこもり、ドイツ軍と政権幹部たちを相手に「諸君、恐れることはない!西部戦線に展開している〇〇将軍(名前は記憶にない)の果敢な戦車部隊が、電撃的な勝利を挙げながらたちまちベルリンの守備を固めに来るだろう!」といった言葉(筆者の記憶なので正確ではないが)を叫ぶ姿が強く印象に残っているのだが、上記を聞いてこのシーンが思い起こされた。
極右の独裁者ヒトラーと社会民主党中心のリベラル連立政権のショルツ首相は、まるで正反対の存在なので、連想するのは大変失礼かとは思いつつも、危機に直面しての国の主導者の態度として、不思議と似ていないだろうか・・。
欧州は歴史的なターニングポイントを迎えているのか?
筆者は先日、欧州を訪問した際、かねてからの知人で顕学の、ある英国人国際政治・地政学者と懇談する機会があったのだが、彼は現在の欧州情勢を極めて憂慮するとともに、欧州が歴史的な転換点に来ているかもしれないと言っていた。
EU統合を実質的に牽引してきたのは英仏独の3か国であるが、今や英国はEUから離脱し、フランスは内政分断とアフリカ情勢の混乱からEUどころではなくなっており、そして経済の雄ドイツがエネルギー政策の自滅的な誤りから再び「欧州の病人」に陥ることで、EU統合の求心力は急激に失われてきていると指摘。
その一方で、ロシアによるウクライナ侵攻で火のついた欧州の地政学の重心は、バルト海を囲んで、欧州北方海域の安全保障を握るポーランドと、新たにNATOに加盟するスウェーデン、フィンランド(いずれも強力な軍備を持つ)の3か国に移っていくのではないかというのである。
特にポーランドは(ウクライナと共に)欧州最大級の陸軍力も保持する一方で、カーボンニュートラル政策については欧州の劣等生と見られてきた反面、潤沢な国産石炭による安価・安定的なエネルギー自給が当面の間可能であり、加えて近年は原子力導入にも積極的なため、ドイツに代わる欧州域内の産業立国としての潜在力を持ち始めているというのである。
仮に同氏が言うように、かねてからエネルギー政策で英仏独とは異なる立場を主張してきたポーランドや、最近になって左派政権から右派政権に政権交代が進んだスウェーデンとフィンランドが、欧州内で発言権を持つようになってくるとすると、従来の中道左派リベラル政権を中心として進められてきた欧州政策の風向きは、今後次第に変わっていくのではないかという見立てである。
そうした大きな文脈で見ると、目下進行中のドイツのエネルギー危機と脱産業化の波は、欧州のみならず世界的な地政学にも、地殻変動をもたらす契機となる可能性を秘めているということで、注視していく必要があるのかもしれない。
■
注1)JETROビジネス短信 (2023年6月14日)
注2)JETROビジネス短信 (2023年6月2日)
注3)実際にはドイツ産業にはもう一つ、構造的な労働力供給の危機もあるのだが、話が長くなるので本稿ではエネルギー危機に限って論じている。
注4)出典:ドレスデン情報ファイルhttp://www.de-info.net/kiso/wirtschaftspltk00.html#energie
注5)「BASFコスト削減で2600人削減へ」(Bloomberg 2023年2月24日)
注6)その辺の経緯は、以前も拙文「ドイツ産業の皆さん、日本へようこそ」(アゴラ言論プラットフォーム 2022/08/24)で紹介した。
注7)川口マーン恵美「ベンツ、BMW、VWが“ドイツ脱出”・・世界有数の優良企業がドイツ国内から次々と逃げ出す残念過ぎる理由」(PRESIDENT Online 2023/09/15)

関連記事
-
GEPRはエネルギー問題をめぐる情報を集積し、日本と世界の市民がその問題の理解を深めるために活動する研究機関です。 福島の原発事故以来、放射能への健康への影響に不安を訴える人が日本で増えています。その不安を解消するために
-
運転開始から40 年前後が経過している原子炉5基の廃炉が決まった。関西電力の美浜1、2号機、日本原子力発電の敦賀1号機、中国電力島根1号機、九州電力玄海1号機だ。これは40年を廃炉のめどとする国の原子力規制のルールを受けたものだ。ただしこの決定には問題がある。
-
米軍のイラク爆撃で、中東情勢が不安定になってきた。ホルムズ海峡が封鎖されると原油供給の80%が止まるが、日本のエネルギー供給はいまだにほとんどの原発が動かない「片肺」状態で大丈夫なのだろうか。 エネルギーは「正義」の問題
-
経済産業省は4月28日に、エネルギー源の割合目標を定める「エネルギーミックス」案をまとめた。電源に占める原子力の割合を震災前の約3割から20−22%に減らす一方で、再エネを同7%から22−24%に拡大するなど、原子力に厳しく再エネにやさしい世論に配慮した。しかし、この目標は「荒唐無稽」というほどではないものの、実現が難しい内容だ。コストへの配慮が足りず、原子力の扱いがあいまいなためだ。それを概観してみる。
-
バイデンの石油政策の矛盾ぶりが露呈し、米国ではエネルギー政策の論客が批判を強めている。 バイデンは、温暖化対策の名の下に、米国の石油・ガス生産者を妨害するためにあらゆることを行ってきた。党内の左派を満足させるためだ。 バ
-
田中 雄三 温暖化は確かに進行していると考えます。また、限りある化石燃料をいつまでも使い続けることはできませんから、再生可能エネルギーへの転換が必要と思います。しかし、日本が実質ゼロを達成するには、5つの大きな障害があり
-
「再エネ100%で製造しています」という(非化石証書などの)表示について考察する3本目です。本来は企業が順守しなければならないのに、抵触または違反していることとして景表法の精神、環境表示ガイドラインの2点を指摘しました。
-
2月の百貨店の売上高が11ヶ月振りにプラスになり、前年同期比1.1%増の4457億円になった。春節で来日した中国人を中心に外国人観光客の購入額が初めて150億円を超えたと報道されている。「爆買い」と呼ばれる中国人観光客の購入がなければ、売上高はプラスになっていなかったかもしれない。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間