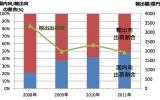再生可能エネルギーのリサイクル問題、ドイツの現状

muhammet sager/iStock
東京都や川崎市で、屋上に太陽光パネル設置義務化の話が進んでいる。都民や市民への事前の十分な説明もなく行政が事業を進めている感が否めない。関係者によるリスク評価はなされたのであろうか。僅かばかりのCO2を減らすために税金が使われようとしているが、国民の間で不公平感は生まれないのであろうか。また、パネルや部品の調達先など、多くの問題が指摘されている。課題の一つがパネルの廃棄処分である。
今回は、太陽光パネルを含め、再生可能エネルギー先進国であるドイツの現状を概説する。
補助金が終わり、太陽光パネル設備が解体・廃棄される
ドイツではエネルギー転換を加速し、2030年までに転換率を電力需要の80%まで拡大、2045年までに必要な電力をすべて再生可能エネルギーで賄おうとしている。再エネの中でも太陽光発電と風力発電の貢献度が高いといわれる。
ドイツにおける太陽光発電の普及はこの20年間で急激に進んだ。国内の発電設備容量は114メガワットから59,000メガワット近くまで増加した。現在、これら設備の多くは国の補助金の対象外となっている。技術的には運転できるのだが、大規模ソーラーパークを運営する事業者にとっては、もはや採算に合わない状態である。これから、毎年多くの設備が解体されていくことになり、多くのモジュールが撤去され、新しいモジュールに置き換えられたりする。
フラウンホーファー研究機構のシリコン太陽光発電研究センターによれば、「2002年に設置したものが2022年に撤去され回収される予定だが、今後の10年間で年間50万トンもの古いモジュールが蓄積される」ということだ。
リサイクルができず、貴重な原材料が失われる
ドイツ政府は電気電子機器法によって、太陽光発電システムのリサイクル率を80%以上と定めており、これはパネルを構成素材のうち、ガラスとアルミについては達成されている。
太陽電池(セル)は、プラスチックフィルムに封入されているため、機械的・化学的な分離が難しく熱処理は可能であるが、良質の排ガスフィルターが必要だという。シリコンや銀などの有価物の回収は、原理的には可能だが、経済的な理由から実用化されていない。
風力発電のリサイクル問題
ドイツの陸上風力タービンの数は、2001年から2021年の間に11,438基から28,230基へと倍増し、現在、累積設置容量は約57,000メガワットになった。20年前に建設された風力タービンのほとんどは、国の補助金がなくなるために、経済的に運転できなくなっている。
修理や保全、その他の費用が売電収入よりも高くなり、事業者はプラントの解体を迫られている。連邦環境庁は、今後10年間で、ローターブレードの廃棄物が年間最大20,000トン、2030年には年間50,000トンに達すると予想している。
同研究機構の風力システム研究所によれば、ローターブレードは、一体型設計で製造された強化プラスチックで作られているので、原理的に複合材料を分離することは可能でも、まったく経済的ではないという。
当初、企業は、解体された風力タービンの最大80%をリサイクルできると宣伝していた。しかし、現在でも循環経済は確立されていない。実際にリサイクルされているのは、スチールなどの金属のみで、ネオジムなどの貴重なレアメタルを含む発電機の磁石でさえ、リサイクルできていない。
また、コンクリート支柱は粉砕される利用されているが、品質が良くないため、路盤材などの用途に限定される。コンクリートの基礎部分は、そのまま地面に放置されたままである。さらに、SF6など、廃棄が困難な有害物質も排出される。
膨大な廃棄物の山ができる
業界は何年も前から「100%リサイクル可能な工場を建設する」と言い続けてきた。しかし、太陽光や風力発電設備のリサイクル・プラントは実現されていない。
両設備とも、製造時に消費したエネルギーより多くのエネルギーを生み出すことはできるが、設備の寿命が来れば、残るのは、リサイクルできない巨大なゴミの山である。
我が国の太陽光パネルの廃棄物・リサイクル問題
太陽光パネルは、25~30年で劣化し廃棄される。2012年導入された固定価格買取制度(FIT)が2032年には20年の期限を迎え、廃棄パネルが急増するといわれている。環境省リサイクル推進室の推計によれば、2015年の2,351トンから2040年は80万トンになるという。
太陽光パネルは鉛、カドミウム、セレンなどの有害物質を含んでいるため、産業廃棄物として処理される。また、太陽光パネルのリサイクル事業も始まっており、架台のスチールやレールのアルミ、パネルに使用されているガラスなどは再利用されている。その他の多くは「埋め立て廃棄」であり、今後埋め立て処分場の残余容量は不足し、廃棄パネル問題が深刻化するのは必至である。
政府の補助金(原資:再エネ賦課金など)を所与のものとして運営される再生可能エネルギーの横展開、「金の切れ目が縁の切れ目」で、廃棄パネルが山積みされるという事態に陥らないよう、設置義務化という拙速な事業の見直しを含め、将来のリスクを見通した十分な検討が必要である。

関連記事
-
私は太陽光発電が好きだ。 もともと自然が大好きであり、昨年末まで勤めた東京電力でも長く尾瀬の保護活動に取り組んでいたこともあるだろう。太陽の恵みでエネルギーをまかなうことに憧れを持っていた。いわゆる「太陽信仰」だ。 そのため、一昨年自宅を新築した際には、迷うことなく太陽光発電を導入した。初期投資額の大きさ(工事費込み304万円)には少々尻込みしたが、東京都と区から合わせて約100万円の補助金を受けられると聞いたこと、そして何より「環境に良い」と思って決断した。正確に言えば、思考停止してしまった。
-
私は友人と設計事務所を経営しつつ、山形にある東北芸術工科大学で建築を教えている。自然豊かな山形の地だからできることは何かを考え始め、自然の力を利用し、環境に負荷をかけないカーボンニュートラルハウスの研究に行き着いた。
-
福島の1ミリシーベルトの除染問題について、アゴラ研究所フェローの石井孝明の論考です。出だしを間違えたゆえに、福島の復興はまったく進みません。今になっては難しいものの、その見直しを訴えています。以前書いた原稿を大幅に加筆しました。
-
シナリオプランニングは主に企業の経営戦略検討のための手法で、シェルのシナリオチームが“本家筋”だ。筆者は1991年から95年までここで働き、その後もこのチームとの仕事が続いた。 筆者は気候変動問題には浅学だが、シナリオプ
-
これは今年1月7日の動画だが、基本的な問題がわかってない人が多いので再掲しておく。いま問題になっている大規模停電の原因は、直接には福島沖地震の影響で複数の火力発電所が停止したことだが、もともと予備率(電力需要に対する供給
-
【要旨】日本で7月から始まる再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)の太陽光発電の買取価格の1kWh=42円は国際価格に比べて割高で、バブルを誘発する可能性がある。安価な中国製品が流入して産業振興にも役立たず、制度そのものが疑問。実施する場合でも、1・内外価格差を是正する買取価格まで頻繁な切り下げの実施、2・太陽光パネル価格と発電の価格データの蓄積、3・費用負担見直しの透明性向上という制度上の工夫でバブルを避ける必要がある。
-
大竹まことの注文 1月18日の文化放送「大竹まことのゴールデンタイム」で、能登半島地震で影響を受けた志賀原発について、いろいろとどうなっているのかよくわからないと不安をぶちまけ、内部をちゃんと映させよと注文をつけた。新聞
-
3月上旬に英国、ベルギー、フランスを訪問し、エネルギー・温暖化関連の専門家と意見交換する機会があった。コロナもあり、久しぶりの欧州訪問であり、やはりオンライン会議よりも対面の方が皮膚感覚で現地の状況が感じられる。 ウクラ
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間