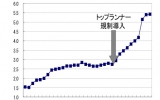「脱炭素と気候変動」の理論と限界⑤:法則科学か設計科学か

Trifonov_Evgeniy/iStock
「法則」志向の重要性
今回は、「ドーナツ経済」に触れながら、社会科学の一翼を占める経済学の性格について、ラワースのいう「法則の発展を目的としない」には異論があるという立場でコメントしよう。すなわち「法則科学か設計科学か」という問題である。
(前回:「脱炭素と気候変動」の理論と限界④)
手元にある簡単な科学年表(アシモフ、1989=1996:44)を見ると、現在のいわゆる自然科学分野では、中学生ならみんな知っている「アルキメデスの原理(浮力の原理)」(260B.C.)時代から「法則」志向があったことが分かる。
「真理の連鎖全体」追究の先にある「法則」
時が移りデカルトもまた、人の生体や自然界の「真理の連鎖全体」の哲学を通して、神が定めた「法則」を認めた(デカルト、1637=1997:58)。「訳注」によれば、これは「自然法則、さらには論理学や数学の法則。神が永遠真理として創造し、われわれの精神に生得的に刻み込み、物質世界にも及んでいる」(同上:119)とされる。
確かに対象とした自然現象や社会現象に潜む「真理の連鎖全体」の把握こそ、自然科学や社会科学の究極の目的であると私は考える。
その他紆余曲折はありながらも、論理学や数学を超えて医学や今日でいう社会科学でも「法則性」が探求されてきた。たとえばマルクス(1818-1883)とほぼ同時代を生きた医学者ベルナール(1813-1878)『実験医学序説』(1865)では、「法則が我々に与えるところのものは、原因結果の数量的関係である。また科学の停まるべき目的もそこにある」(ベルナール、1865=1970:114)とのべられている。あるいは「科学は何をおいてもまず事実について一致することを要求する。事実こそは、我々がその上に立って考慮をめぐらすべき基礎であるからである」(同上:306)。
このような内容がちりばめられた「実験医学」を「社会調査」に読み替えるだけで、ベルナールのこの名著は現代社会学の実証性を考える際にきわめて有用な古典にもなる。
「なまの事実と科学的事実」の観察と思索
ベルナールより41歳若いポアンカレは、数学者・天文学者というよりも「最後の万能学者」(ポアンカレ、1905=1977)であった(訳者あとがき:291)。
そこでも法則は、「もしすべてこれらの条件が満足されるならば、これこれの現象が起こるであろう」という表現になる(同上:261)とした。そのためには、「われわれはあらゆる事実を知ることはできない。よって、知るに価するような事実を選び出さなければならない」(同上:287)という判断により、「なまの事実と科学的事実」(同上:234)間の観察と思索を繰り返すことになる。
なぜなら、「科学的事実なしには科学はあり得ないし、科学的事実はなまの事実の翻訳にほかならない以上、なまの事実なしには科学的事実もあり得ないからである」(同上:243)。もちろん「なまの事実」が間違っていたら、「科学的な事実」には翻訳できない。
温暖化関連の「なまの事実」への疑い
ベルナールやポアンカレの「事実」論をもとに現今の「二酸化炭素地球温暖化」論を見てみると、「直接観察された正しい事実」と「推論によって得る間違った事実」との区別が役に立つ。なぜなら「二酸化炭素地球温暖化」論の内容のほとんどが、30年先や80年先の「推論」によって得られているからである。地球温暖化の先触れの「なまの事実」として扱われてきた「北極の海氷面積の縮小」や「氷河の縮減」もまた、温暖化指標としては疑問を持つ立場も存在する。
たとえば、杉山は観測データと統計データを駆使して、以下のような温暖化関連の「なまの事実」さえも否定する(杉山、2022)。
- 北極の海氷が無くなって絶滅すると言われたホッキョクグマはじつは増えている。
- 温暖化によって海面上昇で沈没すると言われたサンゴ礁の島々は沈んでなどいない。
- 温暖化で激甚化しているとされる台風は強くなっていない。
「なまの事実」でもなく、「推論」だけで組み立てられた地球温暖化の主張では、国際環境経済研究所WEB「要約版」の末尾で触れたフランス語の文章、“C’est de la simulation.”(見せかけのごまかし)の危険性が常在することになる注23)。
コントの「予見するために見る」
その後ポアンカレは『晩年の思想』(1914=1939)で「法則の進化」を論じている。
一般論として表現すると、法則とは「前提と帰結との間にある恒常的な連絡、世界の現在の状態と直ちにそれに継ぐ状態との間にある恒常的な連絡である」(同上:11。ただし、現代かなづかいと当用漢字に金子が修正した、以下同じ)と見なされた。そのうえで、量子研究や天文学それに力学などの経験から、法則とは「理知が創造し、或いは観察した、理知の外に存在するものとして考察され」(同上:33)ると見なされた。
もちろん法則は進化するし、変更されることもある。ノーベル賞を受けた研究成果ではありながら、後日に誤りが判明した業績が皆無ではないことからも想定できるが、科学とその発見された「真理の連鎖全体」としての「法則」もまた、時代の流れとともに変わることは仕方がない。
社会科学でも19世紀中盤のコント(1798-1857)あたりから、「法則」志向が顕著になる。社会学史でも有名な「予見するために見る」(voir pour prévoir)ためには「法則」の存在が不可欠だからであった。「自然法則は不変であるという一般教理に従って、『将来いかに成るか』(ce qui sera)を断定するために『現在いかに在るか』(ce qui est)を研究することをその特質とする」(コント、1844=1938:58)。これはいわば社会学の鉄則である。
「法則性」志向が濃厚な『資本論』
コントよりも20歳年下のマルクスの遺著である『資本論』では、「法則性」志向がさらに濃くなる。なぜならこれは、資本主義経済と社会の「法則」の探求のため書かれたからである。ドイツ語版第一版の「まえがき」に見るように、「資本主義的生産の自然法則から生じる社会的な敵対関係の発展度の高低は、それ自体としては問題ではない。問題は、この法則そのもの、鉄の必然性をもって作用し貫徹するこの傾向」(マルクス、1867=1962-64=1980:84)をイギリス史に基づいて把握しようとした注24)。
そして「近代社会の経済的運動法則を明らかにするのが、この著作の最終目的」(同上:85)と高らかに宣言される注25)。
『資本論』での法則は経済法則だけに止まらず、自然法則(:347)、社会法則(:207)、生産の法則(:1327)、発展法則(:1334)、投機の法則(:244)、交換の法則(:232)、資本主義的取得の法則(:340)、資本主義的の蓄積の法則(:368)、価値の法則(:260)、貨幣流通の一般的法則(:609)、剰余価値の分配を規制する法則(:1271)、差額地代の法則(:1239)、人口法則(:347)など多岐に亘る注26)。
揺籃期の碩学も「法則」志向
科学とりわけ社会科学の揺籃期の碩学たちは、複雑な人間が織りなす経済や社会の「法則」をそれぞれのやり方で掴もうとした。
マルクスより30歳若く、ウェーバーよりも少し長生きしたパレートもまた、「科学的法則とは実験的斉一性にほかならない」(パレート、1920=1941=1996:10)として、「法則」への言及が多い注27)。「経済法則および社会法則を含めた一切の法則は、真正の例外を有しない。斉一でない斉一性は無意味である。俗に例外と言われるものは、一つの法則の効果に他の法則の効果が重なったものである。……(中略) 多くの科学において、その研究が困難なのは、種々多数の斉一性が錯綜しているからにほかならない」(同上:11)。
研究の困難性を「斉一性の錯綜」で説明したのは卓見である注28)。しかも社会現象の「反復性」(同一の条件の下で繰返し確証された関係)と科学的法則性を同一化したこと、および「斉一性」が錯綜することの指摘は、今日でも参考になるところが大きい。
多数の要因が想定される特定の社会現象を説明する際には、量的諸要因ならばその「錯綜」を取り除くために計量的手法の重回帰分析などを使うことになる。
なお、マルクスに比べると非常に少ないとはいえ、ケインズでさえも、「心理法則」(ケインズ、前掲書:80;178)、「収穫逓減の法則」(同上:406)、「社会の生産的な要素の適用や報酬をもたらす法則」(同上:332)などが散見される。
同じくシュムペーターもまた、「法則」としたいところでは「諸傾向の叙述」(シュムペーター、1950=1995:97)に止めているが、他のたとえば『経済発展の理論』では、「生産収益逓減の法則」(シュムペーター、1926=1977上:78)や「費用法則」(同上:145)などを使っている。ただし、マルクスほどの法則指向性はなく、むしろ「図式」や「説明原理」(同上:144)としての使用が多いように思われる。
理論社会学の「法則」志向
最新の理論社会学でももちろん「法則」志向は継承されている。「社会学理論は一般的、永続的、普遍的な法則を開発できなかった」(ターナー、2010=2020:16)という批判に対して、社会学理論を「法則定立化」、「類型図式化」、「歴史的説明」に3分類したうえで、ターナー自身は「法則」指向の「社会の自然科学」を標榜する。この後に、マクロ社会システムを「人口」、「生産」、「分配」、「規制」、「再生産」の基本的動力で一般化しようとする試みが続く(同上:18)。
このうち「人口」そして「人口の再生産=生殖」は、社会システムの土台であるから高田の人口史観が応用できる(金子編、2003)。また、「生産」は「経済」、「分配」は「政治」、「規制」は「社会統合」、「再生産」は「価値・文化」に対応すると考えれば、パーソンズのAGIL図式を彷彿とさせる(金子編、2019)。
総体的にいえば、ここで簡単に紹介した「法則」志向は学術的には不可欠である。人類社会の未来を展望する際にも、経済学や社会学で蓄積されてきた様々な「法則」をわれわれは謙虚に学んでおきたい。
設計科学には勢力論の活用を
したがって、「法則科学」と「管理・設計科学」とを対置させるような問題の立て方では、社会科学は前進できなくなる。むしろ、「法則」を活用したその先に、新しい経済学を「稀少な資源の管理科学」と位置づけることで、それが可能になるのではないか。
なぜなら、ラワースの「設計による分配」や「設計による環境再生」などに象徴される「設計」は、いつの時代も勢力関係に左右されてきたからである。ラワースもまた「勢力」の重要性には触れている(ラワース、前掲書:131-132)。
そのような「設計」の歴史を踏まえれば、日本においてはそれに加えて、高田の「勢力論」(1940=1958=2003)で示された「勢力加速度の法則」などは参考になるところが多い注29)。
(次回:「脱炭素と気候変動」の理論と限界⑥に続く)
■
注23)英語でもフランス語でも綴りが同じsimulationは、ないものをあるように見せかけることを意味し、dissimulationはあるものを隠すという意味がある。
注24)フランス語版からの翻訳は、「資本主義的生産の自然法則から生じる社会的敵対の完全な発展の高低ではなく、これらの法則そのもの、鉄の必然性をもって現われ自己を実現する傾向」(太字原文 マルクス、1872-1875=1979:ix)と訳されている。
注25)フランス語版からは、「本書の窮極目的は、近代社会の運動の経済法則を解明すること」(1872-75=1979:xi)という翻訳になっている。
注26)引用ページは鈴木鴻一郎訳(中央公論社版)による。
注27)ラワースは本文でパレートの「8020の法則」を引用し解説している(:239)。しかし「参考文献」にはパレートの著書はなく、パースキー(1992)の解説論文が「8020の法則」の「原注」として示されている(:449)。
注28)ただし、今日的な日本語感からすれば、原語のuniformitéを「斉一性」と訳すよりも「画一性」ないしは「一様性」のほうが分かりやすいであろう。
注29)「勢力というのは人間間の関係に附着している価値」(高田、前掲書:5)や「社会における個人勢力の集積は勢力要求即ち力の欲望の標的となり、それを目ざしてすべての競争と対立と努力と緊張がある」(同上:339)などは、「管理」や「設計」が人間の営みである限り、さまざまなヒントを与える。なおここで紹介した「勢力加速度の法則」とは、ある主体が「連帯の関係によって他の勢力をよび集め、それが基本となって更に他の勢力を集むることにより急速にその大きさを加えてある段階に達する、という関係をさす」(高田、1940=1958=2003:119 ただし、現代かなづかいと当用漢字に金子が修正した)。
【参照文献】
- Asimov,I.,1989, Asimov’s Chronology of Science and Discovery, HarperCollins Publishers,Inc.(=1996 小山慶太・輪湖博訳『アイザック・アシモフの科学と発見の年表』丸善)
- Bernard,C.,1865,Introduction à l’étude de la médecine expérimentale .(=1970,三浦岱栄訳 『実験医学序説』岩波書店)
- Comte.A.,1844,Discours sur l’esprit positif.(=1938 田辺寿利訳 『実証的精神論』岩波書店).
- Descartes,R.,1637,Discours de la méthode.(=1997 谷川多佳子訳『方法序説』岩波書店).
- 金子勇編,2003,『高田保馬リカバリー』ミネルヴァ書房.
- 金子勇編,2019,『変動のマクロ社会学』ミネルヴァ書房.
- Marx,K,1867=1962-64,Das Kapital,(=1980 鈴木鴻一郎責任編集『マルクス エンゲルスⅠ Ⅱ 世界の名著54 55』中央公論社).
- Marx,K,(traduction de Roy)(1872-1875)Le Capital,Maurice Lachatre et Cie ,Paris.(=1979 江夏美千穂・上杉聰彦訳『フランス語版資本論』(上下)法政大学出版局).
- Pareto,V.,1920,Compendio di sociologia generale ;per cura di Giulio Farina.(=1941=1996 姫岡勤訳・板倉達文校訂『一般社会学提要』名古屋大学出版会).
- Poincaré,H.,1905,La Valeur de la science.(=1977 吉田洋一訳『科学の価値』岩波書店).
- Poincaré,H.,1914,Dernières pensées.(=1939 河野伊三郎訳 『晩年の思想』岩波書店).
- Schumpeter,L.A.,1926,Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung,2.Aufl.(=1977 塩野谷祐一・中山伊知郎・東畑精一訳『経済発展の理論』(上下)岩波書店).
- Schumpeter,J.A.,1950,Capitalism,Socialism and Democracy,3rd. Harper & Brothers.(=1995 中山伊知郎・東畑精一訳『資本主義・社会主義・民主主義』(新装版)東洋経済新報社).
- 杉山大志,2022,「15歳からの地球温暖化」国際環境経済研究所WEB連載(1.31)
- Turner,J.H.,2010,Theoretical Principles of Sociology,Volume1 Macrodynamics, Springer Science +Business Media,LLC.(=2020 正岡寛司ほか訳『社会学の理論原理-マクロ・ダイナミクス Vol.1』 学文社).
- 高田保馬, 1940=1958=2003,『勢力論』ミネルヴァ書房.
【関連記事】
・「脱炭素と気候変動」の理論と限界①:総説
・「脱炭素と気候変動」の理論と限界②:斎藤本のロジックとマジック
・「脱炭素と気候変動」の理論と限界③:仮定法は社会科学に有効か
・「脱炭素と気候変動」の理論と限界④:ラワース著「ドーナツ経済」の構想と限界
・「脱炭素と気候変動」の理論と限界⑤:法則科学か設計科学か
・「脱炭素と気候変動」の理論と限界⑥:「ドーナツ21世紀コンパス」の内実
・「脱炭素と気候変動」の理論と限界⑦:WEIRDを超えた5つの人間像
・「脱炭素と気候変動」の理論と限界(最終回):成長と無縁の繁栄はありえない

関連記事
-
東京電力福島第一原発の直後に下された避難指示によって、未だに故郷に帰れない避難者が現時点で約13万人いる。
-
東日本大震災以降、エネルギー関連の記事が毎日掲載されている。多くの議論かが行われており、スマートメーターも例外ではない。
-
大型原子力発電所100基新設 政府は第7次エネルギー基本計画の策定を始めた。 前回の第6次エネルギー基本計画策定後には、さる業界紙に求められて、「原子力政策の180度の転換が必要—原子力発電所の新設に舵を切るべし」と指摘
-
IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回の論点⑳に続いて「政策決定者向け要約」の続き。前回と
-
全原発を止めて電力料金の高騰を招いた田中私案 電力料金は高騰し続けている。その一方でかつて9電力と言われた大手電力会社は軒並み大赤字である。 わが国のエネルギー安定供給の要は原子力発電所であることは、大規模停電と常に隣り
-
SDGs(Sustainable Development Goals、持続可能な開発目標)については、多くの日本企業から「うちのビジネスとどう関連するのか」「何から手を付ければよいのか」などといった感想が出ています。こう
-
かつて省エネ政策を取材したとき、経産省の担当官僚からこんなぼやきを聞いたことがある。「メディアの人は日本の政策の悪い話を伝えても、素晴らしい話を取材しない。この仕事についてから日本にある各国の大使館の経済担当者や、いろんな政府や国際機関から、毎月問い合わせの電話やメールが来るのに」。
-
前回お知らせした「非政府エネルギー基本計画」の11項目の提言について、3回にわたって掲載する。まずは第1回目。 (前回:強く豊かな日本のためのエネルギー基本計画案を提言する) なお報告書の正式名称は「エネルギードミナンス
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間