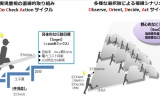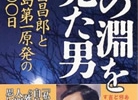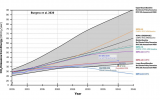豪首相「COP26で石炭は終焉」との主張に猛然と反論
COP26におけるグラスゴー気候合意は石炭発電にとって「死の鐘」となったと英国ボリス・ジョンソン首相は述べたが、これに反論して、オーストラリアのスコット・モリソン首相は、石炭産業は今後も何十年も事業を続ける、と述べた。

スコット・モリソン オーストラリア首相 Wikipediaより
海外各紙が報じている(SBS (ビデオインタビュー付き), Dailymail、Washingtonpost)
モリソンの発言概要は以下のとおり:
- 2050年までに排出量を完全にゼロにするという目標のためにオーストラリアの農村部や地域の人々に「代償を払わせる」ことはしない。(注:オーストラリアは主に民間の自主的取り組みによって目標を達成するとしている)
- 2030年の排出目標の深堀はしない(注:COP26で採択されたグラスゴー気候協定では、来年エジプトで開催されるCOP27サミットまでに各国が「パリ協定の気温目標と整合的な」2030年の排出削減目標の深堀を検討することになっている。現在のオーストラリアの目標は2005年比で2030年までに30%削減となっている。)
- 低排出ガスの新技術への移行は長い時間をかけて行われるため、石炭部門で雇用されているオーストラリア人は、今後何十年もその業界で働き続けることになる。
- オーストラリアの国益を守るために立ち上がることを謝罪するつもりはない(no apologies)。(注:オーストラリアは、世界第2位の石炭輸出国であり、世界第5位の石炭生産国である。オーストラリアから石炭を購入している主な国は、日本、インド、中国、台湾)。
- 温暖化問題を実際に解決することができるとわかっている技術進歩に焦点を当て、安全保障と経済とのバランスのとれた方法で温暖化対策を行うつもりだ。温暖化対策のためにオーストラリア人に税金を課したり、法律で規制したり、強制したりするつもりはない。
外国の圧力に阿らず毅然として国益を守る。これが本当の政治家だ。日本にはこのような人物はいないのか?
■

関連記事
-
例年開催されるCOPのような印象を感じさせたG7が終わった。新聞には個別声明要旨が載っていた。気候変動対策については、対策の趣旨を述べた前文に以下のようなことが書かれていた。 【前文】 遅くとも2050年までにCO2の排
-
評価の分かれるエネルギー基本計画素案 5月16日の総合資源エネルギー調査会でエネルギー基本計画の素案が了承された。2030年の電源構成は原発20-22%、再生可能エネルギー22-24%と従来の目標が維持された。安全性の確
-
温暖化問題は米国では党派問題で、国の半分を占める共和党は温暖化対策を支持しない。これは以前からそうだったが、バイデン新政権が誕生したいま、ますます民主党との隔絶が際立っている。 Ekaterina_Simonova/iS
-
COP28が11月30日からアラブ首長国連邦(UAE)のドバイで開催される。そこで注目される政治的な国際合意の一つとして、化石燃料の使用(ならびに開発)をいつまでに禁止、ないしはどこまで制限するか(あるいはできないか)と
-
IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回の論点⑳に続いて「政策決定者向け要約」の続き。前回と
-
東京電力福島第一原子力発電所の事故から早2年が過ぎようとしている。私は、原子力関連の会社に籍を置いた人間でもあり、事故当時は本当に心を痛めTVにかじりついていたことを思い出す。
-
6月30日記事。環境研究者のマイケル・シェレンベルガー氏の寄稿。ディアプロ・キャニオン原発の閉鎖で、化石燃料の消費が拡大するという指摘だ。原題「How Not to Deal With Climate Change」。
-
地球温暖化というと、猛暑になる!など、おどろおどろしい予測が出回っている。 だがその多くは、非現実的に高いCO2排出を前提としている。 この点は以前からも指摘されていたけれども、今般、米国のピールキーらが詳しく報告したの
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間