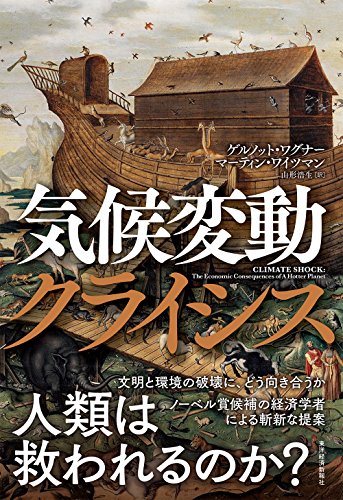気候変動は惑星規模のギャンブル-『気候変動クライシス』【書評】
ゲルノット・ワグナー(ハーバード大学工学・応用科学リサーチ・アソシエイト、同大学環境科学・公共政策レクチャラー)
マーティン・ワイツマン(ハーバード大学経済学教授)
東洋経済新報社
経済学者は、気候変動の問題に冷淡だ。環境経済学の専門家ノードハウス(書評『気候変動カジノ』)も、温室効果ガス抑制の費用と便益をよく考えようというだけで、あまり具体的な政策には踏み込まない。現実的な話をすると、「大企業に奉仕する御用学者」とか「石油メジャーから金をもらっている」とか攻撃されるからだ。
そんな中で、本書はかなり環境保護派寄りの立場を取っている。といっても「かけがえのない地球を守れ」みたいな素朴な話をしているのではない。気候変動はフランク・ナイトの分類でいえば、予測できるリスクではなく、確率もわからない不確実性であり、しかもその危険が大きく、不可逆だということがわかってきたからだ。
いいかえれば気候変動対策は「惑星規模のギャンブル」だが、その賭け金も配当もよくわからない。さらに厄介なのは、100年単位の超長期の問題なので、割引率によって答が大きく変わることだ。その意味では、気候変動はファイナンスの問題に近い。
気候変動対策の費用と効果
これは投資理論(CAPM)でおなじみのベータの問題である。これは株式市場が1%変化したとき、特定の株式のリターンが何%変化するかを表す係数で、ベータが高い株式はハイリスク・ハイリターンで、ベータが低いと落ち着いた動きをする。したがってベータの高い資産には高い割引率(リスク・プレミアム)をつけ、ベータの低い資産(国債など)には低い割引率が適用される。
気候変動が通常の循環的なものならベータは高く、将来の割引現在価値は低く評価される。したがって気候変動を防止する対策のコストと比較すると将来価値は小さいので、あまりコストをかけるべきではない。逆に割引率が低いと、コスト(割引現在価値)は高くなる。
2006年にイギリス政府に提出されたスターン報告https://www.env.go.jp/earth/report/h19-01/08_ref06.pdfでは、「最悪の場合は100年後にGDPの20%が気候変動で失われる」と予想し、割引率を0.1%ときわめて低く設定したため、必要な対策のコストも莫大なものになった。
しかし多くの経済学者は普通の金融市場でみられる3~5%の割引率を想定し、必要なコストをもっと低く見積もる。炭素税に換算すると、ノードハウスの計算では炭素1トンあたり20ドルぐらいだ。100年先を考えると、割引率で結果は大きく変わる。
著者はここで、今まで経済学者が考えなかったファットテールに注目する。これは、確率は小さいが大きなリスク(不確実性)で、たとえば隕石が落ちてきて、その破片でおおわれて地球が氷河期になる確率はきわめて低いが、起こると莫大な被害が出る。
このようにわからないファットテールについては、一定の保険をかけたほうがいいというのが著者の意見だ。ファイナンスでいうと、2008年の金融危機のような世界経済を破壊する破局が、それほど低くない頻度で起こっている。
ただ不確実性もファットテールも確率がわからないので、定義によって計算できない。こういう場合にどうすればいいかもよくわかっていないが、政府の問題としては安全保障に似ている。戦争はめったに起こらないが、起こったときの被害を最小化するために莫大なコストをかける。
本書は炭素税でいうと36ドル/トンぐらいを推奨している。それが最適だという保証はないが、やや高めにコストを見積もり、様子をみながら調節するのが現実的だろう。パリ協定のような割当は、賢明な政策とはいえない。経済学者が好むのは塵を散布する大気中にジオエンジニアリングだが本書は、これは好ましくないとしている。

関連記事
-
北海道大学名誉教授 金子 勇 マクロ社会学から見る「脱炭素社会」 20世紀末に50歳を越えた団塊世代の一人の社会学者として、21世紀の課題はマクロ社会学からの「新しい時代の経済社会システム」づくりだと考えた。 手掛かりは
-
エネルギー政策をどのようにするのか、政府機関から政策提言が行われています。私たちが問題を適切に考えるために、必要な情報をGEPRは提供します。
-
小泉環境大臣がベトナムで建設予定の石炭火力発電所ブンアン2について日本が融資を検討していることにつき、「日本がお金を出しているのに、プラントを作るのは中国や米国の企業であるのはおかしい」と異論を提起している。 小泉環境相
-
釧路湿原のメガソーラー建設が、環境破壊だとして話題になっている。 室中善博氏が記事で指摘されていたが、湿原にも土壌中に炭素分が豊富に蓄積されているので、それを破壊するとCO2となって大気中に放出されることになる。 以前、
-
GEPRを運営するアゴラ研究所は毎週金曜日9時から、アゴラチャンネル でニコニコ生放送を通じたネットテレビ放送を行っています。2月22日には、元経産省の石川和男氏を招き、現在のエネルギー政策について、池田信夫アゴラ研究所所長との間での対談をお届けしました。
-
「2030年までにCO2を概ね半減し、2050年にはCO2をゼロつまり脱炭素にする」という目標の下、日米欧の政府は規制や税を導入し、欧米の大手企業は新たな金融商品を売っている。その様子を観察すると、この「脱炭素ブーム」は
-
【概要】特重施設という耳慣れない施設がある。原発がテロリストに襲われた時に、中央操作室の機能を秘匿された室から操作して原子炉を冷却したりして事故を防止しようとするものである。この特重施設の建設が遅れているからと、原子力規
-
10月16日、ポツダムで開かれた記者会見で、「難民問題についてAfDはずっと先を行っているが、いったいCDUにはどのような戦略があるのか」という質問を受けたメルツ首相が、「もちろん、街の風景に問題があるため、内務省はさら
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間