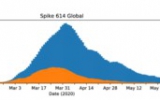【シンポ関連】遺伝子組み換えは農薬ではない

日本でも、遺伝子組み換え(GMO)作物が話題になってきた。それ自体は悪いことではないのだが、このブログ記事に典型的にみられるように、ほとんどがGMOと農薬を混同している。これは逆である。GMOは農薬を減らす技術なのだ。
「遺伝子組み換え」というと、いかにも危険な遺伝子操作をするようだが、単なる品種改良の技術である。今までは交配によって遺伝子の組み替えを植物にさせていたのを、人間が実験室でやるだけだ。その主な目的は、除草剤や害虫に強い品種をつくることだ。
除草剤は毒物である。人間が大量に飲むと死ぬ劇薬だが、雑草を取り除くために使われている。しかし除草剤はすべての植物を殺すので、何回にもわけて雑草だけが死ぬように散布する必要がある。これに対して、GMOで除草剤に耐性のある品種をつくると、1回で雑草だけを殺すことができる。
害虫を殺す殺虫剤も毒物である。GMOで害虫に強い品種をつくると、殺虫剤の散布もなくすことができる。これによって農作業が楽になり、収量が増えるだけでなく、農薬(除草剤・殺虫剤)の使用量も大きく減るのだ。農薬で死んだ人はたくさんいるが、GMOで死んだ人はいない。
反GMO運動は、反原発運動に似ている。彼らは「自然は正しい」と信じているが、GMOをやめると毒性の強い農薬が増えることは知らない。有機農業で高い農作物を売っている業者は、彼らの無知を利用してGMOを阻止しているが、GMOをまったく使っていない日本の1人あたり農薬使用量は世界一だ。
しかしGMOには毒性がないので、海外では普通に使われている。日本に輸入されるトウモロコシの7割以上は、GMO作物だ。農水省も許可しているが、農協が「安全確保」を理由にして阻止しているので、栽培には使えない。GMOを支配しているのはモンサントなどの外資系企業で、農協の独占を脅かすからだ。
アゴラ研究所では、2月29日に「遺伝子組み換え作物は危険なのか?」と題して、GMOは危険なのか、それがなぜ誤解されているのか、を科学者やジャーナリストとともに考える。
(2016年2月15日掲載)

関連記事
-
東京で7月9日に、新規感染者が224人確認された。まだPCR検査は増えているので、しばらくこれぐらいのペースが続くだろうが、この程度の感染者数の増減は大した問題ではない。100人が200人になっても、次の図のようにアメリ
-
原子力基本法が6月20日、国会で改正された。そこに「我が国の安全保障に資する」と目的が追加された。21日の記者会見で、藤村修官房長官は「原子力の軍事目的の利用意図はない」と明言した。これについて2つの新聞の異なる立場の論説がある。 産経新聞は「原子力基本法 「安全保障」明記は当然だ」、毎日新聞は「原子力基本法 「安全保障目的」は不要」。両論を参照して判断いただきたい。
-
はじめに:なぜ気候モデルを問い直すのか? 地球温暖化対策の多くは、「将来の地球がどれほど気温上昇するか」というシミュレーションに依存している。その根拠となるのが、IPCCなどが採用する「気候モデル(GCM=General
-
G7首脳が原爆資料館を視察 G7広島サミットが開幕し、各国首脳が被爆の実相を伝える広島平和記念資料館(原爆資料館)を訪れ、人類は核兵器の惨禍を二度と繰り返してはならないとの認識共有を深めた。 しかし現実にはウクライナを侵
-
去る4月16日に日本経済団体連合会、いわゆる経団連から「日本を支える電力システムを再構築する」と題する提言が発表された。 本稿では同提言の内容を簡単に紹介しつつ、「再エネ業界としてこの提言をどう受け止めるべきか」というこ
-
福島の原発事故では、原発から漏れた放射性物質が私たちの健康にどのような影響を与えるかが問題になっている。内閣府によれば、福島県での住民の年間累積線量の事故による増加分は大半が外部被曝で第1年目5mSv(ミリシーベルト)以下、内部被曝で同1mSv以下とされる。この放射線量では健康被害の可能性はない。
-
GEPRを運営するアゴラ研究所は映像コンテンツ「アゴラチャンネル」を放送しています。5月17日には国際エネルギー機関(IEA)の前事務局長であった田中伸男氏を招き、池田信夫所長と「エネルギー政策、転換を今こそ--シェール革命が日本を救う?」をテーマにした対談を放送しました。
-
>>>(上)はこちら 3. 原発推進の理由 前回述べたように、アジアを中心に原発は再び主流になりつつある。その理由の第一は、2011年3月の原発事故の影響を受けて全国の原発が停止したため、膨大な費用が余
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間