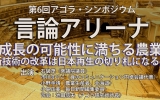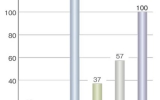シンポジウム 遺伝子組み換え作物は危険なのか?

日本の農業の姿が自立、競争へ変わろうとしています。そして世界の農業では遺伝子組み換え作物が、生産の拡大やコストの削減に重要な役割を果たしています。
ところが日本では、なぜかその作物を自由につくり、活用することができません。健康に影響するのではないか、栽培すると生態系を変えてしまうのではないかなど、懸念が消費者の間にあります。
「遺伝子組み換え作物はなぜ誤解されるのか」「なぜ日本で生産ができないのか」をテーマに、その本当の姿を、多面的な視点から考えるシンポジウムを開催します。ジャーナリスト、生産者、研究者、消費者団体幹部らが出席します。
遺伝子組み換え作物の問題を考え始めるきっかけとして、また詳しい方は新しい知識を獲得する場として、ぜひご参加ください。共に問題を考えましょう。
出席者:
小島正美(毎日新聞編集委員)
田部井豊(農業生物資源研究所研究員)
有田芳子(主婦連合会会長)
小野寺靖(農業、北海道在住)
司会: 池田信夫(アゴラ研究所所長)
日時:2016年2月29日(月曜日)18:30〜20:30
イイノホール Room B
東京都千代田区内幸町2−1−1

小島正美氏と編著書

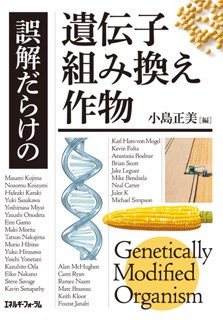
池田信夫氏

※このシンポジウムは、ニコニコ生放送、またYoutubeで公開されます。
(2016年2月8日掲載)

関連記事
-
12月22日公開。日本の農業の姿が変わろうとしています。 規制と補助金主導から、自立と競争への転換です。改革が遅れた分野ですが、それゆえに発展に大きな「伸びしろ」があります。
-
ワッツバー原発(テネシー州、TVAホームページより) テネシー州で建設が進められてきたテネシー川流域開発公社(TVA)ワッツバー原子力発電所2号機 (Watts Bar Unit 2、テネシー州)が10月3日、商業運転を
-
東京電力の元社員の竹内さんが、一般の人に知らないなじみの少ない停電発生のメカニズムを解説しています。
-
9月13日記事。日本原研の運営する高速増殖炉のもんじゅについて、政府が廃炉を含めた検討に入ったとの報道。菅官房長官はこの報道を否定している。ただ費用について、誰も出せると考えていない。
-
東京大学地震研究所の教授らによる活断層調査での誤りについて3月30日付産経新聞社説は、厳しい書き出しで批判した。工場跡地の中に打ち込ませていた杭を、首都直下地震につながる立川断層の破砕層と見誤ったのだ。
-
再稼動の遅れは、新潟県の泉田知事と東電の対立だけが理由ではない。「新基準により審査をやり直す原子力規制委員会の方針も問題だ」と、池田信夫氏は指摘した。報道されているところでは、原子力規制庁の審査チームは3つ。これが1基当たり半年かけて、審査をする。全部が終了するのは、単純な計算で8年先になる。
-
アゴラ研究所は、9月27日に静岡で、地元有志の協力を得て、シンポジウムを開催します。東日本大震災からの教訓、そしてエネルギー問題を語り合います。東京大学名誉教授で、「失敗学」で知られる畑村洋太郎氏、安全保障アナリストの小川和久氏などの専門家が出席。多様な観点から問題を考えます。聴講は無料、ぜひご参加ください。詳細は上記記事で。
-
田原・政権はメディアに圧力を露骨にかけるということはほとんどない。もし報道をゆがめるとしたら、大半の問題は自己規制であると思う。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間