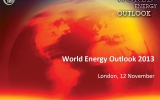遺伝子組み換え作物、活用は可能か【アゴラ農業シンポジウム4】
出席者
市川まりこ(食のコミュニケーション円卓会議代表)
小野寺靖(農業生産者、北海道)
小島正美(毎日新聞編集委員)
司会:池田信夫(アゴラ研究所所長)
映像
まとめ・成長の可能性に満ちる農業【記事1】
要旨1・石破議員講演「農業による日本活性化」【記事2】
要旨2・パネルディスカッション上 農業改革の可能性【記事3】
この記事は要旨3・パネルディスカッション下、【記事4】
参考・池田信夫氏解説「石破茂氏の「日本経済の伸びしろ」」
(16年12月20日に行われたアゴラ農業シンポジウムの後半要旨)
安全性に傾きがちな日本の消費者運動
池田・石破さんの意見には、印象に残る点がいくつかありました。メディアがこの問題、安全に傾きがちな面はあるという指摘ですが、小島さん、この点をどう考えますか。
小島・確かにそのような点はあると思います。メディアも、政治家と同じように、読者、そして抗議に弱いのです。批判を受けると萎縮してしまい、前例を踏襲するようになる。しかし遺伝子組み換えでは、商品化から20年の時間が経過して、健康のリスクのないことが示されたため、最近は議論も落ち着いているように思えます。
池田・また石破さんは、「日本と欧米の消費者団体は違うところがあるのかもしれない」という感想を話しました。私もそんな印象を受けています。普通の国なら消費者団体は農作物価格の引き下げに動きます。日本の消費者団体は、なぜか安全性ばかりを強調するし、一部の過激な人は遺伝子組み換え作物などの技術革新を妨害します。
市川・そうした面はあります。一部の人の提起する議論がいつも同じで、安全性ばかりが強調される面があります。私はそうした食をめぐる常識とされてきたことでも、冷静に検証し、思い込みや常識に囚われない主張をする消費者運動をして来ています。パターン化した人々の考えを変えるには、新しい技術を使い、利便性を感じてもらうことで可能になると思います。私は、遺伝子組み換え技術を使って花粉症を治すなどの取り組みに関心を寄せています。
池田・小野寺さんにうかがいたいのは、自民党の農業改革を北海道の農家の皆さんは、どう受け止めているのかということです。また改革の対象になっている農協はそんなに力が強いのかということを教えていただきたいです。
小野寺・農業改革は報道で知るのみですね。日常の農業に忙しい。そして地域農協は購買、販売、金融の3つを持っているわけです。そうしたところからプレッシャーがかかると、それをはねのけるのは難しいです。
日本は海外から大量に、飼料として遺伝子組み換えの穀物を購入しています。そして表示も5%以下なら、また意図しない混入なら、しなくてもいい。実際のところ、私たちはそれを食べている可能性もあるのです。それなのに、それを国内では法律で禁じられていないのにつくることはできなくなっています。
農業は草との戦いの面があります。家庭菜園の本を読んだことがありますが、そこに除草の大変さは書かれていませんでした。私たちは「業」として農業をしているわけです。その合理化のために、新技術を使いたいのです。
池田・農協や他の農家が妨害しているのは、競争力もあり、意欲的な小野寺さんのような農家が、成果を出すのを止めたい意図があるのではないでしょうか。
小野寺・それは分かりません。私は平均的な農家です。みんな草取りを嫌がっているのに、やろうという動きを示すと、やめようという圧力に直面してしまいます。
小島・遺伝子組み換え作物を実現しようとする動きは、なぜか途中でつぶれます。農水省で意欲的な担当者が準備をすると、政権交代などの政治の影響で、できなくなってしまったことがあります。民間企業がやると消費者団体の反対で断念しました。国の研究機関がやろうとすると、訴訟を起こされたり抗議をされたりしました。研究者は疲弊してしまうのです。
農協関係者は、風評被害ということを気にします。遺伝子組み換え作物の反対派は「つくったら村の農産物を買わないぞ」と言ってきます。その場合に、議論をしなければならないのですが、めんどくさいので農家に栽培をやめさせてしまう方向に動くのです。
池田・農協はグループ企業が、海外からの飼料用穀物の輸入の窓口にもなっているはずです。それでいて地域農協が遺伝子組み変え作物の栽培を妨害するのは行動が矛盾しているのではないでしょうか。
小島・騒ぎになりかねないので、組織は明確な反対はしないのですが、なんとなく反対をする。けれども状況は変わってきていると思います。遺伝子組み換え作物は他国で導入され、日本でも大量に輸入されている。そしてそれによる健康被害は出ていないわけです。その論拠も少なくなっています。
反対の理由はあいまいなものが多いので、それを変えようという動きがあれば変わると思います。小野寺さんみたいな意欲的な農家を周囲が守り、応援していく方法があるのかなと思います。
市川・「多くの消費者が不安に思っている」というのは、遺伝子組み換え作物反対する人々とか、その他の問題でも、良く使われる言葉です。けれども、その本当の姿は分かりづらいものがあります。強硬に反対する意見を表明して、行動する人はごく一握り。その回りにはなんとなく不安という人が多いと思います。
ただしこのような中でも解決策はあると思います。遺伝子組み換え作物の栽培ができないよう一律の禁止ではなく、選択の自由を農家にも消費者にも与えるとか、それを使うことによる可能性を広げるという政策をしていただきたいです。
農業改革の前提
池田・石破さんの講演では「インフレにしても日本経済はよくならない」という指摘がありました。これはその通りで、アベノミクスは需要側を刺激する政策です。安倍首相はがかつて「輪転機ぐるぐる回してお札を刷れば景気がよくなる」と述べましたが、お金を増やすと効果があるいう考えです。アベノミクスによって最初の1年は多少効きましたが、今になっては成長率も物価上昇もほとんどなくなってしまいました。
生産性があがらないと、持続的な経済成長は無理です。需要側だけではなく、供給側も強くしなければならない。つまり産業の強化です。農業を産業として育て、まず成長の可能性がある輸出で増やそうという石破さんの提案はその通りと思います。
自民党は農協改革・農政改革に手をつけました。それは歴史上はじめてです。しかしTPPが批准されず、今年の参議院選挙で、自民党が予想外に苦戦しました。東北では農協が足を引っ張った。前向きのことはできないけど後ろ向きのことはできるわけです。日本には、こうした後ろ向きのことをできる人たちがいます。
当面、輸出を増やすというのは、妥当な政策と思います。輸出を10倍にすることは可能でしょうか。
小野寺・10年後は狙えるかもしれませんが、それを可能にするのは技術革新だと思います。農家が草取りで疲弊したら、販売を促進するとか、現実を変えるエネルギーは生まれません。
池田・株式会社が自由に農業をできないというのも、変な話です。それは、消費者の方も意欲的な農家を支える動きがあっていいように思うのです。
市川・一昔前、「大手」の消費者団体は農業関係者とタイアップして、同じ主張をしてきましたが、激しく抗議をするような昔ながらの消費者団体は少なくなっているように思えます。ようやく、この10年、さまざまな問題で多様な意見を主張する消費者団体が出てきました。ただし世の中に流れる情報、報道に乗る情報はパターン化していますし、昔ながらの主張が繰り返される面があります。行政も、「NPOや消費者団体はこういうものだ」という固定観念があるようで、昔からの消費者団体が、相変わらず国の審議会の席を占めているように思います。
空気の読めない人が利益を得る
小島・「大手」の消費者団体は、もう力はなくなっていると思います。なり手が少なくて、前の女性代表の娘さんが継いでいる例もあります。力があれば、日本の政治で、社民党とか、民進党の勢力がもっと強いはずです。
社会には惰性で物事が進む例があります。小学校の体育で「逆上がり」というのがあります。これができなくて苦しんだ人もいるでしょう。けれども調べると、逆上がりは、繰り返ししたとしても、筋力が向上するとか、何かメリットがあるわけではないそうです。それができることが、体力の目安になるわけでもない。できないのに優れたスポーツ選手はいるそうです。昔からの「惰性」で行われているにすぎないそうです。
だから遺伝子組み換え作物問題をはじめ農業改革を阻むものは、「惰性」で続いていることがないか、検証が必要であると思います。
この作物では、身近に使うことが必要かもしれません。例えばハワイのパパイヤの8割は、レインボーパパイヤになっています。これは遺伝子組み換え技術を使い、ウィルスへの耐性があり、味もよい。そして企業ではなく、地元の大学教授がつくったものです。消費者がその例に触れ、食べることで、状況は変わるかもしれません。
そして生産者も消費者も、選択の自由を得られるようにすべきです。懸念を示す人がいてもいいでしょう。しかし作らせないというのはやりすぎで、小野寺さんのような意欲的な農家が、自由に活動できるようにするべきでしょう。
池田・この問題、なかなか変わらない。農業は、崖っぷちで30年、ほったらかされましたが、それでまだ大丈夫と惰性で続いているようです。伸びしろは大きいのに、談合とか自制で低いところにとどまっている。
ただこれは見方を変えれば、先行して意味あることをした人は利益を得られるということです。私はソフトバンクの孫正義さんと通信の世界でつきあってきましたが、彼はそうした「空気の読めない人」です。ADSLを認めてもらおうとしたとき、「主張が通らなければ、総務省に行ってガソリンかぶって火を付ける」なんて言っていました。そうしためちゃくちゃさゆえに、物事が変わった面があったわけです。
遺伝子組み換え作物が象徴ですが、日本社会には何も前向きのことはできなくても、人の妨害だけはすることができる人たちがいます。農業改革は足踏みしていますが、そうした人を、「空気の読めない人」が壊してほしいです。農業は伸びしろの大きな産業で、大きく変わる可能性があります。
(編集・石井孝明 ジャーナリスト GEPR編集者)

関連記事
-
活断層という、なじみのない言葉がメディアに踊る。原子力規制委員会は2012年12月、「日本原電敦賀原発2号機直下に活断層」、その後「東北電力東通原発敷地内の破砕帯が活断層の可能性あり」と立て続けに発表した。田中俊一委員長は「グレーなら止めていただく」としており、活断層認定は原発の廃炉につながる。しかし、一連の判断は妥当なのだろうか。
-
日本のすべての原発は現在、法的根拠なしに止まっている。それを確認するために、原子力規制委員会・規制庁への書面取材を行ったが、不思議でいいかげんな解答をしてきた。それを紹介する。
-
言論アリーナ「どうなる福島原発、汚染水問題・東電常務に田原総一朗が迫る」で姉川尚史東電常務が公表した図表21枚を公開する。
-
要旨「数値目標を1%上積みするごとに、年間1兆円の費用がかかる。これは1トンCO2あたり10万円かかることを意味する。数値目標の本当のコストは途方もなく大きいので、安易な深掘りは禁物である。」
-
すべての国が参加する枠組みであるパリ協定の合意という成果を挙げたCOP21(国連・気候変動枠組み条約第21回締約国会議)。そして今後の国内対策を示す地球温暖化対策計画(温対計画)の策定作業も始まった。この影響はどのように日本の産業界、そしてエネルギー業界に及ぶのか。3人の専門家を招き分析した。
-
報道ステーションの3月11日の報道を振り返ると、伝えるべき重要な情報をまったく強調していない。おかしな異説を唱える人の少数説ばかり取り上げている。「福島県の甲状腺がんが原発事故によるもの」とのシナリオを前提に、その筋書きに沿う発言をしてくれる人物を登場させている。
-
国際エネルギー機関(IEA)は11月12日、2013年の「世界のエネルギー展望」(World Energy Outlook 2013)見通しを発表した。その内容を紹介する。
-
私は自民党議員連盟「FCVを中心とした水素社会実現を促進する研究会」(通称:水素議連)の事務局長として、会長である小池百合子衆議院議員(編注・インタビュー時点)や仲間と共に、水素社会の実現を政治の立場から支えようとしている。水素の活用による国民の幸福を確信している。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間