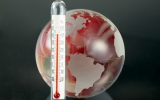原発事故後の違法な政策を見直すべきだ
今年9月に国会で可決された「安全保障関連法制」を憲法違反と喧伝する人々がいた。それよりも福島原発事故後は憲法違反や法律違反の疑いのある政策が、日本でまかり通っている。この状況を放置すれば、日本の法治主義、立憲主義が壊れることになる。
また違法な状況によって混乱の続く原子力・エネルギー政策を放置すれば、原発に対する国民の信頼が失墜し、将来を決める国のエネルギー選択を誤る。
今回は、憲法の財産権の侵害、原賠法(原子力損害賠償法)の問題、東電の補償の問題にテーマを絞り、問題を考察したい。いずれも法律に違反している。国は施策を修正し、電力会社は正論を主張し、国民の信頼を回復してほしい。
1.事故を起こしていない原発を停止させた政策は憲法違反ではないか?
福島原発事故直後、当時の菅直人首相は中部電力浜岡原発の停止を要請し、会社側はこれを実質的な命令と受け止めて原発を停止させた。これへの批判は既に行われているが(1)、今後も影響する大きな問題であるので、再度採りあげたい。
政府の要請の背景には、当時の東海大地震発生への危惧と反原発の世論が反映されていた。しかし、それは国の法律に基づくものではなかった。政権の恣意で事故を起こしていない原子炉を停止させ、多額の損失を電力会社に課すことは、憲法に定める財産権の侵害ではないか(2)。原発の操業停止が事業者の意思や電力の需給見通し、コストの問題を検討せず、政策判断で行われたなら、そのための損害は政府が負担すべきであろう。
また他にも例がある。九州電力川内発電所が定期検査で運転停止したのは2011年5月であった。通常なら検査を終了し、書類審査と使用前検査を経て再稼働できるはずであったが、結果的には4年以上も停止を余儀なくされた。その直接の原因は、原子力規制委員会が「新しい安全審査が終わるまで動かさない」と決め、新安全基準による審査が終了するまで合格証を出さなかったためであるが、その法的根拠は存在しない(3)(4)。この規制委員会の方針は全国の原発を止める根拠になってしまい、影響を拡大させた。
このまま、原子力発電所を法的根拠がない行政の恣意的な運用で止め続ければ、日本は法治国家ではなくなってしまう。原発停止による影響は、電気代上昇や二酸化炭素排出量の増加を含め甚大になっている。国民はこの影響の原因が法律違反にあることを理解すべきであり、電力会社は過去の施策の反省を求めて正論を主張する必要がある。福島原発事故の後で、原子力発電の信頼回復が必要である。しかし、異常な状況にあることで、そうした取り組みが行えなくなっている。
2.福島原発事故に対する原賠法の適用は正当に行われているか(5)
当時政府は事故の影響を全て東電の責任にするような施策を採り、マスコミや世論もこれに異論をはさんでいない。また、政府は緊急を要する損害賠償問題を超えて電気事業システムの見直しまで行おうとしている。このままでは影響がますます拡大・複雑化するので、原賠法に関する問題点を2点挙げたい。
(1)“異常に巨大な天災地変”なら、東電の責任は免責されるのではないか?
原発事故の損害は、避難生活や風評被害等無数にあり、予想される補償額は兆円の規模を超えているし、それが何時まで続くのかも分からない。この巨額な賠償の法的根拠をあいまいにしておくべきでない。
原賠法第3条は、「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない」と定めている。原発事故の直前に発生した巨大地震と津波は、ただし書きにある“異常に巨大な天災地変”に相当するのではないか。東電は正論を主張すべきである。
(2)東電の国有化や電力システム改革は原賠法の目的に合っているのか?
原賠法はその第1条に「この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が発生した場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もって被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする」と定めている。当時政府は、原子力損害賠償支援機構を作って国が損害に対して仮払いできるように原子力事故被害緊急措置法を成立させ、さらに緊急特別事業計画の認定や総合特別事業計画を通して2012年に東電を事実上国有化し、事故を起こした原子炉の廃炉措置を決めた。
しかし、原賠法は民間事業者の独立を前提としていたはずであり、国有化という異常な方法は支援方法の逸脱ではないか(2)。
政府はさらに損害補償の問題と同時に、発送電分離を含めた電力システム改革を進めており、2022年までにそれが行われる予定である。緊急性を要する損害賠償の問題と電気事業のあり方の問題とを同時に行うことによって、将来の電力事業、原子力事業の発展に悪影響を与えかねない状況を作り出している。電力自由化については既に広く議論されている。(7)(8)しかし当事者である電力会社が、福島原発事故の後で社会的な批判を受け、発言を封じられてしまった。電力事業が適切な形で自由化されるかは不透明であり、事故処理への影響も不透明になっている。電力会社は電力システムのあるべき姿を主張し、事故影響の拡大・複雑化を防止してほしい。
3.必要以上の放射線防護対策を東電が負担すべきなのか?
事故直後政府は住民の強制避難を指示し、食品安全基準や除染目標を定めたが、これらの規制は必要以上に厳しい。放射能による影響で誰も犠牲になっていないし、健康障害も報告されていないが、長期避難のために福島県だけでも1800人を超える震災関連死が発生した。欧米より1/10~1/100も厳しい食品安全基準のため、東北の農水産物の不買運動や風評被害がいまだに国内外に及んでいる。また、1mSv/年のような低い除染目標を定めたため、除染に膨大な税金を使っている(6)。
放射線被ばくの人体への影響については、“100mSv以下なら被ばく以外の日常生活の諸々のリスクと比較して見分けが付かなくなるほど小さい”ことがICRP等により国際的に認められている。住民の被ばく量はかなり早い時期から低いと分かっていたし、汚染時の放射線量は時間の経過とともに減衰する。
もし政府がもっと早い時期に住民避難を解除すれば、犠牲者は大幅に減ったであろう。法的にも、長期にわたる強制避難は憲法に定められた居住・移転の自由や財産権の保護に違反するのではないか。法律学者によれば憲法上の権利も「緊急事態」の下では後退を余儀なくされる(2)らしいが、事故発生から数年も経過しているので“緊急”ではないであろう。
早く避難解除すれば助かっていた生命に対する補償、国際的に桁違いに厳しい食品安全基準のために広がっている風評被害に対する補償、自然レベルの低い目標達成のために困難さが続く除染コストに対する補償など、その額は10兆円以上と巨大になっている。この補償を東電だけに負担させるのは論理的におかしい。政府は安全規制の見直しを速やかに行い、影響の拡大とコストの増加に歯止めをかけなければならない。また、東電は責任の所在を明らかにするため正論を主張すべきであり、それが原発に対する国民の信頼回復につながるであろう。
4.結言
福島原発事故後の政府の施策について批判的な意見を述べたが、意図するところは災害からの早期復興であり、原発に対する国民の信頼回復であり、電力の安定供給による明るい未来への期待である。“放射能は怖い”の世論の中で、正当な意見や批判が拒否され、今の繁栄の礎となった電力会社の貢献は忘却され、非難のみが飛び交っている。この異常な流れが不合理な政策を可能にし、避けることのできた被害を拡大している。
70年前の太平洋戦争の際、新聞やラジオが戦意を煽り、これに世論が同調し、結果が見えていた戦争を遂行して大災害となった。過ちは繰り返してはならない。
参考文献:
(1)森本紀行「福島原子力事故の責任-法律の正義と社会的公正」、日本電気協会新聞部、2012年9月3日
(2)斎藤浩(編)「原発の安全と行政・司法・学界の責任」、(株)法律文化社、2013年7月15日
(3)安念潤司「原子力規制委員会と法治主義」Global Energy Policy Research、2015年 9月7日
(4)池田信夫「安倍政権を揺るがす“日本的ダブルスタンダード”-“法的安定性”のない政治が原発や安保を混乱させる-」Japan Business Press、2015年8月13日等
(5)井上薫「原発賠償の行方」、新潮新書、2011年11月20日
(6)若杉和彦「私の意見-安全規制が原発事故を長期化させていないか?復興加速のため避難・食品安全・除染目標の見直しを求める」日本原子力学会誌、2015年7月
(7)山本隆三「電力自由化と原子力発電所建設の影響-欧米に学ぶ自由化の教訓-」日本原子力学会誌、2014年12月
(8)井上雅晴「電力改革論と真の国益」エネルギーフォーラム新書、2014年7月2日
(2015年12月7日掲載)

関連記事
-
環境団体による石炭火力攻撃が続いている。昨年のCOP22では日本が国内に石炭火力新設計画を有し、途上国にクリーンコールテクノロジーを輸出していることを理由に国際環境NGOが「化石賞」を出した。これを受けて山本環境大臣は「
-
企業で環境・CSR業務を担当している筆者は、様々な識者や専門家から「これからは若者たちがつくりあげるSDGs時代だ!」「脱炭素・カーボンニュートラルは未来を生きる次世代のためだ!」といった主張を見聞きしています。また、脱
-
「世界で遅れる日本のバイオ燃料 コメが救世主となるか」と言う記事が出た。筆者はここでため息をつく。やれやれ、またかよ。バイオ燃料がカーボンニュートラルではないことは、とうの昔に明らかにされているのに。 この記事ではバイオ
-
アゴラ研究所・GEPRは12月8日にシンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」を開催しました。200人の方の参加、そしてニコニコ生放送で4万人の視聴者を集めました。
-
IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 前回の論点㉒に続いて「政策決定者向け要約」を読む。 冒頭
-
菅首相が昨年末にCO2を2050年までにゼロにすると宣言して以来、日本政府は「脱炭素祭り」を続けている。中心にあるのは「グリーン成長戦略」で、「経済と環境の好循環」によってグリーン成長を実現する、としている(図1)。 そ
-
英国ではボリス・ジョンソン保守党政権が脱炭素(ネット・ゼロ)政策を進めている。だが、家庭用のガス使用禁止やガソリン自動車の禁止等の具体的な政策が明らかになるにつれ、その莫大な経済負担を巡って、与党内からも異論が噴出してい
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間