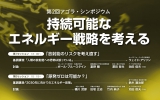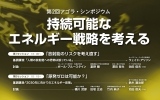今週のアップデート - 原子力再稼動、やり残したもの(2015年8月24日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
原子力政策研究者の諸葛宗男氏に寄稿いただきました。8月11日に九州電力の川内原子力発電所が再稼働しました。ところが、国民に広がる原子力への不信感は払拭されていません。これは政府、原子力規制委員会が、政策をめぐり分かりやすい広報活動をまったくしていないためとの指摘です。再稼動を機に、説明にも力を入れるべきでしょう。
環境法研究家の東田八幡さんの寄稿です。原電敦賀の問題につき、シンポジウム、原電公開資料の検証の中で見えてきた、規制委員会の審査の問題についてまとめています。
3) 再エネ導入と電力供給力確保の両立は難しい-ドイツの事例から
提携する国際環境経済研究所のホームページに掲載された同所主席研究員・理事の竹内純子さんの解説。ドイツは電力自由化と再エネ拡大を同時進行させました。日本もこれから始めようとしています。しかし、供給力確保、天候次第の再エネの安定的使用は難しく、試行錯誤が続いているようです。
今週のリンク
民間の団体、原子力国民会議がセミナーを行います。テーマは、電力自由化、そして地層処分とは何か。興味のある方は、ご参加ください。GEPRも協力します。
2)安倍政権を揺るがす「日本的ダブルスタンダード」-「法的安定性」のない政治が原発や安保を混乱させる
池田信夫アゴラ研究所所長の論考です。JBプレス8月13日掲載。エネルギー、原子力政策では、法律外の取り組みが積み重なっています。景気の悪化の中で、安倍政権の支持率にも影響しかねません。このあいまいな日本的対応を是正すべきでしょう。
3)川内原発の再稼働が必要な4つの理由-再稼働がもたらすリスクとベネフィット
山本隆三常葉大学経営学部教授。ウェッジ・インフィニティ8月18日掲載。川内原発が再稼動しました。その理解は多くの人から得られた状況ではありません。日本と九州の経済にとって、いかに必要かを分析しています。
日本経済新聞8月20日記事。原子力規制の見直し作業を進めていた自民党のプロジェクトチームの草案がまとまりました。内容はこの記事にじゃ詳細は出ていませんが、当初の全面組織改正案よりは、かなり後退しました。規制組織をさわると安倍政権が批判を受けることを懸念したものと思われます。
SAIS米韓センター、ジョセフ・ベルムデッツ研究員。2015年8月発表。SAISはジョンズホプキンス大学ポール・H・ニッツェ高等国際関係大学院(英語:Paul H. Nitze School of Advanced International Studies)で米国の研究機関。北朝鮮の核戦略の概観として。最後の「北朝鮮は、日本の軍事施設(米軍と自衛隊の基地やミサイル防衛システムなど)や一般市民を狙った核攻撃を行うことに躊躇しない」という分析は、かなり怖いものです。

関連記事
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPRはサイトを更新しました。
-
原子力発電に関する議論が続いています。読者の皆さまが、原子力問題を考えるための材料を紹介します。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーの「バーチャルシンクタンク」であるグローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)はサイトを更新しました。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間