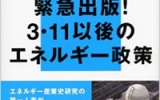使用ずみ核燃料の問題は解決できる
経産省は高レベル核廃棄物の最終処分に関する作業部会で、使用ずみ核燃料を再処理せずに地中に埋める直接処分の調査研究を開始することを決めた。これは今までの「全量再処理」の方針を変更する一歩前進である。
 写真・六ケ所村、日本原燃の再処理工場(同社提供)
写真・六ケ所村、日本原燃の再処理工場(同社提供)核廃棄物の処理は、技術的には「枯れた」分野である。その毒性も管理方法もコスト評価も、世界的にほぼ定まっている。本書はその標準的な成果を、プリンストン大学のフォン・ヒッペルを中心とするチームがまとめたものだ。日本についての英文版は公開されている。(日本語翻訳「徹底検証・使用済み核燃料 再処理か乾式貯蔵か–最終処分への道を世界の経験から探る」(合同出版))
その結論を引用しよう:
1・プルトニウムは核兵器物質である。使用ずみ核燃料の中にあるプルトニウムは実質的にアクセス不能だが、分離ずみプルトニウムは、核テロリストにとって魅力的なターゲットになる。日本が毎年分離することを計画している8トンのプルトニウムは、長崎型原発1000発分をつくるのに十分な量である。
2・核燃料サイクルは経済的に意味がない。非在来型を含めたウランの埋蔵量は数百年分あり、再処理で節約する必要がない。再処理で節約できる効果は25%程度で、ウラン濃縮技術を高度化すれば実現できる。
3・再処理のバックエンドコストは直接処分に比べて2倍だが、それに見合う経済的利益がない。高速増殖炉は技術的に困難で、経済的に成り立たない。MOX燃料をつくるコストは高く、プルトニウムを無料でもらっても引き合わない。
4・最終処分場は存在する。六ヶ所村にキャスクによる乾式処理の中間貯蔵施設を設置し、各地の原発の核燃料プールの廃棄物を受け入れればよい。最終的には地層処分も六ヶ所村で可能だが、その検討は数十年先で十分だ。
5・残るのは、政治的課題である。「核廃棄物を50年以上は置かない」という国と青森県との協定を改正し、最終処分場として位置づける必要がある。県もすでに核燃料税の対象を「再処理される燃料」から「貯蔵される燃料」に切り替えている。
6・処理コストは最終的に電力会社が負担するので、彼らも直接処分に切り替えたほうが負担が小さくてすむ。再処理をやめると、国の「再処理等積立金」による融資が受けられなくなるが、これは目的を変更して直接処分を含めればよい。
これは役所も電力会社も含めて、関係者のほぼ一致した認識だろう。1980年代まではフランスのように核燃料サイクルを積極的に進めた国もあったが、現在では核兵器をもたないのに再処理を進めているのは日本だけだ。アメリカは余ったプルトニウムに懸念を示し、全量再処理の方針を転換するよう求めてきた。
技術的な解決策も明らかなので、残るのは「ここまで再処理工場をつくってきたのにもったいない」というサンクコストの錯覚だが、今までかかった2兆円以上のコストや処理技術のかなりの部分は最終処分場に転用できる。それよりも今後、無理して大量のプルトニウムを作り続けることによるコストは、10兆円を超える。この撤退の判断は、首相にしかできないだろう。
(2015年2月23日掲載)

関連記事
-
筆者は基本的な認識として、電力のビジネスモデルの歴史的大転換が必要と訴えている。そのために「リアルでポジティブな原発のたたみ方」を提唱している。
-
昨年夏からこの春にかけて、IPCCの第6次報告が出そろった(第1部会:気候の科学、第2部会:環境影響、第3部会:排出削減)。 何度かに分けて、気になった論点をまとめていこう。 気候モデルが過去を再現できないという話は何度
-
最大の争点 EUタクソノミーの最大の争点は、原子力発電を善とするか悪とするかの判定にある。 善すなわちグリーンと認定されれば、ESG投資を呼び込むことが可能になる。悪となれば民間投資は原子力には向かわない。その最終判定に
-
今年も台風シーズンがやってきた。例年同様、被害が出る度に、「地球温暖化のせいで」台風が「激甚化」している、「頻発」している、といったニュースが流れるだろう。そこには毎度おなじみの“専門家”が登場し、「温暖化すれば台風が激
-
ロシアの原子力企業のロスアトム社は2016年に放射性ヨウ素125の小線源の商用販売を開始する。男性において最も多いがんの一つである前立腺がんを治療するためのものだ。日本をはじめとした国外輸出での販売拡大も目指すという。
-
はじめに 読者の皆さんは、「合成の誤謬」という言葉を聞いたことがおありだろうか。 この言葉は経済学の用語で、「小さい領域・規模では正しい事柄であっても、それが合成された大きい領域・規模では、必ずしも正しくない事柄にな
-
ロイターが「世界の海面上昇は史上最高になり、海面が毎年4.5センチ上がる」というニュースを世界に配信した。これが本当なら大変だ。この調子で海面が上がると、2100年には3.6メートルも上がり、多くの都市が水没するだろう。
-
高浜3・4号機の再稼動差し止めを求める仮処分申請で、きのう福井地裁は差し止めを認める命令を出したが、関西電力はただちに不服申し立てを行なう方針を表明した。昨年12月の申し立てから1度も実質審理をしないで決定を出した樋口英明裁判官は、4月の異動で名古屋家裁に左遷されたので、即時抗告を担当するのは別の裁判官である。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間