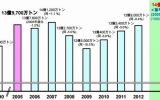原子力規制委員会の活断層審査の混乱を批判する
 日本原電・敦賀原発2号機(同社より)
日本原電・敦賀原発2号機(同社より)問題だらけの活断層審査
原子力規制委員会、その下部機関である原子力規制庁による活断層審査の混乱が2年半続いている。日本原電の敦賀原発では原子炉の下に活断層がある可能性を主張する規制委に、同社が反論して結論が出ない。東北電力東通原発でも同じことが起こっている。調べるほどこの騒動は「ばかばかしい」。これによって原子炉の安全が向上しているとは思えないし、無駄な損害を電力会社と国民に与えている。
同委員会が決めた規制基準では、活断層の上に原子炉の重要構造物を建設してはならないとしている。同委員会の外部機関である日本原電、東北電力などの原子炉の下に活断層があると指摘した。これは原子炉を事実上、使えなくするものだ。
活断層をめぐる審査では以下の問題点がある。
「規制委は活断層の可能性があると報告案をまとめようとしている。ないことを論証する『悪魔の証明』を行政機関が電力会社に迫っている」
「活断層があるとしても、規制委が法律の遡及適用を求める根拠条文が法令上明確ではない」
「原子炉は建設に1基の新設に3000億円以上の費用がかかる電力プラントである。それを正当性のある手続きではなく行政機関が使えなくしている。これは企業の財産権、経済活動を侵害している」
「規制委の有識者会議は、活断層をめぐる科学的な分析が不十分であるし、専門家の意見を聞かない」
「現場のノンキャリアの退職間際の事務官が審査の指揮を執り、その人物のコミュニケーション能力が低く、規制対象の電力会社と適切な対話ができない。幹部のキャリア官僚、委員がそれを放置して、責任逃れをしている」
「規制の横暴をメディアがほとんど伝えない。政治も介入しない」
一連の問題は原発の長期停止の一因になっている。もしこのような形で活断層審査が続けば、敦賀原子力発電所2号機をつぶされかねない日本原電、さらに東通原発1、2号機をつぶされかねない東北電力の経営破綻を招く可能性がある。それは行政活動による企業倒産であり、財産権の侵害だ。さらに国民負担の増加をもたらす。この行政の横暴を止めなければならない。
現状はどうなっているのか
原子力規制委員会の有識者会合の報告書案は一昨年13年5月に「敦賀原発2号機の下の断層が活断層と否定できない」という趣旨の報告書をまとめた。昨年6月までの経緯を以下の論考でまとめた。
「敦賀原発の活断層判定、再考が必要(上)・対話をしない原子力規制委」
「敦賀原発の活断層判定、再考が必要(下)・行政権力の暴走」
原電側が反論の資料を大量に出しておりその方が説得的であること、各国の研究者が「活断層でないとする原電の主張が妥当」と分析していること、そしてこの認定をする有識者会合は法律上、明確な規定がないことを指摘した。また活断層が事後的に見つかったとしても米国ではその対応を工事で行って安全性を高めており、「あれば廃炉」という日本の行政の態度はかなり乱暴であることも述べた。
一連の判断で強引な議事運営をしてきた島崎邦彦規制委委員は、昨年9月に退任した。ところが、規制委は活断層の認定の方向に動いている。
昨年12月10日、敦賀2号機をめぐる「有識者会合ピア・レビュー会合」が開かれた。ピア・レビューとは学術用語で専門家がさまざまな観点から、意見を述べる会議だ。
ところが議事録を読むと専門家からの批判がかなり強い。反原発活動への参加を公言する東洋大の渡辺満久教授などもメンバーで活断層と指摘している。ところがこうした人らの旗色は悪い。以下のコメントがあった。
産総研研究者 「科学的でも技術的でもないですよね。それはもう明らかに何らかの別の判断が入っているということになります」 「データがきちっと評価してないんじゃないかという疑問があります」
岐阜大学准教授「事業者側の考え方をある意味否定をしたいということであれば、やっぱりそこは丁寧な説明が必要」
京都大学名誉教授「(資料の不備を指摘して)現場でちゃんとチェックされたんですか」
批判一色のためか会合座長の加藤照之東京大学地震研究所教授は、「安全側に判断するというのは、これはやはり科学ではなくて、行政であろうというふうに私には思えます」と引き取った。これは明らかに規制委の判断に分が悪い。
ところが規制委とその下部機関である規制庁は、ピア・レビュー会合におけるコメントを反映させず規制委員会に最終報告を示す方向という。専門家が結論のおかしさを指摘し、その修正を求めているにもかかわらずだ。
手続き上の問題だらけ
そもそも活断層だと認定する有識者会合の評価が、どのような行政上位置づけのあるものか、不透明だ。この組織の位置を示す法令はないのだ。その意見を原子力規制委員会が受理し、事実上、原発の活断層を認定することになっている。これは行政権を、権限のない人に委ねることを意味する。この仕組みは問題だ。
さらに原子力規制委の行動が「行き当たりばったり」だ。2013年2月に、「ピア・レビューの結果については、必要に応じ評価書案に反映する」としていた。(規制庁文書)ところが、その後に同年3月に規制委員会の名前で「実施方法」という文章で「当該破砕帯の再評価をするものではなく」という一文を入れた文章を作った。そして今回のピア・レビューでも後者の文章を使った。このように方針が恣意的に、突然変わる。公開の規制委員会の議事録を見ると、同委員会はこの問題で審議をして正式な決定をした形跡がない。規制庁側の責任者が勝手に規制委の名前を使っている疑いもある。
一連の規制委員会の活断層審査の事務を運営しているのは、旧原子力安全・保安院出身の小林勝規制庁管理官だ。個人攻撃の意図はないが、この人はいわゆるノンキャリの技官で定年間近という。筆者はここに官僚人事のいやらしさを感じる。この問題は退任した島崎邦彦原子力規制委員会委員の強引な手法で混乱した。しかし、一度決定が出た以上、なかなかくつがえしたくないようだ。しかし、このままプラントの廃炉になれば、日本原電は行政訴訟に訴える可能性がある。そうした危うい問題をノンキャリ役人一個人に委ねて責任を負わせ、キャリア官僚の幹部は責任から逃げようとしているように見える。
規制委を退任した高官の話を聞いた。この人は活断層の判定問題について「かなりの問題がある」「法令根拠がない行為は、しっかりとした根拠を基づくものに改めなければならないだろう」と認めた。しかし担当でないので「口を出せなかった」として、自分に責任はないことを強調していた。日本の行政官僚によく見られるこうした無責任の連鎖が問題をおかしくしているのだろう。
独立が独善になっていないか
今回のピア・レビューは、行政の一度行った活動を専門家が事実上否定するという、大きな意味のあることだ。これはメディアにとってニュースであろう。ところが反原発を社説で標榜する朝日新聞は「敦賀活断層認定、別の識者が検証 説明追加求める意見も」と報じた。ニュアンスがゆがめられて伝わっている。産経、読売新聞以外、他のメディアも似た論調だ。そしてテレビは、規制委の細かな議論を伝えない。あまりにも専門的すぎるので、メディアは規制委側の情報に頼っているのだろう。しかし今回は明らかに規制委・規制庁の誘導の影響が強すぎる。
反原発の論調が既存メディアに広がっているために、原子力の利用を妨げる規制委・規制庁への批判を自粛しているのかもしれない。しかし活断層審査は原発の賛成・反対の問題ではない。規制委・規制庁による行政権の濫用、電力会社の財産権の侵害、企業活動の妨害の問題である。これは健全な報道の姿ではない。
さらに問題が専門的すぎるため、そして規制委が他の行政機関からの独立性を法律上認められているため、政治家も介入しない。
なぜ規制委・規制庁がここまで頑迷なのか、理解に苦しむ。誤りがあれば修正すればいいことなのに、無理に日本原電の原子炉を廃炉に追い込もうとしている。規制委は有識者会合の報告を受け取り、敦賀原発2号機の再稼働を事実上放置することになるだろう。日本原電は訴訟を行うだろうが、その決定は長引くと見込まれる。
電力会社の損害は膨らみ、それは料金の形で国民が負担する。あまり有能と言えない役所と役人が、日本の電力産業、原子力産業、そして日本経済とアベノミクスの未来を左右している。この状況はあまりにもおかしい。
規制委の活動原則には「科学的・技術的な見地から、独立して意思決定を行う」とある。独立は決して、独善であってはならない。「科学的・技術的な見地」に立って、規制を受ける事業者との対話を行い、適切な行政の姿に変えるべきだ。規制委は発足か2年半経過した。規制委員会の設置法では3年以内の見直しが予定されている。これを機会に同委の独善をただす必要がある。
(2015年1月26日掲載)

関連記事
-
今年の10月から消費税率8%を10%に上げると政府が言っている。しかし、原子力発電所(以下原発)を稼働させれば消費増税分の財源は十二分に賄える。原発再稼働の方が財政再建に役立つので、これを先に行うべきではないか。 財務省
-
中国の台山原子力発電所の燃料棒一部損傷を中国政府が公表したことについて、懸念を示す報道が広がっている。 中国広東省の台山原子力発電所では、ヨーロッパ型の最新鋭の大型加圧型軽水炉(European Pressurized
-
後半では核燃料サイクルの問題を取り上げます。まず核燃料サイクルを簡単に説明しましょう。核燃料の95%は再利用できるので、それを使う構想です。また使用済み核燃料の中には1-2%、核物質のプルトニウムが発生します。
-
風評被害: 根拠のない噂のために受ける被害。特に、事件や事故が発生した際に、不適切な報道がなされたために、本来は無関係であるはずの人々や団体までもが損害を受けること。例えば、ある会社の食品が原因で食中毒が発生した場合に、その食品そのものが危険であるかのような報道のために、他社の売れ行きにも影響が及ぶなど。
-
バックフィットさせた原子力発電所は安全なのか 原子力発電所の安全対策は規制基準で決められている。当然だが、確率論ではなく決定論である。福一事故後、日本は2012年に原子力安全規制の法律を全面的に改正し、バックフィット法制
-
田中 雄三 前稿では、日本の炭素排出量実質ゼロ達成の5つの障害を具体例を挙げて解説しました。本稿ではゼロ達成に向けての筆者の考えを述べていきます。 (前回:日本の炭素排出量実質ゼロ達成には5つの障害がある①) 6. I
-
早野睦彦 (GEPR編集部より)GEPRはさまざまな立場の意見を集めています。もんじゅを肯定的に見る意見ですが、参考として掲載します。 高速増殖炉もんじゅ(福井県敦賀市) (本文) もんじゅの存在意義の問いかけ 「政府
-
政府は2030年までに温室効果ガスを2013年比で26%削減するという目標を決め、安倍首相は6月のG7サミットでこれを発表する予定だが、およそ実現可能とは思われない。結果的には、排出権の購入で莫大な国民負担をもたらした京都議定書の失敗を繰り返すおそれが強い。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間