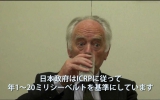福島の強制避難政策の誤り-チェルノブイリ、自主帰還の近郊住民と語る(下)
(上)「故郷に住むのは当然だ」から続く
 (写真1)自主帰還者のイワンさん
(写真1)自主帰還者のイワンさん4・ウクライナでの避難政策の失敗–地域社会が壊れる
こうしたチェルノブイリ事故の立ち入り制限区域で自主的に帰宅する帰還者は「サマショール」(ロシア語で「自ら住む人」という意味)と呼ばれている。欧米を中心に、チェルノブイリ近郊は「生命が死に絶えた危険な場所」と、現実からかけ離れたイメージが広がっている。サマショールの存在は最近、西欧諸国に知られたようで、それは驚きを持って伝えられた。(TED日本版「チェルノブイリに住む理由、それは故郷だから」)
旧ソ連では86年のチェルノブイリの原発事故直後に、30キロ圏の住民に強制退去を行った。その数は約11万6000人という。そして88年までに移住者が集住した町、スラブチッチをつくった。そこの人口は現在2万4000人ほどだ。その他の人は別の地域に分かれて住んでいる。
ウクライナでは原則として、事故原発から30キロ圏内の居住を禁じている。しかし、こうした帰還者の居住を追認してしまった。
ソ連邦崩壊後にウクライナでは、チェルノブイリ周辺地区の避難規制を改めた。年間被ばく15mSvまでが「優先的移住」、また40mSvが「強制退去」とした。その法に基づき90年代に、放射線量が低い場所に家があり希望した住民は帰還した。前述のイワンさんもそうだった。
ところが大半の住民は、新しい土地で生活を始めたために帰還しなかった。一部の人は帰還を望み、実際に戻った。しかし30キロ圏では放射能の汚染度はまちまちで、帰れない場所、帰れる場所が複雑になった。帰れない場所の住民は、近くの場所は帰れるのに、なぜ自分たちはできないのかと不満を表明した。そうした抗議が増えたために、政府は数年後に原則として、30キロ内への帰還を再び禁じたという。再び移住を促されたのに、イワンさんは住み続けてしまった。日本では、こうした移住をめぐるウクライナの政策の混乱は、あまり伝わっていない。
5・敵は放射能だけではない–ストレス、デマが健康を壊す
30キロ圏内に、私たちの入る時はウクライナ政府の管轄の立ち入り禁止区域庁職員のガイドがつく。その人によれば、事故後1000人程度のサマショールが30キロ圏に暮らしている。高齢者が大半だが、だいぶ亡くなってしまい今では100人ほどが残る。平均年齢は80才以上という。WHO(世界保険機関)によれば、ウクライナの平均寿命は70才なのでかなり高齢だ。
サマショールについての本格的な医療調査は筆者の調べた日本語、英語の調査では見つからなかった。しかし総じて長命という。チェルノブイリの30キロ圏内において放射線量は、私の立ち寄った場所ではたいてい毎時0.1〜0.5マイクロシーベルトだった。この程度ならば健康被害の可能性は少ない。そして低線量の被ばくを継続的に受けても、健康被害はチェルノブイリ周辺で観察されていない。健康被害は事故直後の汚染によって起こった。
もちろん筆者はチェルノブイリ原発の周辺が安全であると、詳細なデータがないのに主張するつもりはない。しかし放射能だけではなく、継続的な移住、デマによる継続的なストレスが健康に悪影響を与えたようだ。前出のイワンさんも「自分に健康の被害はない。移住した人は多く亡くなった。ストレスのせいだろう」と話していた。
6・日本の避難解除の遅れは間違っている
チェルノブイリと、日本の福島原発事故の対策を比べてみよう。
日本では原発事故直後に、福島原発から30キロ圏の避難が行われ、約16万人の人が故郷を離れた。低線量の場所から段階的に避難指示は解除されたが、今年3月時点で約9万人の人が、避難したままだ。そして、いつ帰れるか先行きの見えない曖昧な状況が続いている。
理由は複合的だ。その第一の理由は、年間1mSvまでの被ばく量の低減をかかげて、除染を政府が行っているためだ。これは建物や舗装道路を水洗し、表土をはぎ、その物質を放射性廃棄物として処理する。大変手間がかかる取り組みだ。除染の目標線量を低くしすぎたために、実行は大変遅れている。(筆者の記事「福島の除染「1ミリシーベルト目標」の見直しを」「(上)意味はあるのか」)(「(下)パニックが政策決定に影響」)
第二に、人々の意識が変わってしまった。帰還を望む人よりも、移住地で生活を始めた人が多く、3年経過した今では、約2割の人しか帰還を望んでいない。(復興庁「住民意向調査(福島県大熊町、双葉町)」2014年11月14日公表)
第三に、現状復帰は、補償の打ち切りを招きかねないため、誰も言い出せないのだろう。現時点で被災者に東電からの補償金が支払われている。それは当然であるが、その補償は過剰であり、地域と人々の再建に役立つ形になっているか、筆者は疑問に思う。(GEPR記事(「東電宝くじ」…補償と除染が原発被災地に波紋」「福島・南相馬、復興の動きを聞く【原発事故3年】」「原発事故、政府の避難指示は適切だったか【原発事故3年】」))
そして第四に、福島について必要以上に危険視する、恐怖感情が社会に広まってしまった。そして危険を過剰に主張する人々が住民にも、居住者以外の人々にもいる。そうした人々の声に行政は反応してしまう。
こうした理由が複合して、福島原発事故の避難者がいつ帰れるか分からないあいまいな状態が続いている。その結果、多くの弊害が出た。帰還が遅れることによって、健康被害が広がった。復興庁の統計で「震災関連死」と呼ばれる死者は14年3月末の死者数が全国で3089人になるが、そのうち福島県が1704人と突出している。これは高齢者を中心にしたストレスによる健康被害によるものだ。
そして時間が経つほど、30キロ圏内にある福島浜通り地区の地域再建は難しくなる。この地域の放射線量では、健康被害の可能性はないと専門家は一致している。だとしたら早期帰還を断行してもよかった。
しかし3年超の時間の経過で、もはや地域の人々の絆が壊れ始めている。さらに状況の放置によって、東電と国の支出が増えている。補償は世論が東電に責任を負わせようとする中で無限に膨らんでいく可能性がある。しかし東電は経営破綻状態にあるため、その原資は税金だ。
チェルノブイリ事故では、当時のソ連政府は、強制避難を決め、それを実行した。ソ連は当時、社会主義体制下にあり被災地域の土地や不動産は原則として国有が多く、強権的な警察国家であったために人々を移住させやすかった。しかし日本の福島原発事故より決断と行動が速い。
しかしチェルノブイリ周辺の一律の避難という政策は、かなりおおざっぱな安全の確保策だった。前述の帰還住民のように避難に不満を持つ人が出た。行政上の手間がかかる住民への説明、場所ごとの帰還と復興という措置を、ソ連と後継のウクライナ政府は放棄し、一律避難という荒っぽい政策を続けてしまった。ソ連崩壊という社会混乱の中で、その余裕がなかったのであろう。
7・無駄な社会コストの拡大を止めよ
筆者はソ連とウクライナの政策を失敗と思う。「この土地を活用できないのか」という、自主帰還者イワンさんの声に同意する。チェルノブイリ30キロ圏の広大な面積の土地が放置され、28年の時間を経て自然に帰っていることを目の当たりにした。これを活用できないのはもったいない。
筆者は福島原発の自主避難区域に取材で入り、福島原発の周囲で健康被害の可能性が少ないのに、無駄な除染が行われ、人がいないために地域社会が消滅した姿をみた。そして、かつての住民のつながりが避難によって急速になくなっていること、また高齢者の避難による死亡など社会混乱が起こっているのを見聞した。
ウクライナでも、日本でも、一律の強制避難という政策は、原子力災害の発生直後には、必要であったろう。被害の程度が分からないのだから。しかし被害の実態が明らかになった段階で、それによって起こりえるリスクに合わせて、対策とそれに必要な社会コストを考えるべきであった。
一律避難を続ければ、その後にさまざまな問題が出ることはチェルノブイリで先行した事例があった。それを日本政府はまったく学んでいなかった。よく似た無駄と混乱が起こっている。
私は福島において早期の現状復帰が必要と考えている。無駄な除染をやめ、どの土地に住むか、住まないか、合理的、かつ住民の意向を入れた線引きをして、復興と地域再建の計画を早急に出すべきだ。そして住民の自己決定の選択肢を増やす形に、政策を見直すべきだ。
あいまいな現状の政策を続けると、福島浜通り地区に悪しきイメージが定着し、人々の多くは帰還せず、地域社会は完全に壊れてしまうだろう。チェルノブイリと同じように。それは日本人なら誰も望まないはずだ。


政治の実行、住民、また他地域の人の冷静な対応が必要だ。しかし誰も問題を直視しようとも、行動しようともしない。チェルノブイリの失敗を、日本は福島でなぜ繰り返すのだろうか。
(2014年12月8日掲載)

関連記事
-
近代生物学の知見と矛盾するこの基準は、生物学的損傷は蓄積し、修正も保護もされず、どのような量、それが少量であっても放射線被曝は危険である、と仮定する。この考えは冷戦時代からの核による大虐殺の脅威という政治的緊急事態に対応したもので、懐柔政策の一つであって一般市民を安心させるための、科学的に論証可能ないかなる危険とも無関係なものである。国家の安全基準は国際委員会の勧告とその他の更なる審議に基づいている。これらの安全基準の有害な影響は、主にチェルノブイリと福島のいくつかの例で明らかである。
-
アゴラ研究所は、9月27日に静岡で、地元有志の協力を得て、シンポジウムを開催します。東日本大震災からの教訓、そしてエネルギー問題を語り合います。東京大学名誉教授で、「失敗学」で知られる畑村洋太郎氏、安全保障アナリストの小川和久氏などの専門家が出席。多様な観点から問題を考えます。聴講は無料、ぜひご参加ください。詳細は上記記事で。
-
【要旨】(編集部作成) 放射線の基準は、市民の不安を避けるためにかなり厳格なものとなってきた。国際放射線防護委員会(ICRP)は、どんな被曝でも「合理的に達成可能な限り低い(ALARA:As Low As Reasonably Achievable)」レベルであることを守らなければならないという規制を勧告している。この基準を採用する科学的な根拠はない。福島での調査では住民の精神的ストレスが高まっていた。ALARAに基づく放射線の防護基準は見直されるべきである。
-
アゴラ研究所は10月20日、原子力産業や研究会の出身者からなる「原子力学界シニアネットワーク」と、「エネルギー問題に発言する会」の合同勉強会に参加した。 そしてアゴラ研究所所長の池田信夫さんが、小野章昌さん(エネルギーコ
-
放射線医学総合研究所は8月28日、東京電力福島第一原子力発電所近くの放射線量が比較的高い地域に生えているモミの木を調べたところ、幹の先端が欠けるなどの異常が通常より高い割合で現れていたと発表した。
-
アゴラ研究所の行うシンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」の出演者が、GEPRに寄稿した文章を紹介します。
-
「死の町」「放射能汚染」「健康被害」。1986年に原発事故を起こしたウクライナのチェルノブイリ原発。日本では情報が少ないし、その情報も悪いイメージを抱かせるものばかりだ。本当の姿はどうなのか。そして福島原発事故の収束にそ
-
一般社団法人「原子力の安全と利用を促進する会」は、日本原子力発電の敦賀発電所の敷地内断層(2号炉原子炉建屋直下を通るD-1破砕帯)に関して、促進会の中に専門家による「地震:津波分科会」を設けて検討を重ね、原子力規制委員会の判断「D?1破砕帯は、耐震指針における「耐震設計上考慮する活断層」であると考える」は見直す必要がある」との結論に至った。(報告書)
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間