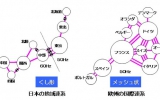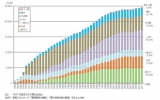蟷螂の斧—河野太郎議員の電力システム改革論への疑問・その3
連系線の運用容量問題への河野氏の疑問
2014年6月11日付河野太郎議員ブログ記事「いよいよ電力の自由化へ」に下記のようなことが書いてある。
○日本国内の電力会社間の連系線の容量を見ていると不思議なことがある。
○東北電力と東京電力間の連系線は1262万kWの容量があるはずだが、東京から東北へ電力を送る運用容量は120万kWと、その10分の1に制約されている。しかし、専門家によれば、この運用容量を超える運用が行われているという。
○中国電力と九州電力の間の関門連系線の容量も556万kWなのだが、中国電力(原文では、四国電力となっていたが、間違いと思われるので、筆者の判断で修正した。)から九州電力へ送電する際の運用容量は30万kWと10分の1以下に抑えられている。しかし、九州電力の新大分火力発電所がダウンした時には中国電力から九州電力へ60万kWを超える送電が行われた。運用容量はどうしたのだろう。電力会社は「短期的な対応だから」と言い訳をしたようだが
このブログは、随分と専門的な内容に切り込んでいて、議員が熱心に勉強されていることが伺われる。ここでは、議員が「不思議なこと」と「どうしたのだろう」と疑問を呈しているポイントについて、見ていきたい。
議員ご指摘の「容量」(東北電力と東京電力間の1262万kWや中国電力と九州電力間の556万kW)は、正確に言うと「全ての設備が健全である前提の下での連系線の熱容量」のことである。つまり、設備事故が発生していない状況において、送電線が過熱しない程度に目いっぱい電気を流すとこれだけ流れる、というものだ。
設備の過熱だけを心配するなら、ここまで電気を流すことが可能なのであるが、実際の運用における容量、つまり運用容量は、これだけではなく電力系統に事故が起こった場合に、停電が発生しない、あるいは発生しても大規模なものにならない、という視点からの限界を考慮している。
電力系統の運用ルールとは何か
電力系統に起こる事故を想定する基準は、「N-1基準」とよばれる万国共通の考え方がある。電力系統内にN個の設備があるとして、「1設備がトラブルで欠けても(N-1)停電しない。2設備(N-2)以上がトラブルで欠けた場合の停電は許容する」という考え方だ。連系線の運用容量は、このN-1基準を踏まえて、次の①~④を考慮した限界値のうち、最小の値を採用する。
①熱容量 送電線が1回線故障しても、残った回線の温度上昇が許容範囲に収まる(ここで言う熱容量は、送電線が1回線故障した場合を前提に、残った回線で流すことが可能な容量であるので、議員が言う容量《全ての設備が健全である前提の下での熱容量》以下の値。)。
②系統安定度 送電線が1回線故障しても、発電機が安定運転できる。
③電圧安定性 送電線が1回線故障しても、電圧を維持できる。
④周波数維持面 連系線のルート断事故による系統の分離が発生しても、周波数を維持できる。
上記の結果、連系線の運用容量は、「全ての設備が健全である前提の下での熱容量」よりも小さい値になるのが通常である。議員ご指摘の「東京→東北の運用容量は120万kWに制約されている」「中国→九州の運用容量は30万kWに抑えられている」は、上記の基準に則ったものである。これを議員は「不思議なこと」と言っているが、実は世界共通の考え方なのだ。
(注)なお、「全ての設備が健全である前提の下での熱容量」は連系設備を増強しなければ変化しないが、運用容量は、発電設備の状況が変わり、想定する事故の前提が変われば変わりうる。東京→東北の120万kW、中国→九州の30万kWはいずれも最新の値ではない。(最新の値は、電力系統利用協議会「各地域間連系設備の運用容量算定結果−平成26年度」を参照。)
実際の運用−九州電力の緊急融通
さらに議員は、「専門家によれば、この運用容量を超える運用が行われている」とも述べている。確かに、緊急時においては、連系線の運用容量を超えて電気を流すことがある。その考え方について、議員も言及している九州電力の新大分火力発電所がダウンしたケース(2012年2月3日)に即して見てみよう。
中国→九州の連系線の運用容量(30万kW)は、周波数維持面の限界値により決定されている。これは、運用容量を超過して電気を流すと、連系線のルート断事故が発生した際に、九州地域の周波数が低下して、停電が発生するリスクがあることを意味する。
さて2012年2月3日午前4時ごろ、九州電力の新大分火力発電所(230万kW)が設備トラブルにより緊急停止した。停止したのは深夜であったが、夜が明けて需要が増加すると、九州地域が供給力不足となることは必至の状況となった。そのため九州電力は、連系線の運用容量を超えて他地域から緊急融通を受け、計画停電を回避した。
先に述べたとおり、この融通を受けている最中に連系線のルート断事故が発生すると、九州地域の周波数が低下して、広域停電が発生するリスクがあった。しかし、この時は、既に発生した設備事故のために計画停電のリスクが高まってしまっており、それを回避するために、九州電力はルート断事故のリスクを甘受する判断をしたわけである。
これについて議員は「運用容量はどうしたのだろう」と疑問を呈している。しかし、この状況でどちらのリスクを優先して回避すべきかという問いに対する答えは、筆者には自明に思える。議員ご自身が九州電力の責任者であれば、運用容量を超えた緊急融通を受けることになれば、普段から運用容量を過小設定していると外から非難を受けそうだと考えて、緊急融通を受けないことにするのだろうか。逆に仮に停電リスクを甘受したうえで、緊急融通を受けてそれをが「言い訳」と批判されたとしたら、どうお感じになるのだろうか。
建設的な議論で系統整備を検討すべき
こうした考え方は、先ごろ公表された広域的運営推進機関の業務規程に、次のように整理されている。
(緊急時の連系線の使用) 第80条 本機関は、前条のマージン使用その他の対策を行ってもなお、供給区域の需給ひっ迫による需要抑制及び負荷遮断を回避できない又は回避できないおそれがあると認めるときは、次の各号に掲げる手順により、連系線利用申込者が、供給信頼度の低下を伴いつつ運用容量を超えて連系線を使用した供給を行うことを認める。(以下略。強調は筆者による)
この「供給信頼度の低下を伴いつつ」という文言が肝である。既に不測の事態が発生し、ほぼ確実に起こりうるリスクに直面している時は、供給信頼度を平時に確保しているレベルから下げることも甘受して、そのリスクを回避すべき、という考え方だ。
もちろん、平時に確保すべき供給信頼度とは何か、という論点はあり得る。例えば、九州電力によると、中国→九州の連系線ルート事故は、過去40年で5回程度発生しているとのことである。つまり、8年に一度程度の停電のリスクを回避するために運用容量を制限しているわけであるが、このようなリスクを甘受しても、運用容量を増やした方がよいという議論はあり得る。
事実を表していない「(電力会社の)言い訳」などという揶揄的な表現を使ったりするのはやめて、こうした論点についての生産的な議論を進めた方が、電力の安定供給をより確かなものする電力システム改革につながると思うのだがどうだろうか。
これまで3回にわたって、河野太郎議員の電力システム改革論についての疑問等を述べてきた。今後は、竹内純子主席研究員が「ウェッジinfinityのウェブ」で、自らの専門との関連の話題を扱う予定である
(2014年9月16日掲載)

関連記事
-
去る4月5日、経済産業省傘下の電力・ガス取引監視等委員会において「電力市場における競争状況の評価」が討議され、電力自由化一年目が総括されました。この評価は政策的に非常に重要な意味を持つものです。電気事業法では2020年4
-
福島原発事故において、地震によって原子炉の主要設備が破壊されたのではないかという懸念が、社会に広がっている。こうした懸念が、原子力規制委員会による過剰ともいえる地震対策や、原子力発電への不安につながっている。この小論が、そうした懸念を払拭する一助になればと思う。
-
日本の電力系統の特徴にまず挙げられるのは、欧州の国際連系が「メッシュ状」であるのに対し、北海道から 九州の電力系統があたかも団子をくし刺ししたように見える「くし形」に連系していることである。
-
自民党が原子力規制委員会の改革に前向きだ。同委員会の設置法では発足3年での見直し条項が置かれているが、今年9月でその年になる。それに合わせて問題の多い同規制委の活動を組織改編で見直そうとしている。
-
英国は6月23日に実施した国民投票で欧州連合(EU)離脱を決めた。エネルギー政策、産業の影響について考えたい
-
PHP研究所から2012年2月15に発売されるアゴラ研究所代表の池田信夫の著書『原発「危険神話」の崩壊』 (PHP研究所)から、「第2章 放射能はどこまで恐いのか」を公開する。現在の福島と東日本で問題になっている低線量被曝など、放射能と人体の影響について、科学的な知見を分かりやすく解説している。
-
内閣府のエネルギー・環境会議が出した「選択肢」を見て、少しでもエネルギーを知るものは誰もがあきれるだろう。稚拙すぎるのだ。そこで国民の3つの選択肢のひとつとして「原発ゼロ」が示されている。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間