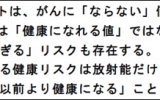今週のアップデート — 原子力をめぐる国民的な議論の必要(2014年5月12日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
宮健三東京大学名誉教授から寄稿いただきました。宮氏は原子力工学の研究者。福島の反省と、適切な議論を訴え、自らの「原子力国民会議」についても紹介しています。福島原発事故の後で、これまで自粛のためか原子力関係者の意見が、社会に出てきませんでした。冷静な議論が広がる状況を歓迎したいです。
2)事業者との対話で高まる原発の安全 –– 米NRCに学ぶ「効果的」原子力規制
GEPR編集者の石井孝明が、何人かの原子力工学者に話を聞き、米国の原子力規制委員会(NRC)の規制の姿をまとめました。間接情報から考えても、その規制は合理的です。混乱の続く、日本の原子力規制委員会の規制と比べると、大きな差があります。日本の是正を期待します。
台湾で原発が政治の道具になっています。福島事故も影響しています。日本とよく似た状況を現地ルポしました。
今週のリンク
ウォール・ストリート・ジャーナル、5月7日社説。(英語)
台湾の混乱を、日韓と対比させながら解説し、同国のエネルギーの脆弱性が高まったと懸念しています。
ゲイル・マーカス 元全米原子力学会会長のコラム。「マーカス博士の部屋」(日本エヌユーエス)。米NRCの規制に関わったマーカス博士のコラム。今回の寄稿で取り上げた「良き規制の原則」がどのようにできたかを紹介しています。
3)NRCの価値観
米国原子力規制委員会(NRC)のホームページ。今回取り上げた規制について示しています。こうした規制理念とその実現指針を、日本の原子力規制委員会は掲げていません。
日経産業新聞5月10日記事。足達栄一郎・日本総合研究所理事の論考。米国の新しい取り組みで、減税と省エネを組み合わせる事例を紹介。節電と省エネが原発事故以来広がりました。こうした取り組みを、税の面から支えることも必要でしょう。
東洋経済オンライン5月9日記事。東芝が復活を遂げつつあるものの、原子力事業が伸び悩みを示しているという話です。福島原発事故や、米国のプロジェクトの混乱。原子力は単価が大きいものの、一度頓挫すると企業収益が大きく左右されてしまいます。
静岡新聞5月11日記事。静岡県の川勝平太知事が、静岡県の浜岡原発(中部電力)の再稼動は、県の条例の未整備、使用済核燃料の問題があるので実質できないと明言。法律に基づかない規制を求めるのは、大変な問題でしょう。

関連記事
-
アゴラ研究所の運営するエネルギー研究機関のGEPRはサイトを更新しました。
-
米国ワイオミング州のチェリ・スタインメッツ上院議員が、『Make CO2 Great Again(CO2を再び偉大にする)』法案を提出したと報じられた。 ワイオミング州では ワイオミング州は長い間、経済の基盤として石炭に
-
福島の原発事故から4年半がたちました。帰還困難区域の解除に伴い、多くの住民の方が今、ご自宅に戻るか戻らないか、という決断を迫られています。「本当に戻って大丈夫なのか」「戻ったら何に気を付ければよいのか」という不安の声もよく聞かれます。
-
崩壊しているのはサンゴでは無く温暖化の御用科学だ グレートバリアリーフには何ら問題は見られない。地球温暖化によってサンゴ礁が失われるという「御用科学」は腐っている(rotten)――オーストラリアで長年にわたりサンゴ礁を
-
100 mSvの被ばくの相対リスク比が1.005というのは、他のリスクに比べてあまりにも低すぎるのではないか。
-
今回の大停電では、マスコミの劣化が激しい。ワイドショーは「泊原発で外部電源が喪失した!」と騒いでいるが、これは単なる停電のことだ。泊が運転していれば、もともと外部電源は必要ない。泊は緊急停止すると断定している記事もあるが
-
有馬純 東京大学公共政策大学院教授 2月16日、外務省「気候変動に関する有識者会合」が河野外務大臣に「エネルギーに関する提言」を提出した。提言を一読し、多くの疑問を感じたのでそのいくつかを述べてみたい。 再エネは手段であ
-
トランプ政権の誕生で、バイデン政権が推進してきたグリーンディール(米国では脱炭素のことをこう呼ぶ)は猛攻撃を受けることになる。 トランプ大統領だけではなく、共和党は総意として、莫大な費用がかかり効果も殆ど無いとして、グリ
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間