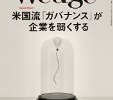今週のアップデート — 原発再稼動とリスク(2014年3月17日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。
今週のアップデート
1)原発は、今の規制で安全になるのか【言論アリーナ・本記】
2)原発は、今の規制で安全になるのか【言論アリーナ・要旨】
アゴラ研究所は、運営するインターネット番組「言論アリーナ」で、「原発は新しい安全基準で安全になるのか」を2月25日に放送しました。原子力規制委員会が行っている諸政策には問題が多く、原発のリスクを高めかねないばかりか、法的な根拠のない対策で問題が多いと、参加者は指摘しています。その報告です。
出席者は東京大学教授(大学院新領域創成科学研究科)の岡本孝司氏、政策家の石川和男氏、アゴラ研究所所長の池田信夫氏でした。
3)原子力規制委員会の見識を疑う ― 民意で安全を決めるのか?
一般投稿で、住友金属工業に勤務していた松永一郎さんに寄稿していただきました。原子力規制委員会が、規制終了後にパブコメを集め、それに基づいて上乗せの政策を検討しようとしていることを批判しています。
今週のリンク
1) 九電「地震想定談合」破る
川内原発の優先審査、決め手は?
日経3月15日記事。九州電力川内原発が、規制委員会によって、優先審査対象になりました。その理由の検証記事ですが、九電がリスクの科学的評価よりも、規制委員会の主張に上乗せしたことで、同委員会に評価されたということのようです。規制委員会の行動には、合理性を感じられません。
日経3月3日記事。英国では、原発周囲、立地候補地でステークホルダーの会合を、政府が入り必ず行うそうです。日本では、反対派の攻撃を怖れ、推進派が消極的でした。冷静な議論の土壌をつくりたいもの。GEPRもそれを目指します。
4) 菅元首相、「原発再稼働」で異例の質問主意書 判断に「誤り」も
3)は衆議院、4)は産経新聞2月21日記事(再掲載)。今回の言論アリーナで言及の資料。
菅直人元首相が国会議員に認められている質問主意書を使い、政府に再稼動の条件について聞いています。規制委員会は、再稼動の審査ではなく、新規制基準の適合性を審査しているにすぎないことを国が認めました。再稼動は法律上今すぐできることになります。
WEDGE Infinity3月12日記事。常葉大学の山本隆三教授の論考。ウクライナ情勢は緊迫しています。しかし、当事者のロシアにEU諸国、トルコは天然ガスを依存。そのためにEU諸国は強硬策に出られないという読みです。これは、国産エネルギーのない日本の将来にも参考になります。

関連記事
-
2020年10月の菅義偉首相(当時)の所信表明演説による「2050年カーボンニュートラル」宣言、ならびに2021年4月の気候サミットにおける「2030年に2013年比46%削減」目標の表明以降、「2030年半減→2050
-
今、世の中で流行っているSDGs(Sustainable Development Goals)を推進する一環として、教育の面からこれをサポートするESD(Education for Sustainable Develop
-
「電力システム改革」とはあまり聞きなれない専門用語のように思われるかもしれません。 これは、電力の完全な自由化に向けて政府とりわけ経済産業省が改革の舵取りをしています。2015年から2020年にかけて3ステップで実施され
-
福島第1原発事故から間もなく1年が経過しようとしています。しかしそれだけの時間が経過しているにもかかわらず、放射能をめぐる不正確な情報が流通し、福島県と東日本での放射性物質に対する健康被害への懸念が今でも社会に根強く残っています。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
日本でも、遺伝子組み換え(GMO)作物が話題になってきた。それ自体は悪いことではないのだが、このブログ記事に典型的にみられるように、ほとんどがGMOと農薬を混同している。これは逆である。GMOは農薬を減らす技術なのだ。
-
これが日本の産業界における気候リーダーたちのご認識です。 太陽光、屋根上に拡大余地…温室ガス削減加速へ、企業グループからの提言 245社が参加する企業グループ、日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)は7月、GH
-
このタイトルが澤昭裕氏の遺稿となった論文「戦略なき脱原発へ漂流する日本の未来を憂う」(Wedge3月号)の書き出しだが、私も同感だ。福島事故の起こったのが民主党政権のもとだったという不運もあるが、経産省も電力会社も、マスコミの流す放射能デマにも反論せず、ひたすら嵐の通り過ぎるのを待っている。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間