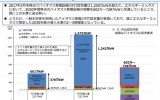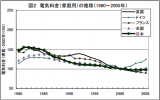中国電力、隠岐営業所27人が見守る設備 — 電力供給を支える現場力
隠岐での困難な電力保守に向き合う
神々の宿る国島根の北東部に位置する島根半島から、約50キロメートル。4つの有人島と約180もの小さな島からなる隠岐諸島は日本海の荒波に浮かんでいる。島後島(隠岐の島町)、中ノ島(海士町)、西ノ島(西ノ島町)、知夫里島(知夫村)の4島合わせて約2万1000人(2013年3月末現在)が生活する隠岐諸島への電力供給を担う、中国電力株式会社の隠岐営業所を訪ねた。
総勢27名の隠岐営業所を率いる月輪所長は、「小さな事故や故障等は、西ノ島に常駐している関係会社の方に対応してもらっているし、台風など予想できる災害に対しては本土から事前に応援要員を配備してもらっているから」と控えめな前置きを置いた上で、「ここでは本当にいろいろな経験ができる。いる人間とあるもので何とかしようとするから、これ以上無いトレーニングになる。所員全員が『隠岐電力株式会社』の経営者マインドを持っている。」と胸を張る。
一帯の電気は、2箇所のディーゼル式内燃力発電所と2箇所の水力発電所、そして県営の風力発電所によって賄われている。島と島は海底ケーブル、あるいは海をまたぐ架空線で連系しているものの、本土からは独立した単独系統であるため、島の設備に何かあればこの島の中で何とかしなければならないのだ。台風や塩害、降雪など常に厳しい自然条件にさらされているため停電も多いのではないかと思っていたが、諸外国はもちろん国内平均と比較しても遜色ない実績であった。
隠岐諸島の主力電源である西郷発電所は、無人運転の発電所で6台のディーゼル式内燃力発電設備を備える。それほど大きくない設備を多くの台数備えているのは、運用効率の向上の点からも、メンテナンスの点からも、そして、いずれかの発電機が故障しても致命傷にはならないというリスク分散の点からもメリットがあるという。
ここでは毎年、夏の需要増大時期を前に、冷却器の清掃を行っている。冷却器は過熱するエンジンを冷却する真水の熱を取り除くために海水を使用しているのであるが、そのパイプの中にはフジツボやムール貝(ムラサキイガイ)といった美味しそうな邪魔者やヘドロがついてしまう。これを放っておくと冷却器のパイプを詰まらせてしまうことになるので、50度程度の温水を通して貝を死滅させ、その後、治具(注・ジグ、工作器具の総称)で突いてすべての不純物を取り除く。
こうした地道な作業をやっておくことで夏の需要増大時期にトラブルが発生することを抑えているのだ。この日現場を案内してくださった出雲電力所の滝山さんは通算7年隠岐島に勤務、斎藤さんも隠岐の島出身で、通算20年間ここで勤務しているベテランだ。
西郷発電所の隅々まで知り尽くしている滝山さん、斎藤さん。

一緒にいらっしゃる時間が長いせいかなんとなく似ているお二人。
技術は使命感と組織力で継承される
翌日は、西ノ島と知夫里島をつなぐ架空配電線の鉄塔の航空障害灯取替え作業を見学させていただいた。高さ26メートルの鉄塔に架設された航空障害灯は1万時間ごとの取り換えを義務付けられているのだという。
現場は地上で見守る2名と昇塔する3名の5名体制。安全確保のため、すべての作業について、事前に大きな声で喚呼。周囲の人間がそれに呼応して復唱する徹底ぶりだ。鉄塔の足元は切り立った断崖で、下を見れば足がすくむことは間違いない。しかし、着実に一歩ずつ、メンバーが息を合わせて昇っていく様は見事だ。入社2年目になったばかりの三谷さんを先輩たちが何くれとなくサポートする姿は、技術継承という言葉では言い表せないものを感じる。

高さ26mの鉄塔の上での作業が続く。

下から見守り的確な指示を出す大原さん。
しかし、年に一度のこの作業の目的は、単に照明の取り替えにとどまらない。こうした作業を平時にやっておくことで、緊急時の作業の訓練にもなると考えているそうだ。月輪所長は「緊急時にどれだけ的確な対応を出来るかが、自分たちの価値」と言い切る。そのためにはこうした平時の訓練に地道に取り組むことはもちろん、地域の皆さんとのコミュニケーションも重要だという。その言葉が実感させてくれたのは、航空障害灯取り替えの現場まで連れて行ってくれたタクシーの運転手さんとの会話だった。
台風、降雪等によって知夫里島で電気設備に事故が発生した場合には、隠岐営業所からチャーター船で駆けつける。しかし車を運ぶことはできないので、島内での移動はタクシーに頼らざるをえない。時には朝3時、4時という時間に叩き起こされることもあるが、「俺達のために来てくれてんだもん」とむしろその復旧作業に関われることが誇らしげですらあった。平時から自分たちでもできることはできるだけやっているそうで、村の有志で支障木の伐採をしたエピソードなどをとくとくと語ってくれた最後に、ポツリと「こんな600人しかいない島、放っとけと思われても仕方ない。交通だっていろんな行政サービスだって効率化していってしまう。その中で中電さんは本当によくしてくれる。おかげでここにまだ住んでいられるんです」と言った。

作業を終えてホッとした表情の5人。
右から小林さん、野田さん、平川さん、三谷さん、大原さん
発送電分離で現場力を維持できるのか
電力システム改革の議論が進んでいる。現在の改革方針の中ではユニバーサルサービスは維持する方針が示されたようだが、自由化されれば本来、こうした社会福祉政策的意義を電力事業者に負わせることはできなくなる。実際隠岐営業所でも,燃料費を含め必要となるコストは電気料金収入を上回っており,市場メカニズムに委ねれば、事業見直しの対象とせざるを得ないだろう。
電気料金審査専門委員会では、遠隔地に住む需要家に多額の送配電コストがかかるというなら、それを料金に転嫁して発電所の近くに移転することを促すことはできないのか、と主張する委員もいたやに聞く。経済学的には正しいのだろうが、この考え方が国民的コンセンサスを得ているとも思えない。電力は国の経済の血液であるからこそ、常により良い事業形態を模索し続けることは当然に必要だ。しかし、「国の経済の血液」という言葉を本当に実感して議論がされているのだろうか?電力の設備が全て地中に埋まって見えなくなっている都会の真ん中で議論せず、たまにはこうした電力供給の現場をみてほしい。隠岐の島では、総勢27名、54の瞳がまっすぐに真面目にその電力設備を見つめ続けている。

(2013年8月5日掲載)

関連記事
-
福島原発事故以来、東京都では3回の都知事選が行われた。脱原発を訴える候補はいたが、都民はそれを争点と重視しなかった。今年2月の選挙で都知事に選ばれたのは「常識人」の舛添要一氏だ。政治に翻弄されがちだった都のエネルギー政策はようやく落ち着きを取り戻した。そしてユニークな再エネ振興、省エネ対策が成果を上げ始めている。選挙の後に報道されない、「日常」の都のエネルギー政策を紹介する。
-
調達価格算定委員会で平成30年度以降の固定価格買取制度(FIT)の見直しに関する議論が始まった。今年は特に輸入材を利用したバイオマス発電に関する制度見直しが主要なテーマとなりそうだ。 議論のはじめにエネルギーミックスにお
-
近代生物学の知見と矛盾するこの基準は、生物学的損傷は蓄積し、修正も保護もされず、どのような量、それが少量であっても放射線被曝は危険である、と仮定する。この考えは冷戦時代からの核による大虐殺の脅威という政治的緊急事態に対応したもので、懐柔政策の一つであって一般市民を安心させるための、科学的に論証可能ないかなる危険とも無関係なものである。国家の安全基準は国際委員会の勧告とその他の更なる審議に基づいている。これらの安全基準の有害な影響は、主にチェルノブイリと福島のいくつかの例で明らかである。
-
2月27日に開催された政府長期エネルギー需給見通し小委員会において、事務局から省エネ見通しの暫定的な試算が示された。そこでは、電力、特に家庭・業務部門について、大幅な需要減少が見込まれている。だがこれは1.7%という高い経済成長想定との整合性がとれておらず、過大な省エネ推計となっている。同委員会では今後この試算を精査するとしているところ、その作業に資するため、改善のあり方について提案する。
-
経済産業省は、電力の全面自由化と発送電分離を行なう方針を示した。これ自体は今に始まったことではなく、1990年代に通産省が電力自由化を始めたときの最終目標だった。2003年の第3次制度改革では卸電力取引市場が創設されるとともに、50kW以上の高圧需要家について小売り自由化が行なわれ、その次のステップとして全面自由化が想定されていた。しかし2008年の第4次制度改革では低圧(小口)の自由化は見送られ、発送電分離にも電気事業連合会が強く抵抗し、立ち消えになってしまった。
-
ロシアの原子力企業のロスアトム社は2016年に放射性ヨウ素125の小線源の商用販売を開始する。男性において最も多いがんの一つである前立腺がんを治療するためのものだ。日本をはじめとした国外輸出での販売拡大も目指すという。
-
経産省・資源エネルギー庁。15年3月公表。水素の普及を進めるロードマップを政府がまとめている。2020年代に家庭用水素燃料電池の普及が視野に入ることを期待している。
-
原油価格は1バレル=50ドル台まで暴落し、半年でほぼ半減した。これによってエネルギー価格が大きく下がることは、原油高・ドル高に加えて原発停止という三重苦に苦しんできた日本経済にとって「神風」ともいうべき幸運である。このチャンスを生かして供給力を増強する必要がある。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間