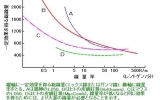放射線をめぐる事実の確認 — 不安をなくす「相場観」を持とう
(編集部より)原子力関係企業の関係者から投稿があった。原子力の推進ではなく、事実関係を述べた提案であり、GEPR編集部の加筆を経て掲載する。GEPRは今後も、中立的立場からエネルギーと原子力をめぐる多様な意見を紹介する。
(以下本文)
放射線リスクの「相場観」を持とう
おそらくGEPR読者の方の多くは、福島第一原発事故による放射線被害はほぼ無いものと理解され、心配もしていないことだろう。しかしながら、社会の一部にまだ心配が残るようだ。事故からもう2年近くになる。さまざまな方が、不安を払拭するための努力を行っている。この原稿でもその試みを行いたい。
必要ない不安を避けるために「放射線を体に受ける量と健康の関係」という視点から、問題を見つめることを勧めたい。造語だが「放射線リスクの相場観」を持つことが必要ではないだろうか。実際に起こる放射能のリスクを把握し、そこから現状を分析するのだ。
年間の放射線被ばく線量について1mSv(ミリシーベルト)という数字が注目されている。まず、この数字の意味について考えてみる。まず確認したいのは、この数字は絶対に守らなければならない被ばく量の上限値ではないということである。
この数値は、各国政府に放射線の防護対策を提言する民間団体のICRP(国際放射線防護委員会)の勧告によるものだ。ICRPは、平時では「公衆の被ばく限度は年間1mSv」、「職業人は年間50mSvかつ5年で100mSv以下(今回のような緊急時は別)」としている。この勧告に基づいて、日本の法律で原子力関連施設の設置・運用にあたって規制値が設けられている。
さらにICRPは「緊急時で被ばくがコントロールできないときには年間20−100mSvの間で、ある程度収まってきたら年間1−20mSvの間で目安を定めて、最終的には平時〔年間1mSv〕に戻すべき」ともしている。
ICRPはこの値を決めるにあたって仮説によりリスクを想定してはいるものの、「自然界の放射線の地域差は大体このくらいの量で、住む場所を選ぶときに自然放射線の量を気にする人もいないだろうから、このくらいなら妥協できるでしょう」という大まかな考え方で決めているとされる。
ICRPは「放射線被ばくは少ない方がよい」という当たり前の立場をとっているが、1mSvの被ばく量は目標にするべきではあっても、それを実現することによる社会コストなどを考えずに、即座に実現するべき数値ではないのだ。(編集部注・この点についてGEPR掲載の中川恵一東京大学准教授の寄稿「放射線被ばく基準の意味」を参照。)
2008年に発表されたICRP勧告111では、放射線防護対策では、「最適化」「正当化」「住民の参加」を行うことを勧告する。最適化とは、被ばくのもたらす健康被害と、それをなくそうとする防護対策の不利益のバランスを取ることだ。「正当化」とは、それによる不利益を、負担者が受け入れることだ。
例えば原子力災害からの防護では、避難、除染、立ち入り禁止などの措置によって地域社会の崩壊、また経済活動の停滞などが起こる可能性がある。これはチェルノブイリ原発事故で生じ、現在の福島でも起こっていることだ。日本政府は勧告に基づく配慮をまったく行っていない。被ばく上限を年1mSvに固執することによる弊害も注目しなければならない。(編集部注・GEPR編集部による「放射線防護の重要文書「ICRP勧告111」の解説」)を参照)
年1mSvの被ばくで健康被害のリスクは極小
次に、年1mSvの被ばく量は科学的に発がんなどのリスクが見出される値ではない。「年1mSvを超えると、即座に人体に危険が及ぶ」という主張している人は信用すべきではないだろう。そもそも、日本人は自然放射線によって、年2・4mSv程度の被ばくを平均でしている。
現在の科学的な知見では短い時間で100mSv以上の放射線を受けた場合に発ガンリスクの増加が見られるとされる。広島・長崎の原爆の被害者の経過観察などから、瞬時の被ばくが100mSvを浴びると、0・5%がんが増えたというデータがある。これは他の発がんリスクと比べても大きなものではない。野菜不足の食生活よりリスクは少ないぐらいで、喫煙習慣よりもさらに小さい。(編集部注・他の発がんリスクと被ばくリスクを比べたアゴラ記事「放射能への対処法」)
しかも福島の原発事故による被ばく量は深刻なものではなかった。福島県の昨年12月発表の県民健康診断の速報値によれば、原発事故で放射性物質が拡散した県北・県中地区では、放射線処理従事者以外の市民の90%以上の方が2mSv未満。原発事故由来の放射能による健康被害は確認されていない。
また人間は自然界に存在する放射性物質を常に摂取している。例えば、バナナ1本にはカリウム40という放射性物質が、約30ベクレル含まれる。人体にもあるカリウム40の放射線量は60キロの成人男性で約4000ベクレルだ。私たちは放射能の中で暮らしている。
こうして比較という視点を絡めた「相場観」を見ると、事故による放射線は、警戒が必要ではあっても、それによる健康不安について過度な不安に陥る必要はないと分かるであろう。
以上の記述は目新しいものではなく、専門家・有識者の共通認識であり、政府が公表したパンフレット「福島県の皆さまへ・健康への影響とこれからの取り組み」にも記載されている。
放射能をめぐる誤解を指摘する
しかしなお、これらへの反論はある。ネット上で散見される主張には次のようなものがあった。
(1)人間は長年天然の放射性物質により被ばくしているので耐性がある。人工の放射線に対しては耐性がない。また内部被ばくは外部被ばくよりも恐ろしい。
(2)ICRPの主張には間違いがある。推進側の団体で、意図的に被ばく線量を小さく見せている。
(3)事故によるものは追加の被ばくであり、本来受けなくても良いもの。許せない。
(1) の主張についての答えは次の通りだ。放射性物質からでる放射能の種類(アルファ線、ガンマ線など)には差はない。特定の放射性物質に対する特別な耐性などはない。また経口摂取による放射性物質は警戒すべきだが、線量が等しければ外部被ばく(体外からの放射線による被ばく)も内部被ばく(放射性物質の摂取による被ばく)も影響は変わらない。また自然のものも、人工のものも、影響は変らない。
(2)の主張は、一種の怪しげな「陰謀論」と言えよう。前述のように、ICRPは科学者の任意団体であり、前身の科学者組織は1924年から活動をしており、現在の名称になったのは1950年だ。設立当時はその際に問題となっていた医療被ばくの被害を防止するための機関であった。原子力利用に伴う被ばくを扱うようになってからも一貫して放射線防護のための機関であり、推進の立場ではない。またICRPの提言は科学のプロセスを経て、現時点での多数説が採用されている。
(3)の主張への答えは、次の通りだ。個人が事故を起こした者を許すか許さないかはその個人の判断によるものであり、このように批判の意見は当然尊重されるべきだ。ただし上述の相場観を前提にして被害がないだろうと分かれば、冷静に議論を行えるのではないだろうか。福島事故の責任追及と、現在起こっている放射能への恐怖がもたらすパニックの沈静化は分けて考えるべきであろう。
ちなみに福島原発事故での直接的な人的被害は、地震・津波被災者の救助の遅れ、病人や老人の避難、あるいは長期の避難のストレスによるものだ。直接的な経済的被害は風評や避難解除の遅れによるものだ。これらは放射線の影響についての正しい「相場観」があれば、ある程度は防ぐことができたはずだろう。
「リスクの相場観」を持ち冷静な議論を
被害は今も進行中だ。それは放射能そのものよりも、それによって起こった出来事によって生じているものだ。これまで述べたような事実を丁寧に伝えるリスクコミュニケーションを、原発事故後に政府は福島や東日本の人々に行うべきであった。しかし不安が残るのは、それに失敗したためと言えよう。
原子力施設の事故では放射線の無用な心配がどうしても絶えない。事業者は事故を二度と起こさないという信念で施設の安全性を高めていくべきだ。一方で国、自治体、事業者、そして国民は「事故は起こるもの、人は間違うもの」との前提で事故への万全の備えをしていく必要がある。備えには過度に恐れることが無いような、放射能の教育も含むべきだろう。
最後に、子供を大切に思う一般人の気持ちを、金儲けや政治に利用する人が今でも散見される、くれぐれも騙されないようにして欲しいものだ。
放射線をめぐって、原発の是非を絡めるのではなく、事実を元にした冷静な議論を行いたい。そのためには、ここで示した「相場観」も、正しい認識に近づく思考のフレームであると思う。事実に基づいて議論と対策をしてこそ、福島の負担は軽減され、復興は早まる。
(2013年1月21日掲載)

関連記事
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク、GEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)日本変革の希望、メタンハイドレートへの夢(上)-青山繁晴氏 2)
-
最近、放射線の生体影響に関する2つの重要なリポートが発表された。一つは、MIT(マサチューセッツ工科大学)の専門家チームが発表した研究成果(「放射能に対する生物学的解析の統合研究?ネズミへの自然放射線比400倍の連続照射でDNAの損傷は検出されず」(英語要旨)「MITニュースの解説記事」)である。
-
元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 今回は、ややマニアックな問題を扱うが、エネルギー統計の基本に関わる重要な問題なので、多くの方々に知っていただきたいため、取り上げる。 きっかけは「省エネ法・換算係数、全電源平均
-
アゴラ研究所の運営するGEPRはサイトを更新しました。
-
気候関係で有名なブログの一つにClimate4youがある。ブログ名の中の4が”for”の掛詞だろうとは推測できる。運営者のオスロ大学名誉教授Ole Humlum氏は、世界の気候データを収集し整理して世に提供し続けている
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPRはサイトを更新しました。
-
金融庁、ESG投信普及の協議会 新NISAの柱に育成 金融庁はESG(環境・社会・企業統治)投資信託やグリーンボンド(環境債)の普及に向けて、運用会社や販売会社、企業、投資家が課題や改善策を話し合う協議会を立ち上げた。
-
「ポスト福島の原子力」。英国原子力公社の名誉会長のバーバラ・ジャッジ氏から、今年6月に日本原子力産業協会の総会で行った講演について、掲載の許可をいただきました。GEPR編集部はジャッジ氏、ならびに同協会に感謝を申し上げます。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間