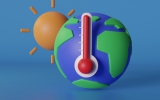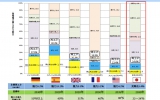今あえて言う、「がんばれ、東電」
(IEEI版)
東電は叩かれてきた。昨年の福島第一原発事故以降、東電は「悪の権化」であるかのように叩かれてきた。旧来のメディアはもちろん、ネット上や地域地域の現場でも、叩かれてきた。
その結果、昨年から今に至るまで、1000人近くの東電社員が社を去った。もちろん、叩かれても仕方がない東電の体質があった。先日公開された原発事故時のテレビ会議の様子を見れば、オペレーターとして原発を運転する組織・人材能力があるのかと疑問に思う人も多いだろう。また、値上げに際しては、「事業者の権利であり、義務でもある」と発言した社長の感覚に、殿様商売的な東電体質に怒りを感じた人が多いことももっともだと思う。
国から資本が注入され、多くの外部取締役が経営の実権を把握した現在、以前の「東電王国」復活はありえない。そんなことを夢想している東電OBや現役プロパーがまだいるとしたら、「あきらめなさい」と言いたい。
しかし、ピンチはチャンスである。東電は、これまで自分たちでさえ経験したことがない立派な会社になることができる。なぜなら、東電パーソンの多くは、電気という経済・生活に必須のインフラ・サービスの供給を守っていきたいと純粋に思っている人たちだからだ。それは、彼ら彼女らの入社以来変わらない思いなのである。その思いを、素直に実際の仕事に結びつけていくことで、信頼は必ず回復できる。
福島第一原発事故以降、現場で文字通り石を投げられても、罵声を浴びせられても、歯を食いしばって電気の供給を絶やさぬように、必要な仕事を黙々とこなしてきた。この人たちには、発送電分離も自由化も、全く異次元の世界での出来事だ。毎日の電気の供給こそが、東電パーソンの矜恃なのだ。
首都を含む関東一円の電力インフラを支える会社、東京電力。東電の再生は極めて困難だが、必ず達成しなければならない重大な課題である。それは東電社員だけではなく、関東で電気を消費している我々すべてにとっての課題である。東電を叩いてばかりいても、何の前進もない。我々みんなが東電再生のステークホルダーなのである。
だからといって、現在の東電を甘やかす必要はない。これまでの自らの欠点を自らが指摘し、改善策を用意し、即実行に移していく。その成果を世に問うことによって初めて、東電は自らを正当に再評価してほしいという資格を得られるということを、東電幹部・社員は忘れないでほしい。
東電が世の中の信頼を回復し、「おっ、ちょっと変わったな」という評価を得るために必要な条件は3つある。
第一に、福島の復興への貢献である。もちろん適切な賠償を進めることは重要な仕事だが、それだけでは足りないし、事務に携わっている現場のモチベーションも上がらない。避難を余儀なくされた地域をどうやって復興するのか、雇用は、インフラ整備は、生活基盤は、教育機会は・・・・一からの町づくりのために、社員が(原子力部隊もそれ以外の部隊も区別なく)一体となってアイデアと実労働を出すことができるかが問われている。
第二に、原発過酷事故を起こした事業者としての責任である。その時まで原発運営に携わっていた人たちが、いまさら自分たちの判断についての合理性を必死で弁護しても、何の意味もない。その人たちが、今後とも日本には原子力が必須のエネルギーだと考えるのであれば、自己弁護ではなく自己反省に時間と労力をかけて、教訓を体系化していくことが重要だ。その体系化された「知」を、自社の後輩たちはもちろん、世界中の事業者に対して、貴重な情報蓄積として伝達していくことが、十字架を負った人たちの使命であり、責任の取り方であるべきなのである。
第三に、創造的な経営ビジョンの立案と実行だ。事故収束や賠償・除染などの仕事があることは当然だ。しかし、今後志のある人が東電に残って、生まれ変わった東電を造りあげたいという意志を持ち続けるためには、前向きな経営ビジョンが必要だ。電力インフラにとどまらず、今後は総合エネルギー企業として、国際的な競争に身を投じるという堅固な決意を、社全体で共有することが重要だ。自由化議論を逆手にとって、ダイナミックな事業展開のロードマップを示すことを期待したい。
もちろん、こうした必要条件を満たしたからといって、すぐに東電に対する信頼が回復するとは限らない。信頼回復の十分条件は何か、あるいは十分条件自体が存在しないのか、そこはいまわからない。わかるはずもない。しかし、やぶれかぶれでいいから、前に歩を進めることが重要なのだ。回ることをやめれば、コマは停止してしまう。
実は私は、東電は最近変わりつつあると見ている。上記の必要条件について、第一の点は、11月7日に公表された東電の「再生への経営方針」で、福島復興本社(仮称)構想が示され、石崎副社長がそのヘッドに任命された。石崎氏は福島第二原子力発電所の所長として赴任したときから同地に惚れこみ、単身赴任期間中ほとんど東京に戻ってこないのみならず、定年退職後は福島に拠点を移そうと震災前に既に家探しを始めていたという。本気度満点の人事である。
第二の点は、原子力改革特別タスクフォースの10月12日の資料を見てもらいたい。ここには、これまでの自社の調査報告書などには見られない率直な反省と改善の方向が示されている。他社が十分参考にすべき内容だと言えよう。
原子力規制委員会が検討している新たな安全基準に加えて、ソフト面でのマネジメントとして他社も取り入れていってもらいたい点が豊富に指摘されている。
第三の経営ビジョンについても、社内カンパニー制の導入を皮切りに、今後自由化や原子力の事業体制に関する国の制度設計が進展するにつれ、さまざまな事業展開のアイデアが出てくる予感はある。
福島第一原発の事故は、被災者の方々や立地自治体に大きなショックと怒りをもたらした。実は、それは東電社員にとっても同じだったのである。その後国有化されるまでの1年間の東電には、ある意味「経営」と言えるものはなく、手足も麻痺していたとしかいいようがない。
しかし、ここに来てようやく、来し方を見つめ、行く末を考える気運が出てきた。
東電内部の改革志向グループは、必ず姿を現わすであろう自社関連の抵抗勢力、ニヒリスティックに論評を加える外部のメディアや「有識者」などは無視して、こうした改革をどんどん進めていってほしい。
私は、こうした方向での改革を支持したい。だから、今あえて言う、「がんばれ、東電」と。
(2012年12月3日掲載)

関連記事
-
経産省・資源エネルギー庁。経産省が2001年からメタンハイドレートの開発研究を、有識者を集めて行っています。現在、「第3フェーズ」と名付けられた商業化の計画が練られています。
-
日本のエネルギーに対する政府による支援策は、原発や再生可能エネルギーの例から分かるように、補助金が多い形です。これはこれまで「ばらまき」に結びついてしまいました。八田氏はこれに疑問を示して、炭素税の有効性を論じています。炭素税はエネルギーの重要な論点である温暖化対策の効果に加え、新しい形の財源として各国で注目されています。
-
電力需給が逼迫している。各地の電力使用率は95%~99%という綱渡りになり、大手電力会社が新電力に卸し売りする日本卸電力取引所(JEPX)のシステム価格は、11日には200円/kWhを超えた。小売料金は20円/kWh前後
-
東日本大震災、福島第一原子力発電所事故から5年間が過ぎた。表向きは停電もなく、日本の国民生活、経済活動は「穏やかに進行中」であるかのように受け止めている国民が多いのではないだろうか。
-
ESGだネットゼロだと企業を脅迫してきた大手金融機関がまた自らの目標を撤回しました。 HSBC delays net-zero emissions target by 20 years HSBCは2030年までに事業全体
-
連日の猛暑で「地球温暖化の影響ですか?」という質問にウンザリしている毎日だ。 最新の衛星観測データを見ると、6月の地球の気温は1991-2020年の30年間の平年値と比べて僅かにプラス0.06℃。0.06℃を体感できる人
-
2015年のノーベル文学賞をベラルーシの作家、シュベトラーナ・アレクシエービッチ氏が受賞した。彼女の作品は大変重厚で素晴らしいものだ。しかし、その代表作の『チェルノブイリの祈り-未来の物語』(岩波書店)は問題もはらむ。文学と政治の対立を、このエッセイで考えたい。
-
現在経済産業省において「再生可能エネルギーの大量導入時代における政策課題に関する研究会」が設置され、再生可能エネルギー政策の大きな見直しの方向性が改めて議論されている。これまでも再三指摘してきたが、我が国においては201
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間