ニコ生アゴラ「2012年の夏、果たして電力は足りるのか!?」報告 ー 解決のカギはスマートグリッド
GEPRを運営するアゴラ研究所はドワンゴ社の提供するニコニコ生放送で「ニコ生アゴラ」という番組を月に1回提供している。6月5日の放送は「2012年の夏、果たして電力は足りるのか!? 原発再稼動問題から最新のスマートグリッド構想まで「節電の夏を乗り切る方法」について徹底検証!!」だった。
元グーグル日本法人社長の村上憲郎氏、国際環境経済研究所所長の澤昭裕氏、環境コンサルタントの竹内純子さんが出演した。司会はGEPRの運営母体であるアゴラ研究所の池田信夫所長が務めた。

6月5日のニコ生アゴラ
電力は関西で足りるのか?
最初のテーマは「電力不足と原発再稼動」。今年の夏は原発の停止によって全国的に電力不足が懸念されている。放送前の5月30日、野田佳彦首相は関西電力大飯発電所3、4号機の再稼動について容認する姿勢を示し、7日には福井県の同意を待って認める考えを示した。

竹内純子さん(環境コンサルタント)
竹内さんは東京電力の元社員。「関西の電力不足は深刻です。政府の電力需給検証委員会によれば、大飯原発が稼動してもピーク時点の需給はほぼ拮抗です。電力会社は不慮の事故や急な気温の変動に備えて、想定される需要に対して供給力の余力、すなわち予備率を8〜10%程度確保しておくものであり、それを考えると今夏は厳しい状況が続きます」と指摘した。
停電が社会に与えるダメージが大きく、また、停電がなかったとしても燃料費の増加は結局コストとして誰かが負担せねばならない。「原発停止による燃料費の増分が1年間で3兆を超えるとの見通しが示されていますが、これは純粋に国外に流出することに注意が必要です」(竹内さん)。
再稼動の方向になったが、元経産省の行政官だった澤氏は「福井県と自治体に判断を投げつけるのではなく、国が原子力を使うことを明確にするべき」と話した。7日の会見で野田首相は「安全性を確保する努力を続け、日本に原発は必要」と明言した。

村上憲郎氏(元グーグル日本法人会長 村上憲郎事務所代表)
村上憲郎氏はグーグル時代から、モノのインターネット(IOT:Internet of Things)と呼ばれるIT技術の生活や道具への応用を提案。大阪府市の特別参与として、エネルギー戦略会議で政策の提言を行っている。(村上氏のGEPRへの寄稿『スマートグリッドが切り開く新生スマートニッポン』)
村上氏は「目先の需給だけではなく、エネルギーシステム全体を考え直すときでしょう。ディマンド・レスポンスを組み入れるべき」と意見を述べた。今までの日本では、主に電力会社である供給(サプライ)側が、需要(ディマンド)に応じて発電と供給をした。電力の使用量は、夏のピークに合わせた山状になっていた。そのピークカット、ピークシフトに対する経済的な仕組みを、ディマンド・レスポンス(Demand Response)と呼ぶが、配慮が乏しかった。
「電力会社は夏の需要に合わせて設備を作っています。一時的な需要に合わせた設備は無駄になり、経済合理性に合いません」(村上氏)。そのために「TOU=Time Of Use」というピークの時点で値段を高くして抑えることや、節電によって生まれた余剰電力を売買する「ネガワット取引所」などの実現が必要と訴えた。村上氏の提案によって、これらはまもなく関西で部分的に実施される見込みだ。
スマートグリッド、「日本発世界標準」も夢ではない
ディマンド・リスポンスを送配電網(グリッド)全体で行うのが「スマートグリッド」という考え方であり、またそれに使う機器が「スマートメーター」だ。
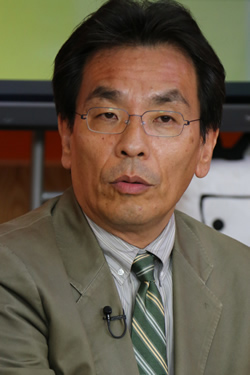
澤昭裕氏(国際環境経済研究所所長)
「技術力のある日本がまず導入すれば、世界標準を作れるかもしれません」(澤氏)。このようにエネルギー業界の関係者は、このスマートグリッド関連で新しい産業が誕生することを期待している。世界各国はこれを実証実験している最中だ。日本では東日本大震災と、その後の電力不足でその活用が検討された。東京電力は政府の意向を受け、スマートメーターを今年度300万台調達する構想を今年4月公表した。この大量導入が定着のチャンスになるかもしれない。
しかし日本のスマートメーターは、電力情報の規格の統一が行われず、エネルギーの使用量などの情報を他の事業者が自由に使うことができない状況だ。東京電力の公表したメーターの仕様にも多くの問題があった。村上氏を中心に民間有識者が「スマートメーター研究会」をつくり、東京電力の仕様に対する反対意見を4月に提出している。(同研究会『東京電力発注のスマートメーター通信機能基本仕様に対する意見書』解説『問題だらけの東電スマートメーター発注―独占延命を図る「トロイの木馬」?−方針転換の意見広がる』)
池田氏は民間有識者を集め、この研究会を発展させて、「IOTコンソーシャム」というNPOを立ち上げる予定を公表した。スマートグリッドとエネルギーシステムの改革、そしてIOTを結びつける活動を行う。「産業のイノベーションにつなげたい」と期待する。(池田氏の解説記事『ソフトバンクのスマートメーター構想』)
村上氏によれば、スマートグリッドは現時点で3方向の利用が検討されている。まず前述の「ディマンド・リスポンス」。次に「見える化」。自分の家庭でどれだけ使っているかがわかり、これは家電製品やHEMS(ホームエナジー・マネジメントシステム)などへ情報を活用する。その中で実際に始まったのは3点目の「見守りサービス」。エネルギーの使用状況を見ることで、高齢者の行動を遠隔地から把握できる。しかし「企業は使い方を考えていても、将来のビジネスのために今は外に出さないでしょう」とも述べた。
「今のスマートグリッド90年代初頭にインターネットが出てきた当時に似ています。スマートグリッドなどで集めたエネルギーの情報は、何に使えるか分からない。逆に何にでも使える可能性がある。エネルギーの変革に日本は一歩前に踏み出ようとしていますが、IOTでさらに一歩前に進めるのではないでしょうか」(村上氏)。
ただし電力会社の戸惑いも理解できると、竹内さんは指摘した。「夢が広がるのはいいことですが、何に使えるか明確に示せないものにどれだけコストをかけるのか、お客様が本当にその「夢」を望んでいるのかもわかりません。高性能のメーターは結局高コストとなり、電気代に上乗せすることが許されるのか、電力会社としては慎重にならざるを得ないでしょう」。
澤氏は経産省時代、インターネットの黎明期に振興政策を担当した。「日本のアプリケーションのアイデアの数が少なく、結局、サービスは米国企業の独壇場になってしまった」。普及ではこうした問題を乗り越えなければならないだろう。
高品質の電気、「電力自由化」でどうする?
次のテーマは「電力自由化」。電力会社の地域独占と発送電の一体事業を見直そうという動きがある。今は産業向けの大口電力への参入はあるものの、家庭などの小口電力は自由化されていない。
「例えば、「原発の電気を使いたくない」と考える人へのサービスや料金メニューはありません。もう少し自由さと工夫があってもよく、ユーザーに不満はあるはずでしょう」と澤氏は現状を指摘した。しかし電力の場合は他の水道や通信を動かす「インフラのインフラ」。澤氏は経産省時代に官僚として自由化を肯定する政策を主張することが多かったが、電力は特に慎重に事を進めなければならないという。「失敗の影響が大きすぎる。この問題は政治的なアジテーションが多く、猪突猛進に進めという進軍ラッパだけでは危ない」。
日本では、停電がほぼなく、そして電圧が一定など高品質な電気の供給が行われている。竹内さんは、東電の支社勤務時代に停電になると、すぐに多くの「おしかりの電話」が来たことを紹介。電力は生活の根幹であり、電力会社には必ず供給しなければならないという安定供給のDNA、『供給本能』とも言える責任感があるという。「それが過剰品質につながったといわれればそうかもしれないが、そうでなければ日本は産業立国が実現できなかったのではないでしょうか」と話した。

池田信夫氏(アゴラ研究所所長)
村上氏は自由化に踏み出す前に、どこまで高い品質の電気の「供給責任」を、維持するべきかの議論が必要と主張した。インターネットでは「自己責任」として、接続でも、コンテンツでも、規制はそれまでの通信システムと異なって少なくなった。
こうした議論に加えて池田氏は、「競争相手の存在が必要」と指摘した。電力は投資がかさむビジネスで参入が難しい。自由化しても参入者が誰もいなければ、電力会社が値上げのし放題になる。「80年代の通信自由化では、政府が第二電電を支援するなど、かなり無理筋のことをやって競争を作り出した。ソフトバンクなど、日本の企業社会の「空気を読めない」会社が、電力ビジネスに入ってきてほしい」と期待した。
電力改革で危機をチャンスに変える
視聴者からの質問もあった。「本当にスマートグリッドは必要なのでしょうか」。澤氏が答えた。「ライフスタイルはなかなか変えられない。目に見えないところでITを使って変えることは役立ちそうです」。澤氏が東大教授であったとき、夏28度、冬18度の冷暖房の温度設定を提案、実施したら、「暑すぎる」など批判が起こり、そろって反対されてしまったという。
最後に村上憲郎氏が話した。「国民がエネルギー問題をここまで考えたことはありません。震災によるエネルギー供給の混乱、原発事故という不幸な出来事がきっかけでした。議論を深め、福島の原発事故、震災で苦しむ方々のためにも、安全で、効率的なエネルギー供給体制をつくることが、私たちの責任ではないでしょうか」。
原発事故以来、エネルギー問題の議論は、原発の先行き、コストなど、今ある問題を解決するための後ろ向きのテーマが多かった。もちろん、今ここにある問題を解決することは、必要だ。しかし、新しい産業を創造する議論があってもいいのではないだろうか。スマートグリッドとIOT、さらに電力自由化によって、イノベーションが始まるかもしれない。「危機がチャンスに変わる」。今回の放送から、そんな期待を抱けた。
(2012年6月11日掲載)

関連記事
-
大変残念なことに、金融庁は2027年度から上場企業へCO2排出量などのサステナビリティ情報開示を義務化する方向で動いています。 サステナビリティ開示、保証基準策定へ議論 金融庁 金融庁は12日、一部上場企業に義務化される
-
事故確率やコスト、そしてCO2削減による気候変動対策まで、今や原発推進の理由は全て無理筋である。無理が通れば道理が引っ込むというものだ。以下にその具体的証拠を挙げる。
-
米国はメディアも民主党と共和党で真っ二つだ。民主党はCNNを信頼してFOXニュースなどを否定するが、共和党は真逆で、CNNは最も信用できないメディアだとする。日本の報道はだいたいCNNなど民主党系メディアの垂れ流しが多い
-
コロナの御蔭で(?)超過死亡という言葉がよく知られるようになった。データを見るとき、ついでに地球温暖化の健康影響についても考えると面白い。温暖化というと、熱中症で死亡率が増えるという話ばかりが喧伝されているが、寒さが和ら
-
はじめに 原子力発電は福一事故から7年経つが再稼働した原子力発電所は7基[注1]だけだ。近日中に再稼働予定の玄海4号機、大飯4号機を加えると9基になり1.3基/年になる。 もう一つ大きな課題は低稼働率だ。日本は年70%と
-
日米原子力協定が自動延長されたが、「プルトニウムを削減する」という日本政府の目標は達成できる見通しが立たない。青森県六ヶ所村の再処理工場で生産されるプルトニウムは年間最大8トン。プルサーマル原子炉で消費できるのは年間5ト
-
世界的なエネルギー価格の暴騰が続いている。特に欧州は大変な状況で、イギリス政府は25兆円、ドイツ政府は28兆円の光熱費高騰対策を打ち出した。 日本でも光熱費高騰対策を強化すると岸田首相の発言があった。 ところで日本の電気
-
ウクライナ戦争の影響を受けて、米国でもエネルギー価格が高騰し、インフレが問題となっている。 ラムスセン・レポート社が発表した世論調査によると、米国の有権者は気候変動よりもエネルギーコストの上昇を懸念していることがわかった
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間
















