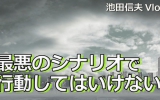日本における発送電分離は機能しているか
(GEPR編集部より)GEPRはNPO法人国際環境経済研究所(IEEI)と提携し、相互にコンテンツを共有します。民間有志による電力改革研究会の発送電分離についてのコラムを提供します。
発送電分離とは
電力自由化は、送電・配電のネットワークを共通インフラとして第三者に開放し、発電・小売部門への新規参入を促す、という形態が一般的な進め方だ。電気の発電・小売事業を行うには、送配電ネットワークの利用が不可欠であるので、規制者は、送配電ネットワークを保有する事業者に「全ての事業者に同条件で送配電ネットワーク利用を可能とすること」を義務付けるとともに、これが貫徹するよう規制を運用することとなる。これがいわゆる発送電分離である。一口に発送電分離と言ってもいくつかの形態があるが、経産省の電力システム改革専門委員会では、以下の4類型に大別している。
| 発送電分離の4類型 | ||
| (1) | 会計分離 | 送電部門に関する会計を分離 |
| (2) | 法的分離 | 送電会社を分離するが、子会社(持ち株方式)でも可 |
| (3) | 機能分離 | ISO※といった中立組織が系統運用を実施 |
| (4) | 所有分離 | 送電部門の資産保有も別会社に分離(資本関係を認めない) |
| ※ISO(Independent System Operator 独立系統運用機関)系統運用機能や託送料金設定、送電線整備計画の策定等を行う。 | ||
(出典)電力システム改革タスクフォース「論点整理」
日本では会計分離+行為規制を採用
このうち、日本では(1)に該当する、送配電部門の会計分離と情報の目的外利用の禁止・差別的取り扱いの禁止といった行為規制を採用している。また電気事業法第93条に基づき指定された電力系統利用協議会(ESCJ)が、送配電ネットワークの設備形成や系統アクセス、系統運用、情報開示等に関するルール策定、これらルールに基づく送配電ネットワーク利用者と電力会社の送配電部門との間の紛争の斡旋・調停などの業務を行っている。
ESCJの運営においては、電力会社、新電力(PPS)、卸電気事業者・自家発設置者、中立者(学識経験者)の各グループが1/4ずつルール策定・改訂の議決権を持ち、苦情処理は中立者だけで構成された監視委員会で審査するなど、中立性・公平性・透明性が配慮されている。また行政は、事前関与を行わないが、ESCJの業務により公益上の問題が生じる場合には、電力会社への直接の規制、ESCJに対する業務改善命令などの事後措置を発動することとしている。
他方、より中立性・公平性・透明性を高める必要があるとして、「(2)法的分離」、「(3)機能分離」、「(4)所有分離」(中立性・公平性・透明性は段々に高まる)を採用すべし」との意見もある。いずれも民間事業者である電力会社の財産権の処分に行政介入することになるため、強制的に導入する場合は「公益の福祉にかなうのか」といった憲法上の問題を生じる。
つまり電力会社の株主が納得して自らそれを受け入れるか、あるいは行政が、現状に著しい問題があり、財産権を制限することでしか解決できないことを証明する必要がある(欧米においても、「(4)所有分離」を行った事業者は、元々国営であったか、自ら売却したかのいずれかである)。
ESCJは機能していないと言われるが
4月25日の第4回電力システム改革専門委員会では、ESCJが機能していない、その原因は、事務局が電力会社の出向者で占められているからだ、権限がないからだ、との意見があった。しかし、前述の通り、中立性・公平性・透明性を配慮した運営ルールがあり、国の事後措置が可能であることを踏まえると、むしろ、各関係者にESCJを使う、あるいは機能させる努力が不足していたように思える。
当日の事務局資料には「送配電部門の中立性に疑義があるとの指摘(事業者の声)」と題して、新規参入者(新電力)から寄せられた事例が8つ記載されている。詳細は経産省HPに掲載された資料をご確認いただきたいが(リンク先は文末に紹介)、記載されているのは疑義だけではなく、既定のルールに対する不満も混在している。
こうした声は、言いっぱなしにするのではなく、中立性に照らして本当に問題があるのかどうか、関係者の間でしっかり深掘りするべきものだ。新電力もESCJの理事会に名前を連ねており、事務局に人も派遣しているのだから、不満・疑問があるのならESCJに相談するなり、ルールの改正を提案すればよい。電力会社も、自らの行為に問題がないと思うならば、今からでもこれらの事例を自らESCJに持ち込み、調査・解明を依頼するべきだ。
加えてエネ庁も、これらの声が寄せられたのであれば、まず必要なのは、ESCJに調査を依頼するなり、自ら調査をして状況を解明することだ。それをすることなく、寄せられた声をそのまま右から左で資料に記載するだけでは、自ら制定したESCJ等の制度を、エネ庁自らスポイルしていると言えないか。上述のとおり、より強力な発送電分離に踏み切るなら、財産権を制限することでしか解決できない問題の所在を行政が証明して、憲法問題をクリアすることが必要だ。今の行政の対応状況が、その証明に耐えるとは考えにくい。
参考文献:
第4回電力システム改革専門委員会(2012年4月25日)参考資料1-2 事務局提出資料(本文で言及している部分は、P18-20)

関連記事
-
需給改善指示実績に見る再生可能エネルギーの価値 ヨーロッパなどでは、再生可能エネルギーの発電が過剰になった時間帯で電力の市場価格がゼロやマイナスになる時間帯が発生しています。 これは市場原理が正常に機能した結果で、電力の
-
前橋地裁判決は国と東電は安全対策を怠った責任があるとしている 2017年3月17日、前橋地裁が福島第一原子力発電所の原発事故に関し、国と東電に責任があることを認めた。 「東電の過失責任」を認めた根拠 地裁判決の決め手にな
-
西浦モデルの想定にもとづいた緊急事態宣言はほとんど効果がなかったが、その経済的コストは膨大だった、というと「ワーストケース・シナリオとしては42万人死ぬ西浦モデルは必要だった」という人が多い。特に医師が、そういう反論をし
-
以前にも書いたことであるが、科学・技術が大きく進歩した現代社会の中で、特に科学・技術が強く関与する政策に意見を述べることは、簡単でない。その分野の基本的な知識が要るだけでなく、最新の情報を仕入れる「知識のアップデート」も
-
昨年の福島第一原子力発電所における放射性物質の流出を機に、さまざまなメディアで放射性物質に関する情報が飛び交っている。また、いわゆる専門家と呼ばれる人々が、テレビや新聞、あるいは自らのブログなどを通じて、科学的な情報や、それに基づいた意見を発信している。
-
小泉・細川“原発愉快犯”のせいで東京都知事選は、世間の関心を高めた。マスコミにとって重要だったのはいかに公平に広く情報を提供するかだが、はっきりしたのは脱原発新聞の視野の狭さと思考の浅薄さ。都知事選だというのに脱原発に集中した。こんなマスコミで日本の将来は大丈夫かという不安が見えた。佐伯啓思・京大教授は1月27日付産経新聞朝刊のコラムで「原発問題争点にならず」と題して次のように書いた。
-
米国ブレークスルー研究所の報告書「太陽帝国の罪(Sins of a solar empire)」に衝撃的な数字が出ている。カリフォルニアで設置される太陽光パネルは、石炭火力が発電の主力の中国で製造しているので、10年使わ
-
放射線の線量データが公表されるようになったことは良いことだが、ほとんどの場合、その日の線量しか表示しない。データの価値が半減している。本来、データは2つの意味を持っている。一つはその日の放射線量がどうなのかということ。2
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間