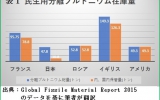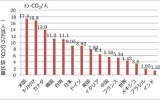今週のアップデート — 日本の全原発停止、再稼動は可能か(2012年5月7日)
国内の原発54基のうち、唯一稼働している北海道電力泊原発3号機が5月5日深夜に発電を停止し、日本は42年ぶりに稼動原発ゼロの状態になりました。これは原発の再稼動が困難になっているためです。
原発の稼動は電力会社の申請により経済産業大臣が認可すれば可能です。しかし福島原発事故後に不安が広がって、原発立地場所の自治体が稼動に反対しています。また昨年に菅直人前首相が、再稼動にあたってストレステストというより厳しい審査を、政治指導によって義務づけました。一連の法律に基づかない行為が無計画に行われたために、再稼動が困難になっています。
夏は電力需要が増える時期であり、原発の停止によって全国的に需給が厳しくなります。特に、関西、九州、北海道では電力が不足することが見込まれます。さらに5月3日に枝野幸男経産大臣は、関電管内の計画停電の実施に言及しました。電力不足の切迫感が一段と強まり、議論が活発になるでしょう。この出来事に関連した情報をGEPRは今週集めました。
1)現在は再稼動について多数派が望み、政府が要請しているにも関わらず、なかなか実現しません。地方自治体の反対意見、さらに関西圏では自治体首長の反対が根強いためです。福島原発事故によって住民が不安を抱くのは当然であり、問題の解決の道筋がなかなか見えません。
問題を考える材料にするため、元経産省のキャリア官僚で、エネルギー政策の運営、また法改正に関わった、政策家の石川和男氏にインタビューを行いました。バランスの取れた冷静な解説で、役所の論理の解説や現実的な解決策が示されています。問題を深く考える人にとって、必読の意見であると思います。
「原発再稼動、対話不足ミスの修正を=安定供給を全国民が考えるとき−政策家・石川和男氏に聞く(上)」(英語版)
「容易ではないピークシフトの実現、再生可能エネの拡充=元経産官僚の語るエネルギー政策最前線−政策家・石川和男氏に聞く(下)」(英語版)
2)放射能について正確な情報がない場合に誰もが不安を抱きます。GEPRは正確な情報の提供を心がけてきました。しかし正確な情報を示しても、人々がそれを信じて活用しなければ、不安を解消することはできません。また過剰な心配は、原発とエネルギーについての、冷静な議論を妨げます。こうした人々にどのように向き合えばよいのでしょうか。
自営業で主婦の白井由佳さんは放射能による不安でパニックに陥りました。その体験を語っていただきました。「放射能パニックからの生還=ある主婦の体験から−自らの差別意識に気づいたことが覚醒の契機に」
3)NPO法人の国際環境経済研究所(IEEI)と、GEPRはコンテンツの共有で提携しています。澤昭裕IEEI所長の寄稿から、民間有志の電力改革研究会の記事「再稼働に向けて−政府と原子力コミュニティの宿題」を提供いただきました。福島原発事故の後で、官民の原子力コミュニティを続けています。澤氏は「こうした宿題に真剣に取り組むかどうかを、反原発派でなくとも、普通の国民はしっかりと見ているということを忘れないでもらいたい」と指摘しています。
今週のリンク・ニュース
1)米紙ワシントンポスト社は社説「原子力をとめる意味」を4月22日に掲載しました。GEPRは日本語訳を提供します。原発の停止により、化石燃料の使用増加で日本の温室効果ガスの削減とエネルギーコストの増加が起こっていることを指摘。再生可能エネルギーの急増の可能性も少なくエネルギー源として「原子力の維持を排除すべきではない」と主張しています。
2)原発の再稼動について、日本の新聞の論調は分かれています。
読売新聞は5月5日、「全原発停止 これでは夏の電力が不足する」、日本経済新聞「「原発ゼロ」解消し電力不安を除け」、産経新聞は5月6日「「原発ゼロ」 異常事態から即時脱却を 安全技術の継承は生命線だ」と社説を発表し、早期の再稼動を訴えました。
一方で、毎日新聞は「エネルギー、原発「出口」戦略を練ろう」と、全原発停止を段階的な脱却の契機にすることを訴えています。一方で朝日新聞は「「原発ゼロ」社会:上 不信の根を見直せ」「下:市民の熟議で信頼回復を」と議論の深化を強調しました。
朝日新聞などの意見は不思議です。今の原発停止は、夏に向けた需給逼迫と、エネルギー負担の増加という「今そこにある危機」をもたらしています。短期の問題を解決することと、長期的な原発脱却の議論は分けられる話です。眼前の危機をどうするか、現実的な議論が望まれます。
3)ウォールストリートジャーナルに日本版コラム「太陽光買取42円は高過ぎる―相次ぐ電池メーカー破綻が示す環境激変」。東京工科大学の尾崎弘之教授が国際比較の中で、買い取り価格の高額さに疑問を示しています。
再生可能エネルギーの強制買取制度について、議論が広がっていますが、専門家はそろって効果について、懐疑的な意見を述べています。
今週のリンク
1)経済産業省「需給見通し及び原発停止による燃料費の増加について」
経産省による4月26日時点の情報が公開されています。過去5年平均の夏のピークと比べると、今年8月の関西電力管内の供給は需要に比べて16%不足。さらに原発の停止によって2012年度は燃料費は全電力会社で3.1兆円増加する見込みです。
2)大阪府市統合本部エネルギー戦略会議ウェブサイト
大阪府が行っているエネルギー戦略会議の議論が公開されています。議論の内容を見ると、原発の再稼動、また原発の是非に偏在しています。さらに、関電の経営、また国の原発政策への注文など、法的根拠、地方自治の枠を超えた議論が行われています。これが関西電力の原発の再稼動が困難になる理由になっています。

関連記事
-
難破寸前政権 大丈夫かあ? 政権発足前夜、早くもボロのオンパレード・・・ 自民党総裁就任から、石破の言動への評価は日をおうごとに厳しさを増している。 思いつき、認識不足、豹変、言行不一致、有限不実行、はては女性蔑視——昭
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーの「バーチャルシンクタンク」であるグローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)はサイトを更新しました。
-
GEPRフェロー 諸葛宗男 今、本州最北端の青森県六ケ所村に分離プルトニウム[注1] が3.6トン貯蔵されている。日本全体の約3分の1だ。再処理工場が稼働すれば分離プルトニウムが毎年約8トン生産される。それらは一体どのよ
-
昨年の震災を機に、発電コストに関する議論が喧(かまびす)しい。昨年12月、内閣府エネルギー・環境会議のコスト等検証委員会が、原子力発電の発電原価を見直したことは既に紹介済み(記事)であるが、ここで重要なのは、全ての電源について「発電に伴い発生するコスト」を公平に評価して、同一テーブル上で比較することである。
-
6月1日、ドイツでは、たったの9ユーロ(1ユーロ130円換算で1200円弱)で、1ヶ月間、全国どこでも鉄道乗り放題という前代未聞のキャンペーンが始まった! 特急や急行以外の鉄道と、バス、市電、何でもOK。キャンペーンの期
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
今回は英国の世論調査の紹介。ウクライナ戦争の煽りで、光熱費が暴騰している英国で、成人を対象にアンケートを行った。 英国ではボリス・ジョンソン政権が2050年までにCO2を実質ゼロにするという脱炭素政策(英国ではネット・ゼ
-
はじめに述べたようにいま、ポスト京都議定書の地球温暖化対策についての国際協議が迷走している。その中で日本の国内世論は京都議定書の制定に積極的に関わった日本の責任として、何としてでも、今後のCO2 排出枠組み国際協議の場で積極的な役割を果たすべきだと訴える。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間