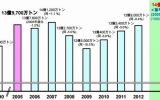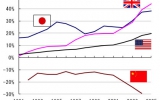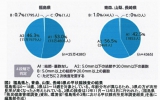放射線の健康影響 ― 重要な論文のリサーチ
【要旨】放射線の健康影響に関して、学術的かつ定量的に分析評価を行なっている学術論文をレビューした。人体への影響評価に直結する「疫学アプローチ」で世界的にも最も権威のあるデータ源は、広島・長崎の原爆被爆者調査(LSS)である。その実施主体の放射線影響研究所(RERF:広島市)は全線量域で発がんリスクが線量に比例する「直線しきい値なし(LNT)仮説」に基づくモデルをあてはめ、その解析結果が国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告に反映されている。しかしLNT仮説は低い線量域(おおむね100mSv以下)では生物学的に根拠がない(リスクはもっと小さい)とする「生物アプローチ」に基づく研究が近年広くなされている。
放射線をめぐる基本知識
放射線は元来自然界に存在するものであったが人類がその存在を認識したのは100年ほど前にすぎない。1895年にレントゲン博士がX線を発見し、3年後にマリー・キュリーが放射線を出す性質を「放射能」と名付けた。そして放射線を人間に役立つように活用する研究が始まった。
一方、この放射線の研究と放射線利用の実用化の歴史は、放射線障害の歴史でもある。1896年1月には、真空管の製作に従事していた技術者の手にX線被曝による皮膚炎が発生し、1902年にはX線照射により皮膚がんの発生することが判明しているそして、1945年8月の広島・長崎への原爆投下は、人類史上初めて一般公衆に大規模な放射線被曝をもたらした[1]。
放射線の健康影響に関する研究をレビューするにあたり、以下は知っておくべき基本的な知識である。
(1) 放射線は自然界すなわち宇宙そして地球上にも存在し、その「自然放射線」に適応できるように生物そして人類は進化してきた。自然に地上にいて受ける放射線をバックグラウンド放射線というが、その世界平均(内部被ばくを含む)は年間2.4mSvである。
(2) 放射線の線量というのは、瞬間に浴びる量と、ある一定期間に浴びる総量をちゃんと区別して把握する必要がある。前者を「線量率」といい、「mSv/h」などの単位で表される。後者を「線量」といい、「mSv」などの単位で表される。数学的に表現すれば、線量率関数をある時間区間で積分したものが線量である。これは、自動車の瞬間速度をある時間区間で積分したものが走行距離であることと同じである。
(3) 放射線に関連する単位には、シーベルト、ベクレル、グレイなどいろいろある。その中で「シーベルト(Sv)」という単位は、人間などの臓器への影響の大きさの観点での比較をするための線量の単位である。そのため、シーベルト単位で同じ線量であれば、その放射線源がラドン温泉であろうが、上空の放射線であろうが、X線検査装置であろうが、原子力発電所であろうが比較可能である。
(4) 放射線の人体への影響には「確定的影響」と「確率的影響」がある。確定的影響とは、人間がある線量(しきい値)以上に高い放射線を浴びると、 脱毛・不妊・白内障などを発症するものである。このしきい値は1000mSv程度の非常に高い線量であり、今回の福島事故でこのような高い線量を浴びた民間の人はまったくいない。したがってここではサーベイの対象とはしない。
「確率的影響」は、放射線を浴びることにより、後々にがんなどの疾患にかかりやすくなるが、すべての人ががんになるのではなく、がんになる可能性が高まるというものである。ご承知のようにがんになる要因としては放射線だけではなく、喫煙、飲酒、不規則な食生活、その他さまざまなものがある。これが、低線量の放射線の人体への影響を評価する上で非常にやっかいな点である。
(5) 放射線の健康影響に関する研究は、「疫学アプローチ」と「生物学アプローチ」に大別される。人間に放射線を当てる実験をすることはできないので、放射線の人体への影響の評価は、起こってしまった放射線被ばくについて、各人の被ばく線量と、その人がいつどのような病気にかかったか、そしていつどのような病気で亡くなったか、を長期間にわたって追跡調査することにより得られるデータを解析する。これが疫学アプローチである。
一方、生物学アプローチでは、マウスなど実験用動物に放射線を当ててさまざまな影響を観察する「インビボ」研究と、試験管内の細胞に放射線を当ててその変化を観察する「インビトロ」研究に大別される。生物学的なメカニズムについて仮説を立て、それを検証することができるが、それがそのまま人間に当てはまるかどうかは別途検討が必要である。また倫理的な理由から実験用動物を用いた研究を禁止している国もある。
LNT仮説「放射能は浴びるほど健康被害になる」との考えは実証されず
さて放射線の健康影響(確率的影響)において、大多数の人が暗黙の前提としているのが、「放射線はたとえ僅かな線量であっても有害であり、がんにかかりやすくなる度合いは、浴びた放射線量に比例して高くなる」というものである。これは「しきい値なし直線仮説(Linear No Thresholdの頭文字をとってLNT仮説という)」と呼ばれる。
LNT仮説の起源は、1930年の遺伝学者マラー博士のショウジョウバエの研究結果(ショウジョウバエに放射線を当てると子孫に突然変異が起こる度合いが増加し、その度合は当てた放射線量に比例する)である。この研究結果自体の後世へのインパクトはあまり大きくないが、広島・長崎の原爆被爆者の追跡調査(LSS)データに対して日米共同研究機関である放射線影響研究所(RERF)がLNT仮説に基づいて、発がんリスクが浴びた放射線量に比例するモデルをあてはめたこと(他のモデルも当てはめたがこの直線モデルが最も適切であるとした)がそれ以降に非常に大きなインパクトをもたらした。
現時点でICRP(国際放射線防護委員会)勧告等の根拠となっているRERFの最新の研究成果は「原爆被爆者の死亡率調査 第13報 固形がんおよびがん以外の疾患による死亡率:1950-1997年」である[2]。ここで、「チェルノブイリ原子力発電所事故から20年-人体影響はどこまで解明されたか-」[3]で指摘しているように、「原爆被爆者の死亡率調査 第13報」[2]においても、50mSv未満の被ばくでは固形がん死亡の有意な増加が認められないことを記述していることに注意する必要がある。
原爆、チェルノブイリ、原発作業者の調査結果
さまざまな放射線被ばくの中でも、広島・長崎の原爆被爆は、浴びた放射線量は爆発時にいた場所や遮蔽物などの自己申告の結果なのでやや正確性に欠ける印象を持ちがちだが、線量はモデル家屋・人体を用いたコンピュータシミュレーションと残留放射線量との照合でかなり信頼のおけるものとなっている。また被爆者手帳を持っている人は医療上優遇されるので、その人がいつどのような病気にかかったか、いつどのような病気で亡くなったかの追跡調査は正確になされており、対象者は約12万人に及ぶ。
そのため、このLSSデータ及びRERFによる解析結果は、放射線の人体への影響を評価した調査研究では世界で最も権威あるものとされており、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告もこのLSSの解析結果を最大の拠り所としている。尚、このLSSデータはRERFのサイトにおいて公開されている。
原爆被爆者調査以外では、原子力発電所作業従事者の健康影響調査は、日本[4]をはじめ世界各国で広範囲に行われている。世界のこの種の調査を統合した分析もなされている[5] 。おおむね、作業従事者に有意な健康影響はみられず、むしろ対照群と比べてリスクが低くなる場合もある。これはいわゆるHealthy Worker Effect(発電所作業従事者には頑丈な人が多いので病気にも罹りにくい)である。
また原子力発電所事故による広域な放射線影響として1986年のチェルノブイリ発電所事故があるが、この事故による放射線影響の定量的・客観的評価は「チェルノブイリ原子力発電所事故から20年-人体影響はどこまで解明されたか-」[3] に記述されている。それによれば、チェルノブイリ周辺ではこれまで、(当局の過失による)小児期のミルク摂取による甲状腺がん(筆者注:発症者のうち死者約0.2%)のリスクが高くなったが、民間人で白血病の増加は認められず、最大の健康影響は精神的影響であるとしている。
LNT仮説は正しいのか ― 結論は出ていないが肯定は減少傾向
ところで、LNT仮説の起源であるマラーの研究は、修復機能のない細胞においてのみ成立する非常に特殊なケースであることが現在では明らかになっている。生物学的にLNTを否定する結果を報告している論文は種々ある[6]。
LNTに生物学的根拠がないのであれば単なる「仮説」である。少なくとも疫学データを拠り所とするならば、100mSv以下の低線量域では有意なリスクの増加が認められないケースがほとんど大多数である。低線量の放射線を浴びても「有意なリスクの増加が認められない 」ということは、放射線の影響の大きさは、それを解析する際に「誤差項」と仮定する他の発がん要因(喫煙・食事・生活習慣等)に埋もれてしまう程度の大きさでしかないということだ。アカデミックの世界では普通「統計的に有意」な結果しか論文にならないので、結果的に「影響あり」という主張だけが目立ってしまう。放射線影響の疫学研究は、他の要因をコントロールすることができないので、LSS(被爆者追跡調査)のようなサンプル数の多いデータでも「低線量域ではリスクの増加は有意でない」ということしか言えない。これはある意味で疫学の限界である。
低線量域(おおむね100mSv以下)におけるLNT仮説の妥当性に関する論争は、最近では2007~2008年に、放射線科学で最も権威のある学術誌Radiation Research上で繰り広げられた。米国科学アカデミーで2007年に発表したBEIRⅦ報告書[7] が基本的に低線量域でもLNT仮説を支持したのに対して、Tubiana他[8]が「生物学的に根拠が無い」と反論。Brenner他[9] が「安易に結論は出せない」とBEIRⅦを擁護。それに対して参考文献の[10]~[13] と次々にLNT批判のコメントが掲載された。ちなみに、医学関連の有名な文献検索サイトPubMedで"low+dose+lnt"で検索すると、最近の論文は「LNTはリスクを過大評価している」という論に立つものは多いが、LNTを擁護する論文は見かけない。
Tubiana他[14] は、これまでの疫学及び生物学アプローチをレビューし、LNT仮説が非現実的であることを指摘している。ICRPも、LNTが普遍の真理であるなどとは言っておらず、「放射線防護」というアクションにのみ用いられるべきであるとしている。
参考文献の[14]や他の多くの文献で述べられているように、同じ線量を浴びる場合でも、より低い線量率でゆっくり浴びた方が発がんリスクは小さくなる。これは放射線の専門家の間では常識となっており、ICRP勧告でも線量率効果係数(DDREF)として”2″という数値を採用している(ゆっくり浴びるとリスクが1/2になるという意味)。しかし、現在の疫学研究結果はほとんどが短期の被ばくなので、この線量率効果の定量的評価については現在も種々の研究や議論がなされている。
尚、本記事で参照した文献はすべて福島事故以前に書かれたものである。
主要参考文献一覧:
[1] 柴田義貞「放射線の人体影響:原爆被爆とチェルノブイリ事故」学校保健研究, Vol.42, 2000年
[2] Preston DL, Shimizu, Y, Pierce DA, Suyama A Mabuchi, K: Studies of mortality of atomic bomb survivors. Report 13 solid cancer and noncancer disease mortality 1950-1997. Radiation Research 160: 381-407, 2003(邦題:「原爆被爆者の死亡率調査 第13報 固形がんおよびがん以外の疾患による死亡率:1950-1997年」、邦訳あり)
[3] 柴田義貞「チェルノブイリ原子力発電所事故から20年-人体影響はどこまで解明されたか-」長崎医学会雑誌, 81巻, 2006年
[4] 放射線影響協会「原子力発電施設等放射線業務従事者等に係る疫学的調査(第Ⅳ期調査 平成17年度~平成21年度) 」
[5] Cardis E, Vrijheid M, Blettner M, et al: The 15-Country Collaborative Study of Cancer Risk among Radiation Workers in the Nuclear Industry: estimates of radiation-related cancer risks. Radiation Research,167(4), 2000
[6] Koana T, Okada O, Ogura K, Tsujimura H, Sakai K: Reduction of Background Mutation by Low Dose X Irradiation of Drosophila Spermatocytes at a Low Dose Rate. Radiation Research 167: 217-221, 2007
[7] National Research Council: Committee to Assess Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation. Health risks from low levels of ionizing radiation: BEIR VII, Phase 2. Washington, DC: The National Academies Press, 2006.
[8] M. Tubiana, A. Arengo, D. Averbeck, and R. Masse: Low-Dose Risk Assessment. Radiation Research 167, 742-744 (2007)
[9] David J. Brenner,a Tom K. Heia and Ohtsura Niwa: Low-Dose Risk Assessment: We Still Have Much to Learn. Radiation Research 167, 744 (2007)
[10] K. L. Mossman: Economic and Policy Considerations Drive the LNT Debate. Radiation Research 169, 245 (2008)
[11] Bobby E. Leonard: Common Sense about the Linear No-Threshold Controversy-Give the General Public a Break. Radiation Research 169, 245 -246 (2008)
[12] M. Tubiana, A. Aurengo, D. Averbeck, and R. Masse: Low-Dose Risk Assessment: The Debate Continues. Radiation Research 169, 246 -247 (2008)
[13] Ludwig E. Feinendegen, Herwig Paretzke, and Ronald D. Neumann: Two Principal Considerations are Needed after Low Doses of Ionizing Radiation. Radiation Research 169, 247 -248 (2008)
[14] M. Tubiana, L. E. Feinendegen, C. Yang, J. M. Kaminski: The Linear No-Threshold Relationship Is Inconsistentwith RadiationBiologic and Experimental Data. Radiology, Volume 251, Number 1.2009

関連記事
-
本レポートには重要な情報がグラフで示されている。太陽光・風力の設備量(kW)がその国の平均需要量(kW)の1.5倍近くまで増えても、バックアップ電源は従来通り必要であり、在来型電源は太陽光・風力に代替されることもなく、従来通りに残っていることである。
-
5月21日、大飯原発運転差し止め請求に対し福井地裁から原告請求認容の判決が言い渡さ れた。この判決には多くの問題がある。
-
4月4日のGEPRに「もんじゅ再稼働、安全性の検証が必要」という記事が掲載されている。ナトリウム冷却炉の危険性が強調されている。筆者は機械技術屋であり、ナトリウム冷却炉の安全性についての考え方について筆者の主張を述べてみる。
-
福島県で被災した北村俊郎氏は、関係者向けに被災地をめぐる問題をエッセイにしている。そのうち3月に公開された「東電宝くじ」「放射能より生活ごみ」の二編を紹介する。補償と除染の問題を現地の人の声から考えたい。現在の被災者対策は、意義あるものになっているのだろうか。以下本文。
-
東京大学准教授、中川恵一氏のご厚意により、中川氏の著書『放射線医が語る被ばくと発がんの真実』(ベストセラーズ)に掲載されたロシア政府のチェルノブイリ原発事故の報告書を掲載する。原典はロシア科学アカデミー原子力エネルギー安全発展問題研究所ホームページ(ロシア語)。翻訳者は原口房枝氏。
-
政府は2030年までに温室効果ガスを2013年比で26%削減するという目標を決め、安倍首相は6月のG7サミットでこれを発表する予定だが、およそ実現可能とは思われない。結果的には、排出権の購入で莫大な国民負担をもたらした京都議定書の失敗を繰り返すおそれが強い。
-
中国の環境汚染が著しい。空気、水、温室効果ガスの排出などの点で、急速な工業化と緩い規制によって環境破壊が広がる。しかし正確な情報は国内外に伝えられず、都市部を中心に中国国民の健康被害が伝えられ、政情不安の一因になっているとされる。東シナ海の汚染、PM2・5(微小粒子状物質)などによる大気汚染、酸性雨による日本への影響が懸念されている。温室効果ガスについては、中国は2010年には米国を抜き、世界最大の温室効果ガス排出国になった。中国は全世界のCO2のうち、約25%(日本は約6%)を排出している。
-
テレビ朝日系列の「報道ステーション」という情報番組が、東日本大震災と福島原発事故から3年となる今年3月11日に「甲状腺がんが原発事故によって広がっている可能性がある」という内容の番組を放送した。事実をゆがめており、人々の不安を煽るひどいものであった。日本全体が慰霊の念を抱く日に合わせて社会を混乱させる情報をばらまく、この番組関係者の思考を一日本人として私は理解できない。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間