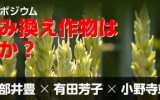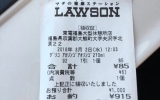チェルノブイリ事故についての放射線の影響評価(要旨の日本語訳)
概要
 ©UNSCER1986年4月26日に発生したチェルノブイリ原子力発電所原子炉の事故は、原子力発電産業においてこれまで起きた中でもっとも深刻な事故であった。原子炉は事故により破壊され、大気中に相当量の放射性物質が放出された。事故によって数週間のうちに、30名の作業員が死亡し、100人以上が放射線傷害による被害を受けた。事故を受けて当時のソ連政府は、1986年に原子炉近辺地域に住むおよそ11万5000人を、1986年以降にはベラルーシ、ロシア連邦、ウクライナの国民およそ22万人を避難させ、その後に移住させた。この事故は、人々の生活に深刻な社会的心理的混乱を与え、当該地域全体に非常に大きな経済的損失を与えた事故であった。上にあげた3カ国の広い範囲が放射性物質により汚染され、チェルノブイリから放出された放射性核種は北半球全ての国で観測された。
©UNSCER1986年4月26日に発生したチェルノブイリ原子力発電所原子炉の事故は、原子力発電産業においてこれまで起きた中でもっとも深刻な事故であった。原子炉は事故により破壊され、大気中に相当量の放射性物質が放出された。事故によって数週間のうちに、30名の作業員が死亡し、100人以上が放射線傷害による被害を受けた。事故を受けて当時のソ連政府は、1986年に原子炉近辺地域に住むおよそ11万5000人を、1986年以降にはベラルーシ、ロシア連邦、ウクライナの国民およそ22万人を避難させ、その後に移住させた。この事故は、人々の生活に深刻な社会的心理的混乱を与え、当該地域全体に非常に大きな経済的損失を与えた事故であった。上にあげた3カ国の広い範囲が放射性物質により汚染され、チェルノブイリから放出された放射性核種は北半球全ての国で観測された。
ベラルーシ、ロシア連邦、ウクライナの住民の間では、2005年までに、事故当時被曝した、6000を超える小児および思春期の子供たちの甲状腺がんの症例が報告された。今後10年の間に、さらに症例数が増えることが予想される。検査体制が強化されていたにも関わらず、そういったがんの大部分は、おそらく事故直後の放射線被曝が原因であった可能性が最も高いだろう。この増加傾向とは別に、事故から20年を経ても放射線被曝を起因とする公衆衛生上の大きな影響があったという証拠はない。全般的ながんの発生率あるいは死亡率、または放射線被曝と関連があるかもしれない非悪性疾患の増加に対する科学的証拠は存在しないのだ。一般住民の白血病発生率は、固形がんと比べて被曝から症状が表れるまでの時間が短いと予想されるために大きな懸念材料のひとつとなっているが、上昇している傾向は見受けられない。最も高い線量に被曝した人はそれぞれ放射線にまつわるリスクが増大する可能性が高いが、大半の住民はチェルノブイリ事故による放射線による深刻な健康上の影響を受けることはなさそうである。放射線被曝とは関係のない、他の健康上の問題が人々の間には多数あるということが知られている。
放射性核種の放出
チェルノブイリ核原子炉の事故は、電気制御システムの実験が行われている際に、原子炉が定期点検のため停止されつつある状態の時に起きた。作業員が安全規定を守らず、重要な制御システムの電源を切り、もともと設計に欠陥があった原子炉が不安定かつ低電力な状態に陥ってしまった。電圧が急上昇したため原子炉容器が破裂するような水蒸気爆発が起こり、さらに激しく燃料と蒸気が反応し、原始炉心が破損、原子炉建屋は激しい損傷を受けた。その後に黒鉛が10日間激しく燃え続けた。このような状況下で大量の放射性物質は放出されたのである。
 Contamination maps ©UNSCER事故により放出された放射線を含むガスや粉塵は、はじめ西および北の方角に風によって運ばれた。その後の日々、風はあらゆる方向から吹いた。放射性核種の降下は、主に放射能雲通過の際によるものであり、それは事故の影響のあった地域全体、そして、程度は低いものの、残りのヨーロッパ全土にも複雑かつ多岐にわたる被曝のパターンをもたらした。
Contamination maps ©UNSCER事故により放出された放射線を含むガスや粉塵は、はじめ西および北の方角に風によって運ばれた。その後の日々、風はあらゆる方向から吹いた。放射性核種の降下は、主に放射能雲通過の際によるものであり、それは事故の影響のあった地域全体、そして、程度は低いものの、残りのヨーロッパ全土にも複雑かつ多岐にわたる被曝のパターンをもたらした。
人の被曝
人々が被曝する原因となった原子炉から放出された放射性核種は、主にヨウ素131、セシウム134、セシウム137であった。ヨウ素131は放射能半減期が短いが(8日間)、空気や汚染されたミルク、葉野菜を摂取することで、比較的急速に人体に取り込まれる。ヨウ素は甲状腺に局所的に蓄積されてしまう。乳幼児の甲状腺の大きさや代謝作用の他に、乳幼児が母乳、牛乳および乳製品を摂取することも関連があるが、通常、乳幼児の放射線の被曝線量は大人のそれよりも高い。
セシウムの同位元素は放射能半減期が比較的長い(セシウム134は2年間、セシウム137は30年間)。これらの放射性核種はその摂取経路、および地表の堆積物からの外部被曝によって、より長い期間被曝する原因となる。数多くの他の放射性核種がこの事故によって関係している。これも公開されたさまざまな評価の中で、影響が検討されている。
事故の影響を最も受けた人々の平均実効線量は、復旧活動に携わった53万人の作業員では約120mSv、11万5000人の避難民では約30mSV、そして事故直後から20年間汚染地域に住み続けた人々では約9mSvだと評価された。(ちなみに、CTスキャンを1回受けると通常9mSv被曝する)。個々人の被曝の最大値は、それ以上の可能性もある。ベラルーシ、ロシア連邦、ウクライナ以外のヨーロッパ諸国も事故の影響を受けた。当該ヨーロッパ各国の平均被曝線量は事故後最初の1年で1mSv未満であったが、その後、年ごとに著しく減少していった。ヨーロッパの中でも距離が離れたところに位置する国々での、この事故における生涯にわたる平均被曝線量はおよそ1mSvであろうと推測される。この被曝線量は、自然由来の放射線量から1年間に受ける被曝線量と同程度であり(地球全体の平均値は2.4mSv)、そのために放射線医学的に、影響があることはほとんどない。
事故による影響を減らそうと奔走した人々や事故現場近くに住んでいた人々の被爆レベルははるかに高かった。これについては、UNSCEAR の評価でかなり詳細に再考察されている。
健康への影響
チェルノブイリ事故は、そのほぼ直後から深刻な放射線による影響を数多く引き起こした。1986年4月26日早朝に現場にいた600人の作業員のうち、134名は高線量の被曝を受け(0.8-1.6Gy)、放射線障害に苦しんだ。このうち28名が事故後3カ月内に死亡した。 その他19名が1987年から2004年の間に死亡したが、その死因はさまざまで、必ずしも放射線被曝と関連付けられるものではない。さらに、UNSCEAR の2008年リポートによると、53万人と言われている復旧活動に携わった作業員のほとんどは、1986年から1990年の間に、0.02Gyから0.5Gyの被曝を受けた。その作業員のグループは今でも、がんやその他の疾病のような、時間が経ってから出てくる影響の潜在的リスクにさらされており、彼らの健康は詳しく追跡される予定になっている。
 ©UNSCER
©UNSCER
チェルノブイリ事故はまた、数百万人の人々が住んでいるベラルーシ、ロシア連邦、ウクライナの各地域を広範囲にわたり放射線によって汚染することにもなった。放射線の被曝にさらされることとなっただけでなく、放射線被曝を制限するために、再定住化、食料供給の変化、そして個人や家族の活動制限という手段がとられたため、事故は、汚染された地域に住んでいた人々の生活も長期にわたって変えてしまった。のちに、このような変化に加え、旧ソビエト連邦が崩壊した際には、経済的、社会的、そして政治的に大きな変革をも伴うこととなった。
最近の20年間は、チェルノブイリ事故によって放出された放射性核種による被曝と後遺症の関係について、特に小児の甲状腺がんについて調査することに関心が集まった。事故直後から数ヶ月の間に甲状腺が受けた被曝線量は、事故当時ベラルーシ、ウクライナ、そしてロシア連邦内の最も影響を受けた地域にいた、高線量の放射性ヨウ素を含む乳を飲んでいた小児または思春期だった子供たちの間で特に高かった。2005年までに、この集団の間で6000を超える甲状腺がんの症例が診断された。これらの大部分は放射性ヨウ素の摂取に起因した。長期間にわたる増加は正確に数値化するのが難しいが、チェルノブイリ事故による甲状腺がんの発生率の増加は、今後何年にもわたって増加するであろうと予想されている。
高線量の被爆を受けた復旧作業に当たったロシア人作業員の間では、白血病の発生率が多少増加したという新たな証拠が現れてきている。しかし他の研究によると、放射線によって誘発された白血病の年間発生率は、被曝してから数十年のうちに低下するだろうと予想されている。さらに、復旧作業にあたった作業員に関する最近の研究では、比較的低線量の被曝によって目の水晶体の混濁が生じた可能性があると推測されている。
放射線障害から生還した106名の患者は、完全に健康が正常化するまで数年を要した。その患者のうち多数は、事故直後から数年の間に、臨床的に有意な割合で放射線によって誘発された白内障を発症した。1987年から2006年の間に、19名の生存者が様々な原因で死亡した。だが、このうち何名かは放射線被曝とは関係のない原因により死亡した。
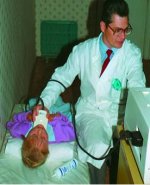 ©UNSCER
©UNSCER
若年時に被曝した人々の甲状腺がん発生率の急増と、作業員の白血病および白内障の発生率増加の徴候とは別に、被爆した人々の間で放射線による固形癌や白血病の発生率の明確な増加はみられていない。また電離放射線と関係のある非悪性疾患があるという証拠もない。しかしながら、実際に受けた被曝ではなく、放射線に対する恐怖による事故への心理的反応は広範にわたってみられた。
時間の経過とともにあらゆるがんが発生する率が増加したことを、チェルノブイリ事故に起因するものだとする傾向があるが、事故の影響があった地域では、事故以前にも増加はみられたということに留意すべきである。さらに、死亡率の全般的な増加はここ数十年の間に旧ソビエト連邦のほぼ全域で報告されており、このことは事故関連の研究の結果を解釈する際に考慮されなければならない。
長期間の電離放射線の被曝によってもたらされる、人体へ遅れて起きる反応の評価は、高線量被曝や動物実験による研究の進展に大きく依存しており、現在解明されていることは限られている。チェルノブイリ事故による被曝に関する研究は、長期間にわたる被曝がもたらす遅発効果について明らかにするかもしれないが、被曝した人々の大部分が受けたのは低線量の放射線であることを考えると、疫学的研究において、がんの発生率あるいはがんによる死亡率が増加すると断定することは難しいであろう。
結論
1986年のチェルノブイリ原子力発電所における事故は、その犠牲者にとって悲劇的な出来事であり、最も大きな影響を受けた人々は、多大な困難に苦しんだ。緊急事態に対応した人々の中には亡くなった人たちもいた。幼少期に被曝した人々や、緊急事態あるいは復旧作業に対応した作業員の人々は、放射線に誘引される影響が増加していくというリスクに直面しているが、圧倒的多数の住民はチェルノブイリ事故からの放射線がもたらす深刻な健康状態を恐れながら生活する必要はない。彼らの大多数は、自然由来の放射線の年間レベルと同じか、その数倍高い放射線量を被曝した。しかし将来的には、放射性物質が減るにつれ、将来受ける被曝線量は緩やかに減少し続ける。チェルノブイリ事故により住民の生活には著しい混乱が起きたが、放射線医学の観点からみると、ほとんどの人々が、将来の健康について概して明るい見通しを持てるだろう。

関連記事
-
毎日新聞7月17日記事。トルコで16日にクーデタが発生、鎮圧された。トルコはロシア、中東から欧州へのガス、石油のパイプラインが通過しており、その影響は現時点で出ていないものの注視する必要がある。
-
欧州の環境団体が7月に発表したリポート「ヨーロッパの黒い雲:Europe’s Dark Cloud」が波紋を広げている。石炭発電の利用で、欧州で年2万2900人の死者が増えているという。
-
池田・本日は専門家を招き、さまざまな視点から問題を考えます。まず「遺伝子組み換え」という言葉に私たちは、なじみがありません。説明をいただけますか。 田部井・私たちの食べる農作物はたいてい品種改良で作られています。遺伝子組み換えはその技術の一つです。品種改良は花粉を交配させ作ってきましたが、遺伝子組み換えは重要な形質を持つ遺伝子を持ってきて植物の種子に加えるというものです。
-
3月11日の大津波により冷却機能を喪失し核燃料が一部溶解した福島第一原子力発電所事故は、格納容器の外部での水素爆発により、主として放射性の気体を放出し、福島県と近隣を汚染させた。 しかし、この核事象の災害レベルは、当初より、核反応が暴走したチェルノブイリ事故と比べて小さな規模であることが、次の三つの事実から明らかであった。 1)巨大地震S波が到達する前にP波検知で核分裂連鎖反応を全停止させていた、 2)運転員らに急性放射線障害による死亡者がいない、 3)軽水炉のため黒鉛火災による汚染拡大は無かった。チェルノブイリでは、原子炉全体が崩壊し、高熱で、周囲のコンクリ―ト、ウラン燃料、鋼鉄の融け混ざった塊となってしまった。これが原子炉の“メルトダウン”である。
-
チェルノブイリ事故によって、ソ連政府の決定で、ウクライナでは周辺住民の強制移住が行われた。旧ソ連体制では土地はほぼ国有で、政府の権限は強かった。退去命令は反発があっても、比較的素早く行われた。また原発周囲はもともと広大な空き地で、住民も少なかった。
-
2011年3月11日に東日本大震災が起こり、福島第一原子力発電所の事故が発生した。この事故により、原子炉内の核分裂生成物である放射性物質が大気中に飛散し、広域汚染がおこった。
-
誰でも見たことがあるだろう、このコンビニのローソンの領収書がかなり変わったものであると、分かるだろうか。3月1日に東京電力福島第1原子力発電所の大型休憩所内に開店した店で発行されたものだ。作業員の人々で店は賑わっていた。こうした町中にある店が原発構内に開店したということは、福島原発事故における周辺環境への危険が低下していることを示すものだ。
-
リウマチの疫学を学ぼう、と公衆衛生大学院への留学を目指していた私の元に、インペリアルカレッジ・ロンドンから合格通知が届いたのは2011年2月28日。その時は、まさかそのわずか11日後に起こる事件のために自分の進路が大きく変わるとは、想像もしていませんでした。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間