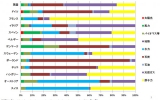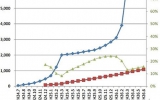今週のアップデート - 太陽光補助政策は妥当か(2014年11月17日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
池田信夫アゴラ研究所所長の論考です。再エネ、太陽光を補助する固定価格買い取り制度を多面的に分析。その必要について疑問を示しています。
2) 1%減イコール1兆円–温室効果ガス数値目標の本当のコスト
温暖化政策研究の第一人者として知られる杉山大志さんの論考です。ガス削減のコストが合理性を欠いていること、特に1トンの太陽光を削減するのに10万円が必要とされる太陽光発電の補助政策が妥当かと、問題を提起しています。
今週のリンク
ウェッジ6月21日記事。朝野賢治電力中央研究所上席研究員の寄稿。太陽光の支援策で、買い取り義務のある20年の間に、どの程度の負担が広がるかの試算です。
ドイツの経済研究機関EFIの今年3月のリポート。ドイツが90年代から始めた、太陽光など再エネ支援システムが、イノベーションや経済に役立たなかったとの結論を示しています。
日経テクノロジー11月14日記事。技術評論家でかつて原発の安全対策を行った桜井淳氏の論考。津波対策では現時点で想定される範囲内では、適切な取り組みを重ねているとの評価です。ただし問題点の検証も連載で行うそうです。
日本経済新聞11月14日記事。CO2排出量が、原発停止の影響で増加していることを示しています。経産省資料「エネルギー需給実績」。
原子力にかかわるさまざまな立場の人が集まった原子力国民会議が12月4日に東京中央集会を行います。その説明と紹介を行いました。出演は諸葛宗男(NPO法人パブリック・アウトリーチ上席研究員)、澤田哲生(東京工業大学原子炉工学助教)の2氏。コーディネーターは、ジャーナリストの石井孝明氏でした。

関連記事
-
政府のグリーン成長戦略では、2050年までに二酸化炭素(CO2)の排出を実質ゼロにすることになっています。その中で再生可能エネルギーと並んで重要な役割を果たすのが水素です。水素は宇宙で一番たくさんある物質ですから、これが
-
エネルギー政策の見直しの機運が高まり、再生可能エネルギーへの期待が広がる。国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP・FI)の特別顧問を務め、環境、エネルギー問題のオピニオンリーダーである末吉竹二郎氏の意見を聞いた。
-
今回も、いくつか気になった番組・報道についてコメントしたい。 NHK BS世界のドキュメンタリー「デイ・ゼロ 地球から水がなくなる日」という番組を見た。前半の内容は良かった。米国・ブラジルなど水資源に変化が現れている世界
-
(GEPR編集部より)この論文は、国際環境経済研究所のサイト掲載の記事から転載をさせていただいた。許可をいただいた有馬純氏、同研究所に感謝を申し上げる。(全5回)移り行く中心軸ロンドンに駐在して3年が過ぎたが、この間、欧州のエネルギー環境政策は大きく揺れ動き、現在もそれが続いている。これから数回にわたって最近数年間の欧州エネルギー環境政策の風景感を綴ってみたい。最近の動向を一言で要約すれば「地球温暖化問題偏重からエネルギー安全保障、競争力重視へのリバランシング」である。
-
全国の電力会社で、太陽光発電の接続申し込みを受けつけないトラブルが広がっている。これは2012年7月から始まった固定価格買い取り制度(FIT)によって、大量に発電設備が設置されたことが原因である。2年間に認定された太陽光発電設備の総発電量は約7000万kW、日本の電力使用量の70%にのぼる膨大な設備である。
-
ここ数回、本コラムではポストFIT時代の太陽光発電産業の行方について論考してきたが、今回は商業施設開発における自家発太陽光発電利用の経済性について考えていきたい。 私はスポットコンサルティングのプラットフォームにいくつか
-
山梨県北杜市(ほくとし)における太陽光発電による景観と環境の破壊を、筆者は昨年7月にGEPR・アゴラで伝えた。閲覧数が合計で40万回以上となった。(写真1、写真2、北杜市内の様子。北杜市内のある場所の光景。突如森が切り開
-
1.太陽光発電業界が震撼したパブリックコメント 7月6日、太陽光発電業界に動揺が走った。 経済産業省が固定価格買取制度(FIT)に関する規則改正案のパブリックコメントを始めたのだが、この内容が非常に過激なものだった。今回
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間