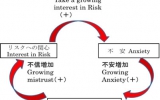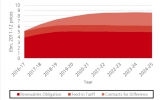米国はパリ協定から離脱するのか
パリ協定については未だ明確なシグナルなし
トランプ大統領は選挙期間中、「パリ協定のキャンセル」を公約しており、共和党のプラットフォームでも、「オバマ大統領の個人的な約束に過ぎないパリ協定を拒否する」としている。しかし、政権発足後、トランプ大統領はパリ協定について旗幟鮮明にしていない。その背景はパリ協定に関して政権内に意見対立があるからだと言われている。
スティーブン・バノン上席戦略官、スコット・プルイットEPA長官等がパリ協定からの離脱を主張している一方、レックス・ティラーソン国務長官、イヴァンカ・トランプ氏及びジャレット・クシュナー大統領上級顧問が残留を主張しているとされ、「イヴァンカの反対により、近々発出される大統領令の中にパリ協定を否定する文言を入れることが見送られた」との観測記事もある。
パリ協定離脱派の論理
米国内でパリ協定を否定する議論としては、理念的に否定するもの、手続き面の瑕疵を指摘するもの、内容を問題視するもの等が絡み合っている。理念的に否定するものは、そもそも温暖化問題、特に人類起源の温室効果ガスと地球温暖化の相関関係は科学的に証明されておらず、温室効果ガス削減の国際的・国内的な取り組み自体が無意味であるとする。この考え方に立てばUNFCCCもパリ協定もナンセンスということになる。トランプ政権に根強いマルチラテラリズムへの懐疑的な考え方とも通ずるものがある。
トランプ大統領の最側近とされるスティーブン・バノン氏が会長を務めていた右派ニュースサイトBreitbart はイヴァンカがパリ協定離脱に関する文言挿入を阻止したとの上記記事に反発し、「イヴァンカが何を言おうとトランプ大統領は温暖化について動揺してはいけない」、「人類起源の温暖化は問題ではなく、これを問題視する人はいかさま師、嘘つき、バカ、サクラである」との激烈な記事を掲載している。
手続き面の瑕疵を問題視するものは、本来、パリ協定は条約批准権限を有する上院のプロセスを経るべきであったにもかかわらず、オバマ大統領は行政協定で批准を行ったことを批判する。共和党関係者の中には、「プレッジ&レビューに基づくパリ協定は、ブッシュ政権が目指していた方向性と本質的には同じ。
しかしオバマ大統領が上院のプロセスを経ずに米国の批准を急ぐことにより、パリ協定の発効を早め、次期政権が共和党政権になっても4年間は離脱できないようにしたため、上院がパリ協定を支持する可能性はゼロになった」という声も聞かれる。
パリ協定の内容を問題視するものとしては、「米国の削減目標(2025年までに2005年比▲26-28%減)は産業・雇用に悪影響を与える」「米国の目標設定にあたって産業界との協議が一切なされていない」、「2030年まで排出量をいくら増やしても良いという中国の目標に比較して米国の目標は譲歩し過ぎである」等がある。
パリ協定残留派の論理
政権内でパリ協定残留を支持する議論としては、「選挙でトランプを支持した人々は国内の規制緩和や雇用創出には関心があるが、パリ協定離脱そのものにはこだわりはない」、「パリ協定は京都議定書と異なり、目標達成に法的拘束力がなく、目標さえ見直せば米国に対する実害はない」、「パリ協定離脱は米国の国際的地位に悪影響を与える」、「交渉テーブルには席を確保しておいた方がよい」、「欧州は米国のパリ協定残留を強く望んでいる。交渉材料として使えば良い」等があげられる。
最後の論点に関連して、トランプ政権の政策アドバイザーが「米国がパリ協定に残留するためには化石燃料からの排出量を削減する技術の開発・普及を世界が支持することが条件」と欧州委員会関係者に語ったとの記事もある。ただし、クリーンパワープランの廃止など、国内温暖化対策を大幅に後退させる以上、政権部内でパリ協定残留を支持する者も、オバマ目標の見直しを当然の前提としている。
パリ協定をめぐる3つのシナリオ
以上を踏まえるとトランプ政権のパリ協定への対応として以下のシナリオが考えられる。
シナリオ1:UNFCCCそのものから離脱し、パリ協定もろとも1年で離脱する。
シナリオ2:UNFCCCには残留するものの、大統領令、パリ協定の上院送付・否決により、パリ協定からは離脱する旨の米国の意思を対外的に明確にし、協定上の手続きに則って4年かけて離脱する。パリ協定の詳細ルール策定交渉には代表団を送らない。
シナリオ3:UNFCCC、パリ協定に残留するが、オバマ政権の2025年目標(及び2050年の長期戦略)を下方修正する(あるいは単に無視する)。パリ協定の詳細ルール策定交渉に参加し、中国等の新興国に甘いルール策定を阻止する。
今年のG7、G20の議長国イタリア、ドイツはサミットで気候変動、パリ協定を取り上げたいと考えている。先般のG20財務大臣会合・中央銀行総裁会議共同声明からはグリーンファイナンスや気候変動、パリ協定に対する言及が一切入らなかった。トランプ・メルケル首脳会談でも本件が突っ込んで話し合われたとの報道はない。欧州もトランプ政権を過度に刺激し、逆効果にならないよう注意深く対応しているのだろう。この状況がサミットまで続くのか、それまでにトランプ政権が上記シナリオのいずれかを選ぶのか、注目される。

関連記事
-
自民党政権になっても、原発・エネルギーをめぐる議論は混乱が残っています。原子力規制委員会が、原発構内の活断層を認定し、原発の稼動の遅れ、廃炉の可能性が出ています。
-
リスク情報伝達の視点から注目した事例がある。それ は「イタリアにおいて複数の地震学者が、地震に対する警告の失敗により有罪判決を受けた」との報道(2012年 10月)である。
-
菅首相の16日の訪米における主要議題は中国の人権・領土問題になり、日本は厳しい対応を迫られると見られる。バイデン政権はCO2も重視しているが、前回述べた様に、数値目標の空約束はすべきでない。それよりも、日米は共有すべき重
-
きのうのアゴラシンポジウムでは、カーボンニュートラルで製造業はどうなるのかを考えたが、やはり最大の焦点は自動車だった。政府の「グリーン成長戦略」では、2030年代なかばまでに新車販売の100%を電動車にすることになってい
-
気候変動開示規則「アメリカ企業・市場に利益」 ゲンスラーSEC委員長 米証券取引委員会(SEC)のゲンスラー委員長は26日、米国商工会議所が主催するイベントで講演し、企業の気候変動リスク開示案について、最終規則を制定でき
-
トランプ次期米国大統領の外交辞書に儀礼(プロトコール)とかタブーという文字はない。 大統領就任前であろうが、自分が会う必要、会う価値があればいつなんどき誰でも呼びつけて〝外交ディール〟に打って出る。 石破のトランプ詣でお
-
一石?鳥 いわゆる「核のごみ」(正式名称:高レベル放射性廃棄物)処分については昨今〝一石三鳥四鳥〟などというにわかには理解しがたい言説が取りざたされている。 私たちは、この核のごみの処分問題をめぐって、中学生を核としたサ
-
11月23日、英国財務省は2017年秋期予算を発表したが、その中で再エネ、太陽光、原子力等の非化石予算を支援するために消費者、産業界が負担しているコストは年間90億ポンド(約1.36兆円)に拡大することが予想され、消費者
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間