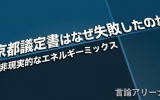今週のアップデート - 日本以外で伸びる原子力産業(2015年7月21日)
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
今週のアップデート
福島事故の後、日本勢の勢いが鈍り、中露企業の動きが活発になっている事実を紹介します。このまま一つの産業が縮小してもいいのでしょうか。言論アリーナの紹介。近日中に記事を公開します。
自民党の電力安定推進議員連盟が、原子力規制をめぐる改革案をまとめました。内容は、抜本的に現在の規制の姿を変えるもの。この報道がほとんど行われていないために、これを紹介します。
提携する国際環境経済研究所の論考の掲載。松本真由美東京大学客員准教授の米国の環境政策のリポート、総論部分です。大国ゆえにかなり大がかりなものになっています。
今週のリンク
日本経済新聞7月17日記事。規制委の有識者会合は北陸電力の志賀原発(石川県)について、活断層の可能性があるという報告をまとめました。再稼動は当面困難になります。事業者は当然、反発。このおかしな一連の活断層をめぐる騒動を、終わらせるべきでしょう。
WNN(ワールド・ニュークリアー・ニュース)7月16日記事。原題は「Chinese nuclear giant officially launched」。中国政府主導で、原子力の輸出・生産企業の統合が進み、原子力発電所の運営や投資事業を手掛ける中国電力投資集団(CPI)と、国営エンジニアリング会社で原子炉開発も行う国家核電技術(SNPTC)とが合併し、新会社の「国家電力投資集団」(SPI)が北京で正式に設立しました。これで中国の原子力グループは3つに集約。SPIは売電収入年2000億元(4兆円)の大企業です。
朝日新聞7月20日記事。朝日新聞の調査で、原発の工事会社と地方政治家の関係が示されました。一部の地方の産業の中心が建設会社であり、違法ではありませんが、好ましいことではありません。こうしたことの透明性を確保していくことが必要です。
日本経済新聞7月17日記事。日本の温暖化ガスの削減目標が、首相出席の会議で正式に決まりました。しかし、この目標は、かなり「詰めて」いません。(参考・池田信夫「温室効果ガス26%削減は不可能である」)見切り発車は大丈夫なのでしょうか。
ワシントンポスト7月17日記事。イランをめぐる核合意が成立しました。査察の徹底化、そしてイラン禁輸の緩和が内容です。これについて、イラン原油の輸出によって、エネルギー問題の影響は長期的に現れるでしょう。米国の意見ですが、賛否両論が出ていたので紹介します。

関連記事
-
再生可能エネルギーの先行きについて、さまざまな考えがあります。原子力と化石燃料から脱却する手段との期待が一部にある一方で、そのコスト高と発電の不安定性から基幹電源にはまだならないという考えが、世界のエネルギーの専門家の一般的な考えです。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
東日本大震災から2年。犠牲者の方の冥福を祈り、福島第一原発事故の被害者の皆さまに心からのお見舞いを申し上げます。
-
電力中央研究所の朝野賢司主任研究員の寄稿です。福島原発事故後の再生可能エネルギーの支援の追加費用総額は、年2800億円の巨額になりました。再エネの支援対策である固定価格買取制度(FIT)が始まったためです。この補助総額は10年の5倍ですが、再エネの導入量は倍増しただけです。この負担が正当なものか、検証が必要です。
-
アゴラ研究所・GEPRは12月8日にシンポジウム「持続可能なエネルギー戦略を考える」を開催しました。200人の方の参加、そしてニコニコ生放送で4万人の視聴者を集めました。
-
自民党政権になっても、原発・エネルギーをめぐる議論は混乱が残っています。原子力規制委員会が、原発構内の活断層を認定し、原発の稼動の遅れ、廃炉の可能性が出ています。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
-
アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。
動画
アクセスランキング
- 24時間
- 週間
- 月間